
「AIアシスタントは便利だけど、会社の機密情報や個人情報を入力するのは少し不安…」と感じていませんか?
本記事では、そんなあなたのための「AIアシスタントの安全な使い方」を徹底解説。情報漏洩がなぜ起こるのかという仕組みから、ChatGPTやGeminiですぐに実践できる具体的なセキュリティ設定、そして安全なツールの選び方まで、わかりやすくご紹介します。
この記事を読めば、情報漏洩のリスクを正しく理解し、具体的な対策を自分で実行できるようになります。漠然とした不安が解消され、もうセキュリティを過度に恐れる必要はありません。読後は、AIアシスタントのパワーを安全かつ最大限に引き出し、自信を持って日々の業務や学習を加速させられるようになっているでしょう。
なぜ危険?AIアシスタントに潜む情報漏洩リスクの仕組み

業務の効率を飛躍的に向上させるAIアシスタントですが、その利便性の裏には情報漏洩のリスクが潜んでいます。なぜリスクが存在するのか、まずはその仕組みから正しく理解しましょう。
入力したデータはどこへ?AIアシスタントの基本的なデータフロー
私たちがAIアシスタントのチャット画面に入力したテキストやアップロードしたファイルは、自分のパソコンの中だけで処理されているわけではありません。データはインターネットを通じて、AIを開発・提供している企業のサーバーに送信され、そこで処理された結果が私たちの画面に表示されます。
【データの基本的な流れ】
パソコンやスマートフォンのチャット画面に質問や指示を入力する。
入力されたデータはインターネットを経由して、AIのサーバーへ送られる。
サーバー上で大規模言語モデル(LLM)がデータを解釈し、回答を作成する。
生成された回答が再びインターネットを経由して、ユーザーの画面に表示される。
この「サーバーへの送信」というプロセスがあるため、入力した情報が意図せず外部に漏れる可能性がゼロではないのです。
AIの学習データとして情報が二次利用される可能性
最も注意すべきリスクの一つが、入力した情報がAIアシスタントの「学習データ」として利用される可能性です。
AIは、より賢く、より自然な回答を生成するために、膨大な量のテキストデータを学習しています。多くの無料AIアシスタントサービスでは、ユーザーが入力した会話の履歴を、サービス品質の改善やAIモデルの精度向上のための「教科書」として再利用することがあります。
もし、あなたが入力した会話に個人名や会社の内部情報が含まれていた場合、それがAIの知識の一部となり、将来的に他のユーザーへの回答として、形を変えて表示されてしまうリスクが否定できません。
実際にあった情報漏洩の事例から学ぶべき教訓
過去には、海外企業で従業員が社外秘のソースコードをAIチャットに入力してデバッグさせた結果、その情報が漏洩してしまったという事例が報告されています。また、特定のAIアシスタントで、他のユーザーのチャット履歴のタイトルが見えてしまうという不具合が発生したこともありました。
これらの事例から学ぶべき教訓は、「入力した情報は、自分の管理下を離れる」という意識を常に持つことです。一度インターネット上に送信されたデータは、完全に消去したり、その後の利用をコントロールしたりすることが非常に困難になることを覚えておきましょう。
特に注意すべき3つの情報(個人情報・企業の機密情報・非公開情報)
具体的に、どのような情報をAIアシスタントに入力すべきではないのでしょうか。特に以下の3種類の情報は、リスクが非常に高いため、絶対に入力しないようにしてください。
氏名、住所、電話番号、メールアドレス、マイナンバー、クレジットカード番号、特定の個人を識別できる情報など。
顧客リスト、財務情報、未公開の製品情報、人事情報、社内システムのID・パスワード、非公開のソースコードなど。
公開前の研究データ、論文の草稿、個人的なプライベートの悩みなど、他者に知られたくない情報全般。
【実践編】主要AIアシスタントの安全なセキュリティ設定

情報漏洩のリスクを理解した上で、次はその対策を実践しましょう。ここでは、主要なAIアシスタントサービスで今すぐできる具体的なセキュリティ設定を解説します。
まず実践したい対策の基本|入力する情報を工夫する
最も簡単で効果的な対策は、入力する情報そのものを工夫し、機密情報を含めないようにすることです。
- 匿名化・抽象化する:固有名詞や具体的な数値を、一般的な言葉や変数に置き換えましょう。
- 悪い例:「株式会社A商事の鈴木太郎様(電話番号:090-XXXX-XXXX)への納期遅延のお詫びメールを作成してください。注文番号はB-12345です。」
- 良い例:「取引先の担当者様への納期遅延のお詫びメールを作成してください。製品名は『製品X』です。」
- 分割して質問する:一度にすべての情報を与えず、文脈を切り離して複数回に分けて質問することで、情報の関連性を断ち切ることができます。
【ChatGPT】チャット履歴と学習をオフにする設定(オプトアウト)
OpenAI社のChatGPTでは、会話履歴を保存せず、AIの学習にも利用させない「オプトアウト」設定が可能です。
【設定手順】
- ChatGPTにログインし、画面左下の自分のアカウント名をクリックします。
- メニューから「Settings(設定)」を選択します。
- 「Data controls(データ制御)」の項目を開きます。
- 「Chat history & training(チャット履歴とトレーニング)」のトグルスイッチをオフ(緑色から灰色へ)にします。
この設定をすると、過去の会話履歴は表示されなくなりますが、プライバシーは格段に向上します。
【Google Gemini】アクティビティを無効化しプライバシーを保護する設定
GoogleのAIアシスタントであるGemini(旧Bard)でも、アクティビティ(履歴)を保存しない設定が可能です。
【設定手順】
- Geminiの画面左側にあるメニューから「アクティビティ」をクリックします。
- 「Gemini アプリのアクティビティ」という項目で、「オフにする」を選択します。
- 確認画面が表示されるので、内容を確認して「オフにする」または「オフにしてアクティビティを削除」を選択します。
Googleアカウント全体のアクティビティ設定と連動しているため、設定内容をよく確認することが重要です。
【Microsoft Copilot】データ保護の仕組みと設定の確認方法
Microsoft Copilot(旧Bingチャット)は、Microsoftアカウントでサインインして利用する場合、法人向けの「Copilot for Microsoft 365」を利用する場合でデータの扱いが異なります。
特に、法人向けライセンスで提供される「Copilot for Microsoft 365」では、「商用データ保護」が標準で有効になっており、入力したデータが組織外に漏洩したり、AIの学習に使われたりすることはないと明記されています。個人のMicrosoftアカウントで利用する場合は、他のサービス同様、入力情報に注意が必要です。
Adobe製品などに搭載されたAIアシスタント機能の注意点
近年、Adobe AcrobatのPDF要約機能など、既存のツールにAIアシスタントが搭載されるケースが増えています。これらの機能を利用する際は、そのツールのプライバシーポリシーを確認し、ファイルの内容がどのように扱われるかを理解することが不可欠です。多くの場合、機能向上のためにコンテンツが利用される可能性があるため、機密文書を扱う際は特に注意し、必要に応じて機能を無効化する設定も検討しましょう。
安全性の高いAIアシスタントの選び方と比較ポイント

どのAIアシスタントを選ぶかは、セキュリティを考える上で非常に重要です。ここでは、安全性の高いサービスを見分けるための比較ポイントを解説します。
プライバシーポリシーで必ず確認すべき3つの項目
サービスの利用規約やプライバシーポリシーは長く複雑ですが、少なくとも以下の3点は必ず確認しましょう。
「サービス改善」「AIモデルの学習」といった目的でデータが利用されるかどうかが明記されています。
ユーザーが自分のデータをAIの学習から除外する(オプトアウトする)権利と、その具体的な方法が記載されているかを確認します。
あなたのデータが、関連会社や提携企業などの第三者に提供される可能性があるかを確認します。
セキュリティ認証(SOC 2など)の有無をチェックする
SOC 2(ソックツー)は、外部の監査機関が企業のセキュリティ体制などを評価する国際的な認証です。この認証を取得しているサービスは、データの取り扱いに関する厳格な基準をクリアしている証となり、信頼性の一つの指標となります。法人向けサービスを選ぶ際には、特に重要なチェックポイントです。
【目的別】個人利用と法人利用での選び方の違い
無料プランでも、今回紹介したオプトアウト設定をしっかり行えば、多くのケースで安全に利用できます。利便性とプライバシー設定のしやすさを重視して選びましょう。
無料プランの利用は原則として避けるべきです。データのプライバシーが保護され、管理機能が充実した法人向けの有料プラン(例:ChatGPT Enterprise, Copilot for Microsoft 365)の契約を強く推奨します。
無料版と有料版のセキュリティレベルはどれくらい違うのか
一般的に、無料版と有料版の最も大きな違いは「商用データ保護」の有無です。
入力データがAIの学習に利用される可能性があります。
入力データは学習に利用されず、組織内でのみ扱われることが保証されています。また、アクセス管理や監査ログなど、企業に必要なセキュリティ機能が充実しています。
機密情報を扱う場合は、コストをかけてでも有料の法人向けプランを選択することが、結果的に企業をリスクから守ることにつながります。
【法人向け】企業でAIアシスタントを導入する際の安全ガイドライン
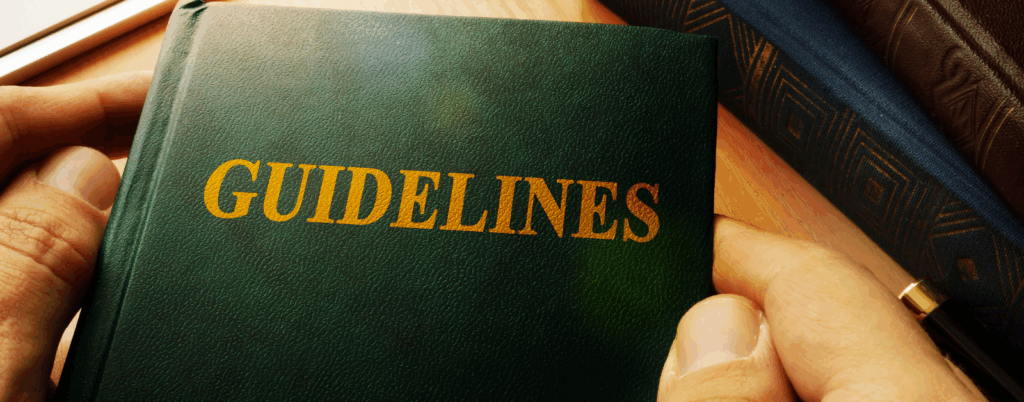
企業としてAIアシスタントを安全に活用するためには、個人のリテラシー任せにするのではなく、組織としてのルール作りが不可欠です。
なぜ今、社内AI利用ガイドラインが必要なのか
ガイドラインがない状態では、従業員が知らず知らずのうちに機密情報を漏洩させてしまう「シャドーIT」のリスクが高まります。明確なルールを設けることで、従業員は安心してAIを活用でき、企業は情報資産を守ることができます。AIの利用を禁止するのではなく、安全な使い方を定義することが、企業の競争力を高める鍵となります。
ガイドラインに盛り込むべき必須項目リスト
社内ガイドラインには、少なくとも以下の項目を盛り込むことを推奨します。
- 利用目的の定義:どのような業務での利用を許可・推奨するかを明確にする。
- 利用可能なツールの指定:会社として利用を許可するAIアシスタントサービスをリスト化する。
- 入力禁止情報の明確化:個人情報、顧客情報、機密情報など、入力してはいけない情報の具体例を定義する。
- セキュリティ設定の義務付け:オプトアウト設定など、必須で行うべきセキュリティ設定の手順を示す。
- 利用結果の取り扱い:AIが生成した文章やコードを業務で利用する際の注意点(著作権、ファクトチェックなど)を定める。
- 問題発生時の報告ルート:情報漏洩の懸念が生じた場合の報告先と手順を明確にする。
従業員へのセキュリティ教育で伝えるべきこと
ガイドラインを作成するだけでなく、その背景にあるリスクと目的を全従業員に周知することが重要です。「なぜこのルールが必要なのか」を丁寧に説明し、AIを「賢く、安全に使う」意識を組織全体で醸成していきましょう。
セキュリティが担保された法人向けAIサービスとは
前述の通り、「ChatGPT Enterprise」や「Azure OpenAI Service」、「Copilot for Microsoft 365」などが、法人向けの代表的な高セキュリティサービスです。これらのサービスは、入力データのプライバシー保護を契約で保証しており、企業が求める管理機能やサポート体制を備えています。
まとめ『AIアシスタントを正しく理解し、安全に活用しよう』
本記事では、AIアシスタントに潜む情報漏洩のリスクとその仕組み、そして私たちが今すぐ実践できる具体的な安全対策までを解説してきました。
【この記事のポイント】
- AIアシスタントへの入力情報は、開発企業のサーバーに送信される。
- 入力データがAIの学習に利用され、情報漏洩につながるリスクがある。
- 「オプトアウト設定」と「入力情報の工夫」が個人でできる最も有効な対策。
- 企業は、ガイドラインを策定し、セキュリティが担保された法人向けプランを利用すべき。
AIは、もはや私たちの仕事や学習に欠かせないパートナーとなりつつあります。リスクを正しく理解し、適切な対策を講じることで、その計り知れない恩恵を安全に享受することができます。この記事を参考に、あなたも今日から「賢いAIユーザー」として、自信を持ってその一歩を踏み出してください。


