
「アパート経営で安定収入を得たいけど、空室や管理の手間が不安…」 そんなお悩みを解決する選択肢として『サブリース』を不動産会社から提案されていませんか?
本記事では、サブリースとは何か、その仕組みからメリットはもちろん、見落としがちなデメリットや契約前に必ず知るべき注意点までを網羅的に解説します。“家賃保証”という言葉を鵜呑みにして後悔しないために、専門家として知っておくべき不動産のプロとして知っておくべき知識をまとめました。
この記事を読み終える頃には、サブリースの全体像が明確になり、不動産会社の提案を冷静に見極め、ご自身で最適な判断を下せるようになっているはずです。

サブリースとは?初心者にも分かる基本的な仕組み
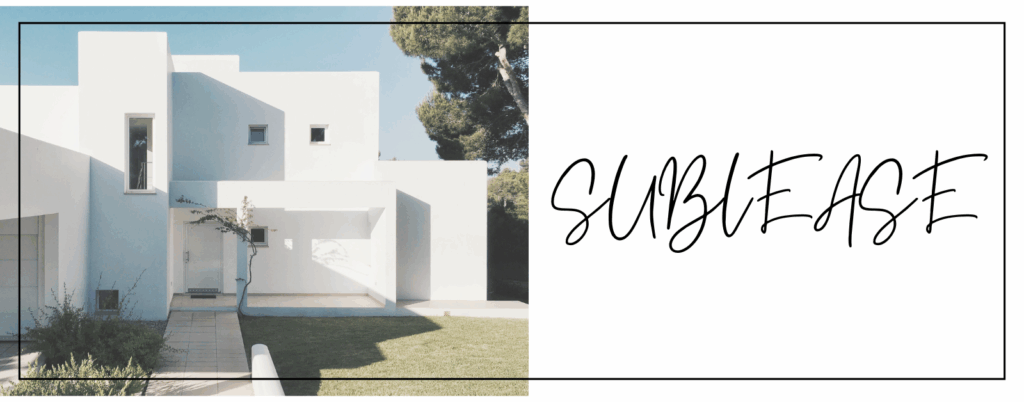
サブリースという言葉は聞いたことがあっても、その仕組みを正確に理解している方は少ないかもしれません。まずは、不動産投資の第一歩として、サブリースの基本をしっかりと押さえましょう。
サブリース契約の全体像を解説
サブリースとは、不動産会社がオーナーから物件を一括で借り上げ、その物件を入居者に転貸(てんたい)する仕組みのことです。「又貸し(またがし)」と言うとイメージしやすいかもしれません。
この契約形態では、登場人物が3者登場します。
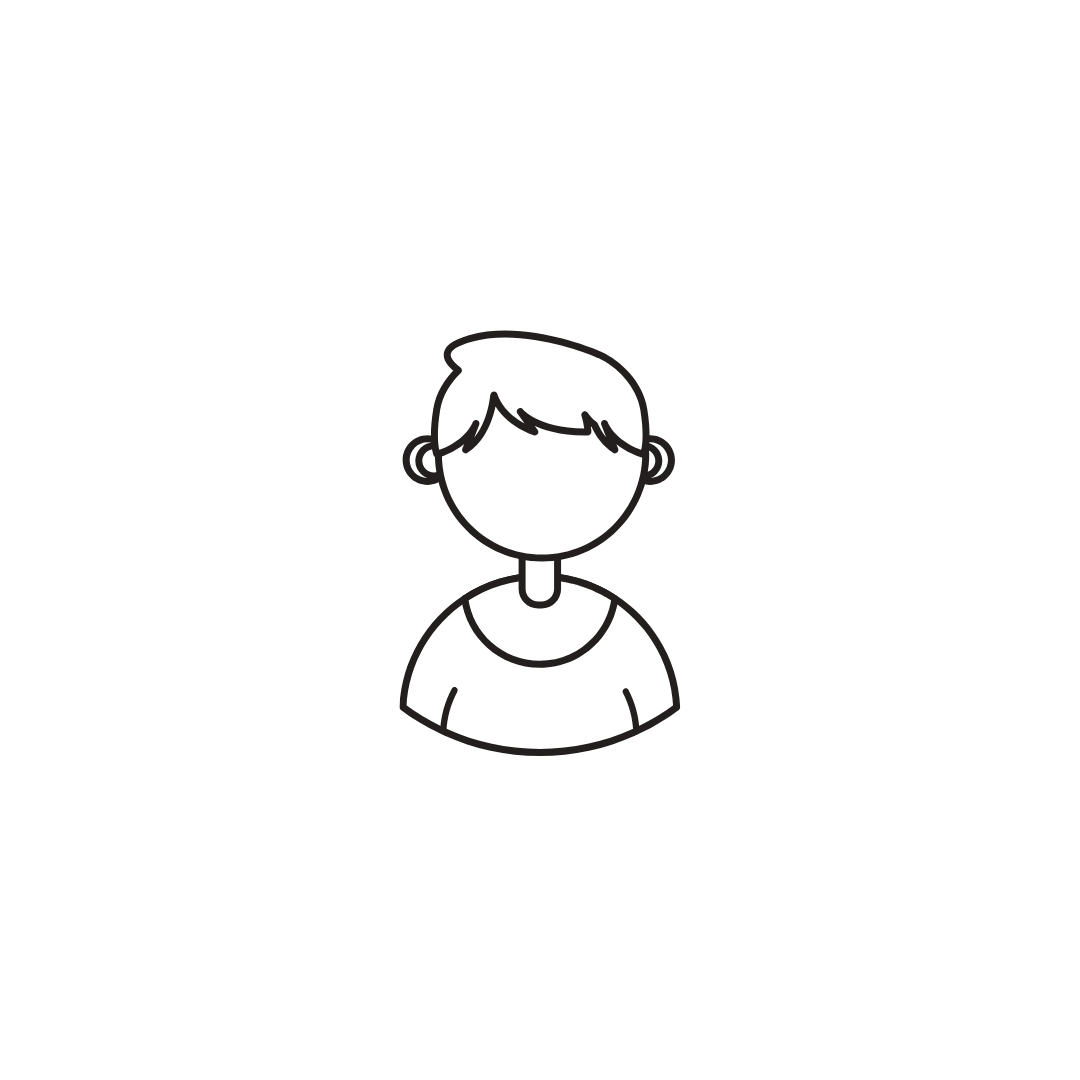 オーナー
オーナー物件の所有者。サブリース会社に物件を貸し出す「貸主」です。
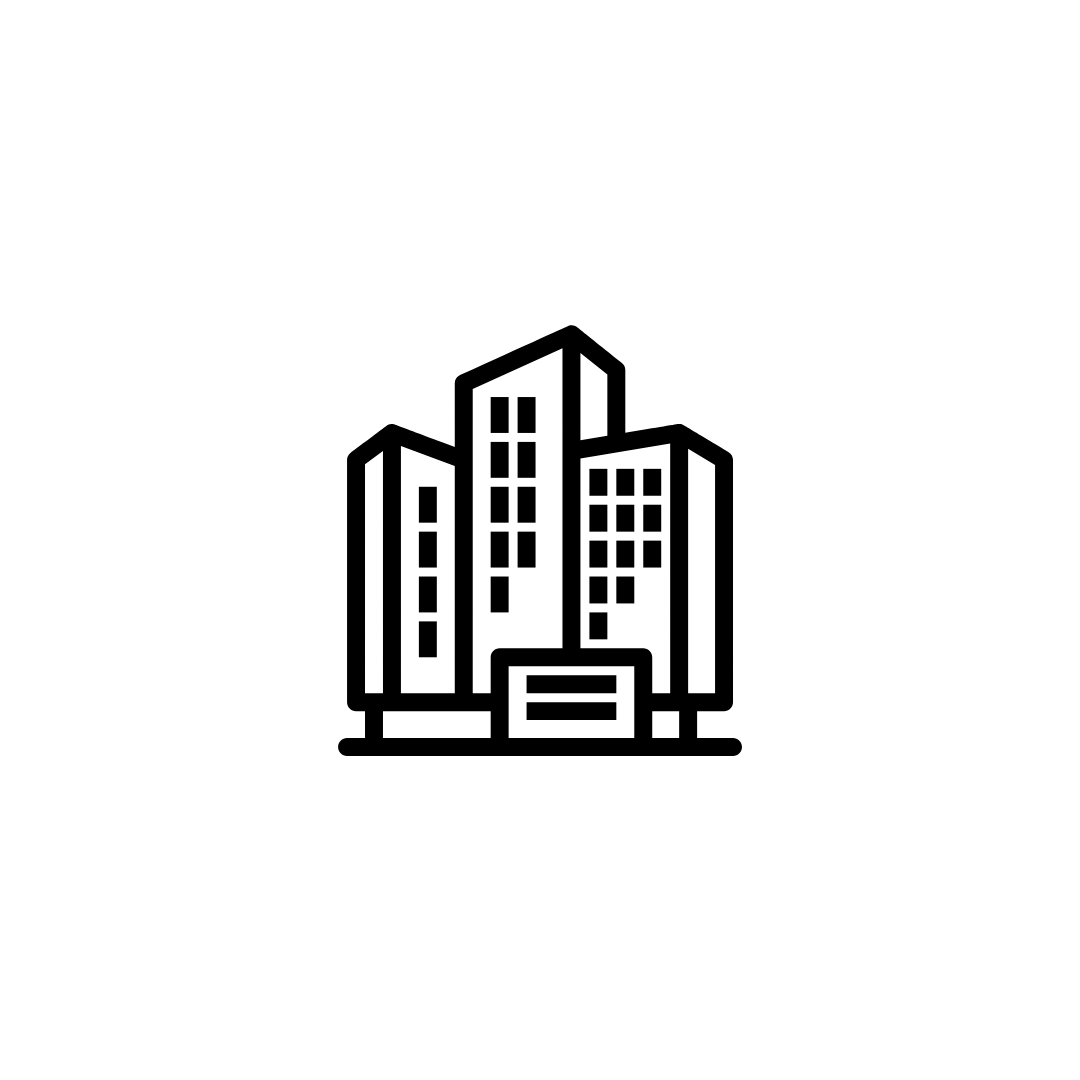
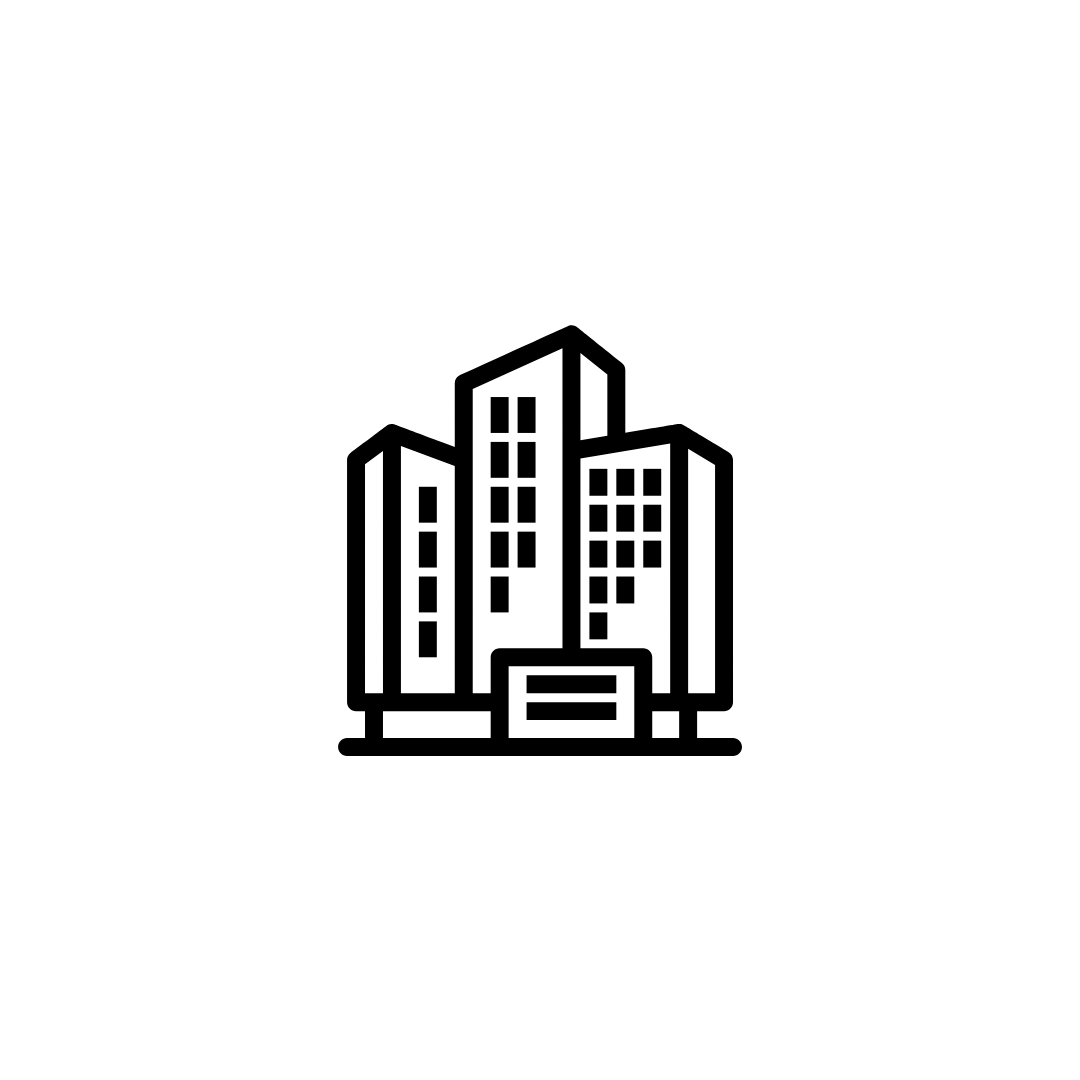
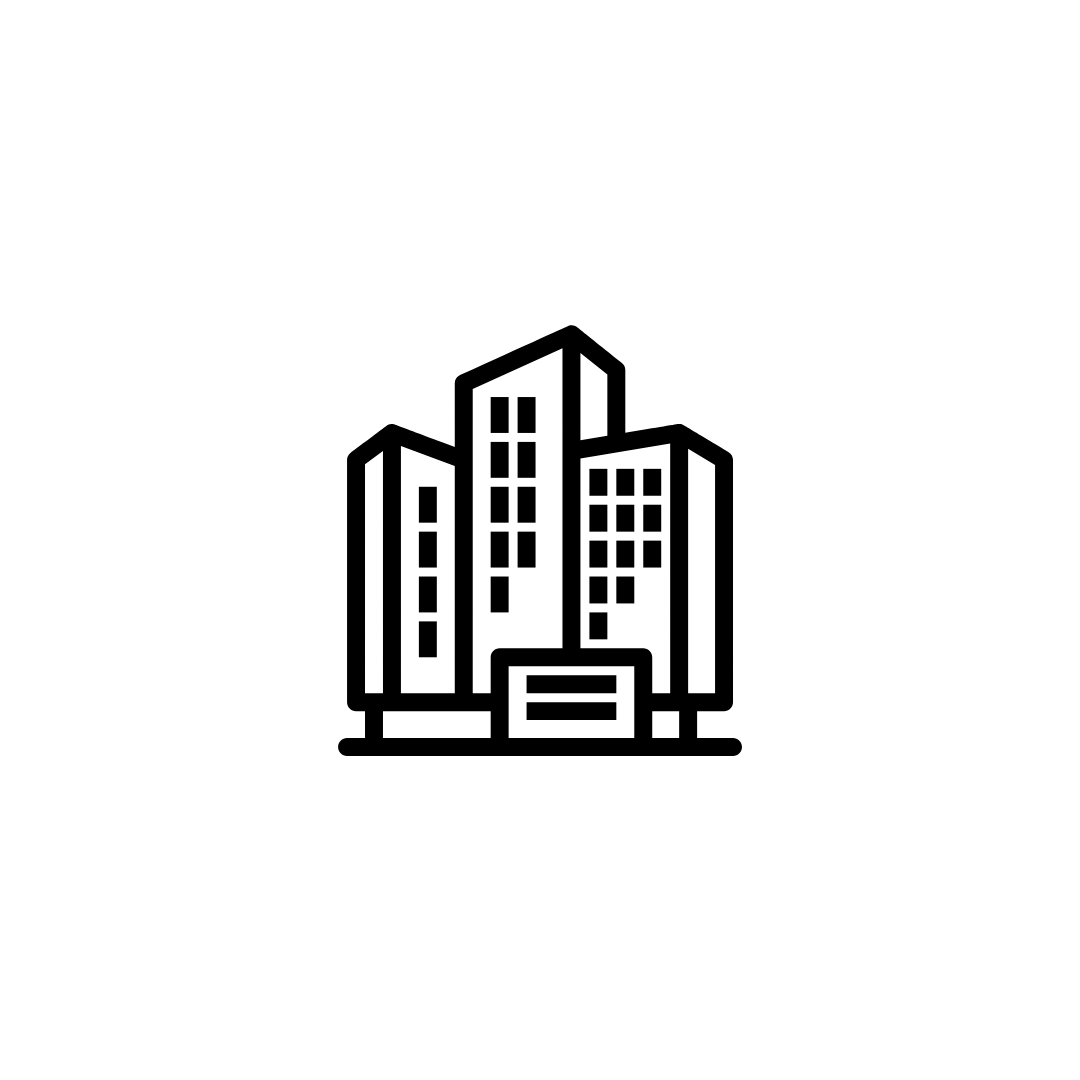
オーナーから物件を借り、入居者に貸し出す「借主」であり「転貸人」です。
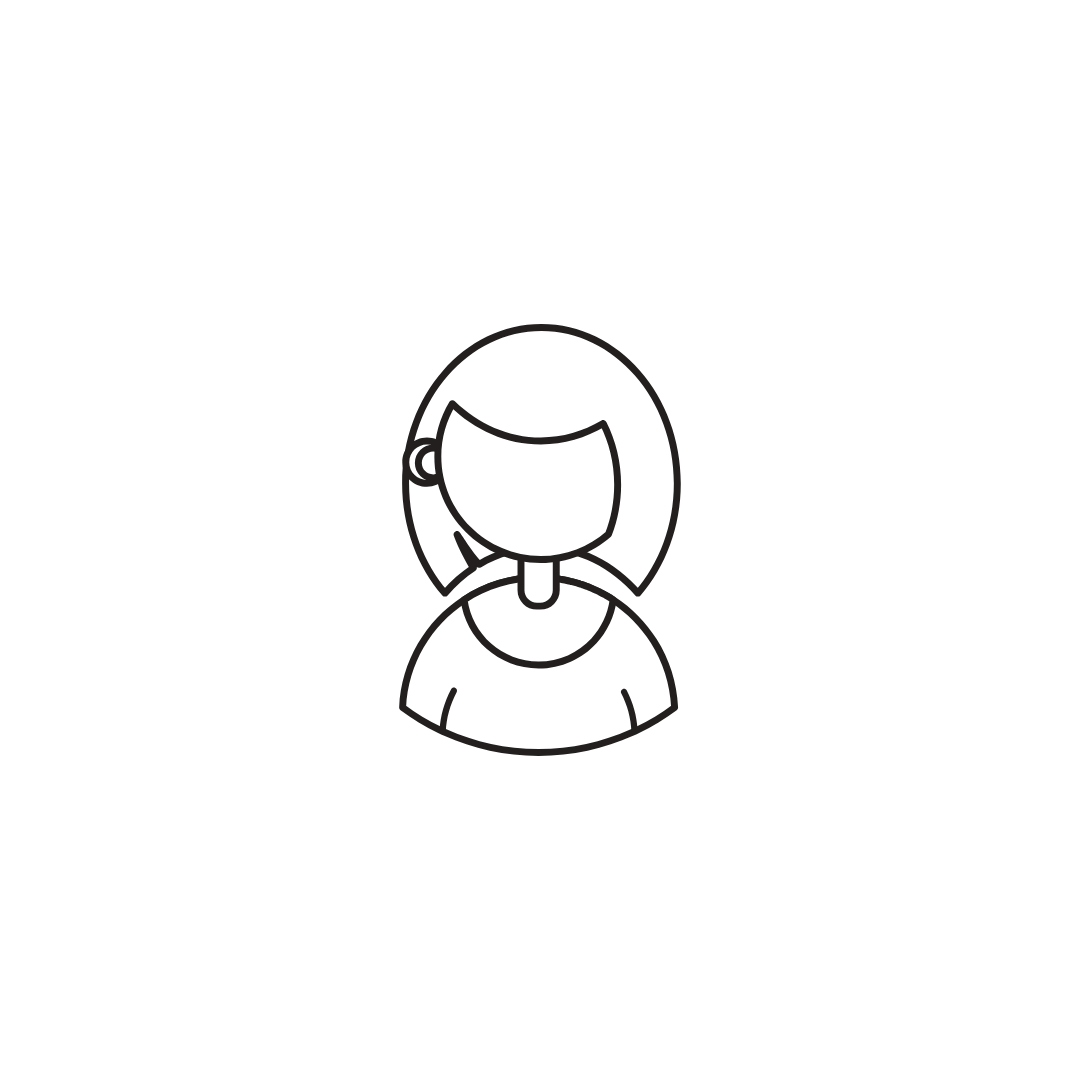
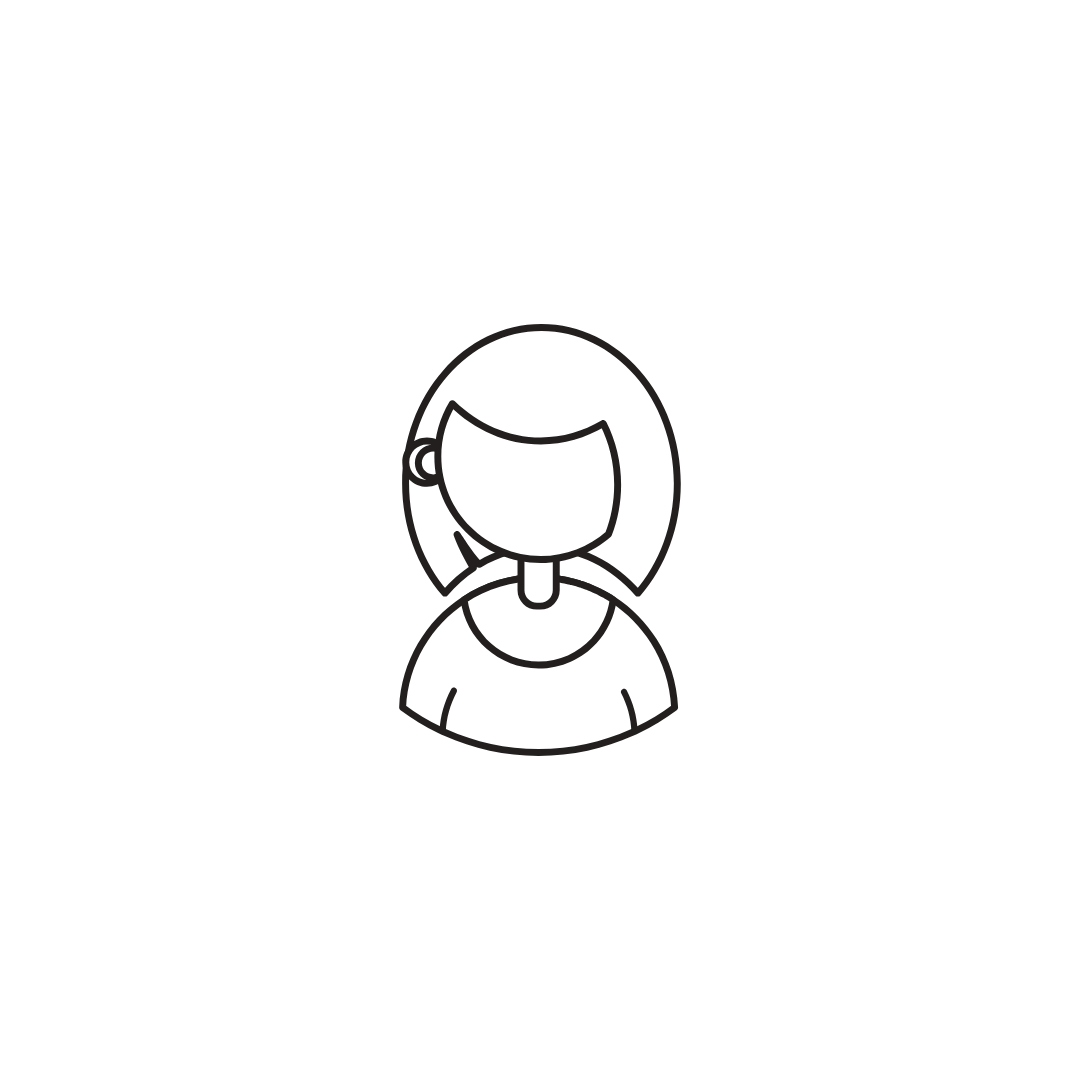
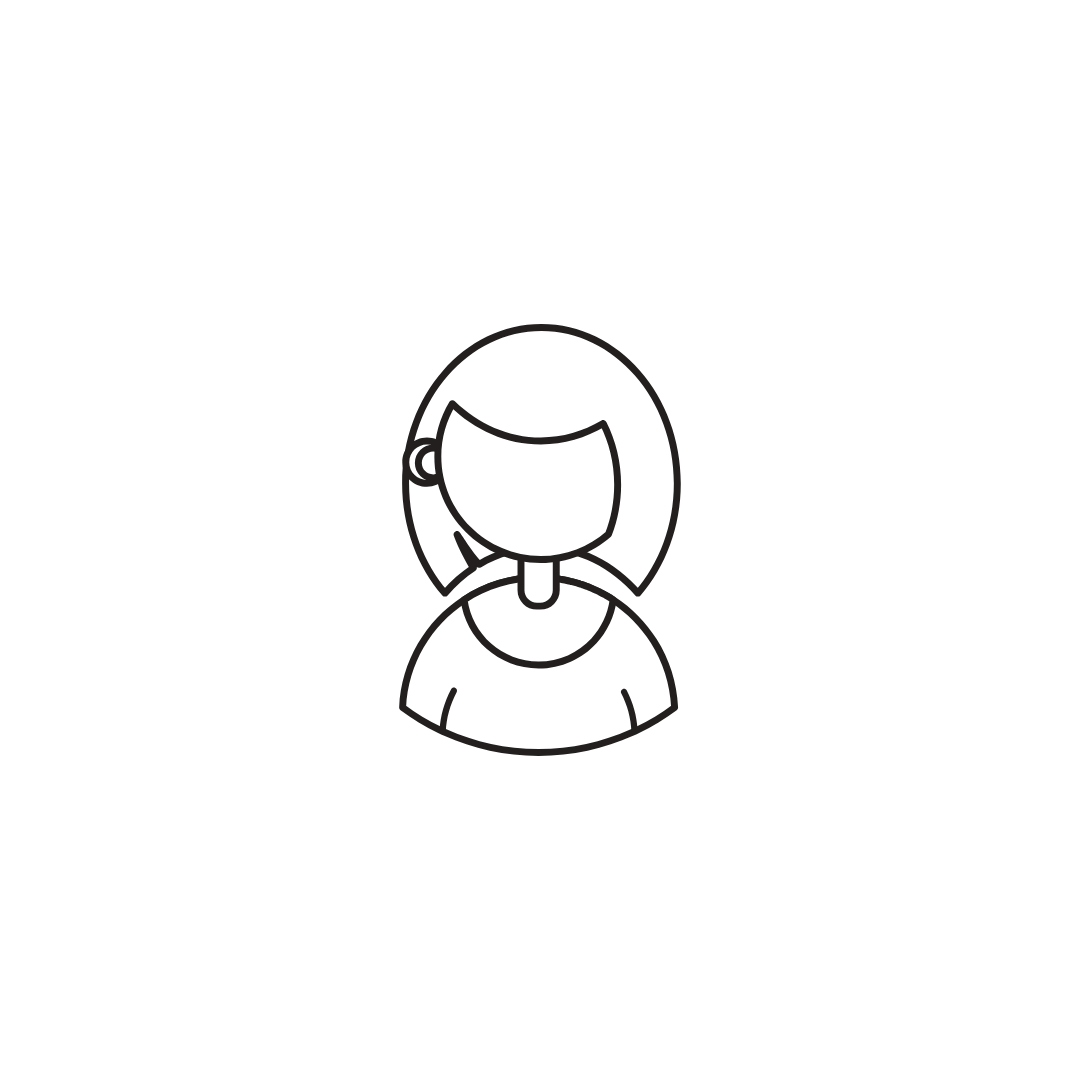
サブリース会社から物件を借りる「転借人」です。
この仕組みの最大の特徴は、オーナーと入居者の間にサブリース会社が入る点です。オーナーはサブリース会社と「賃貸借契約」を結び、サブリース会社は入居者と「転貸借契約」を結びます。
そのため、実際の入居者がいるかいないかに関わらず、オーナーはサブリース会社から毎月一定の賃料を受け取ることができます。これが「家賃保証」や「空室保証」という名称で呼ばれる、基本的な仕組みです。


「一括借り上げ」との違いは?
サブリースと共によく使われる言葉に「一括借り上げ」があります。この二つの言葉は、厳密には意味が異なります。
- 一括借り上げ:オーナーがサブリース会社に物件を貸す行為(インプット)を指します。
- サブリース:サブリース会社が入居者に物件を転貸する行為(アウトプット)を指します。
このように、指している行為の側面が違うだけで、実際には「一括借り上げ」と「サブリース」は一連の事業モデルを指す言葉として、ほぼ同義で使われることがほとんどです。本記事でも、これらを一体の仕組みとして解説していきます。
「管理委託」との決定的な違いは?
不動産経営の手間を省くもう一つの方法に「管理委託」があります。サブリースと混同されがちですが、その性質は全く異なります。決定的な違いは、空室や家賃滞納のリスクを誰が負うかです。
| 比較項目 | サブリース契約 | 管理委託契約 |
| 契約形態 | 賃貸借契約 | 業務委託契約 |
| オーナーの立場 | 貸主 | 貸主 |
| 不動産会社の立場 | 借主 | 管理の代理人 |
| 入居者との契約 | サブリース会社 | オーナー |
| 空室・滞納リスク | サブリース会社が負う | オーナーが負う |
| オーナーの家賃収入 | 一定額(保証賃料) | 変動(家賃 – 管理料) |
| 礼金・更新料収入 | 原則、会社のもの | 原則、オーナーのもの |
サブリースは不動産会社が「借主」としてリスクを負うため、オーナーの収入は安定しますが、手数料は高め(一般的に家賃の10%~20%)です。一方、管理委託はあくまで「代理人」のため、リスクはオーナーが負いますが、手数料は比較的安価(家賃の3%~5%程度)です。
オーナーにとってのサブリース契約、3つのメリットとは?


サブリースの仕組みを理解したところで、次にオーナーにとって具体的にどのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。
メリット1【空室や家賃滞納のリスクを気にせず安定収入を得られる】
サブリース契約最大のメリットは、収入の安定性です。通常の賃貸経営では、空室期間は家賃収入がゼロになり、入居者が家賃を滞納すれば督促の手間と収入減のダブルパンチを受けます。
しかし、サブリース契約では、サブリース会社が物件を丸ごと借り上げてくれるため、実際の入居状況に関わらず、毎月契約した保証賃料がオーナーに支払われます。これにより、ローンの返済計画や将来の資金計画が非常に立てやすくなります。
メリット2【煩わしい賃貸管理業務から解放される】
アパートやマンションの経営には、想像以上に多くの管理業務が発生します。
- 入居者募集の広告活動
- 内見の対応、契約手続き
- 家賃の集金、滞納時の督促
- 入居者からのクレーム対応(騒音、水漏れなど)
- 退去時の立ち会い、原状回復工事の手配
- 共用部分の清掃やメンテナンス
サブリース契約を結べば、これらの煩雑な業務をすべてサブリース会社に一任できます。特に、本業が忙しいサラリーマンオーナーや、物件から遠方に住んでいるオーナーにとって、この手間からの解放は非常に大きな魅力と言えるでしょう。
メリット3【相続時の手続きや確定申告がシンプルになる】
複数の部屋を所有している場合、相続が発生すると、各部屋の賃貸借契約をすべて把握し、資産評価を行う必要があります。サブリースであれば、契約相手がサブリース会社一社に集約されるため、相続財産の評価がしやすく、手続きがスムーズに進みます。
また、毎年の確定申告においても、収入の計算がシンプルになるというメリットがあります。入居者ごとの入退去や家賃の変動を気にする必要がなく、サブリース会社からの年間収支報告書を基に申告できるため、会計処理の手間を大幅に削減できます。


【最重要】サブリースで注意すべき5つのデメリットとリスクとは?
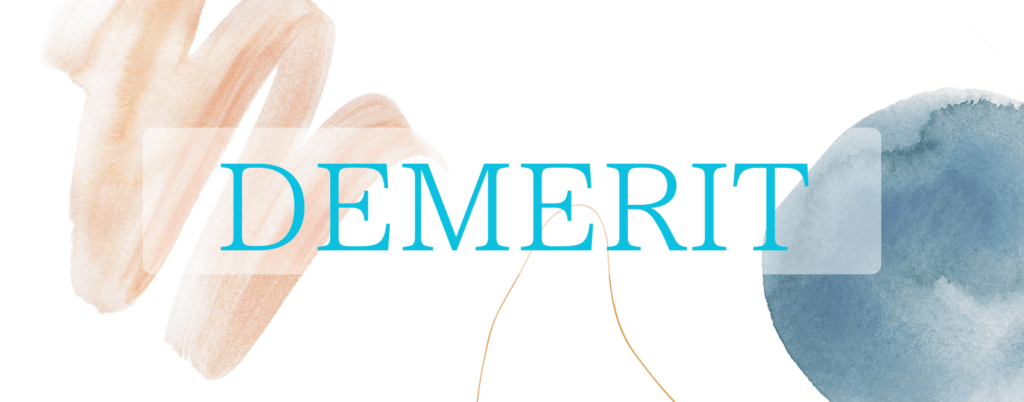
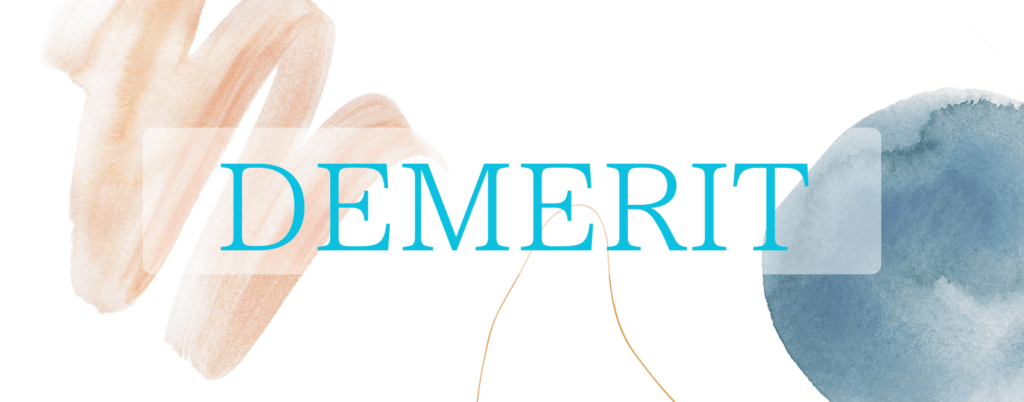
ここまでメリットを解説してきましたが、サブリース契約は良いことばかりではありません。むしろ、これからお話しするデメリットとリスクを正しく理解することが、後悔しないための最も重要なポイントです。
デメリット1【「家賃保証」は永年ではない!賃料は減額される】
「30年一括借上」「安心の家賃保証」といった魅力的な言葉をよく見かけますが、これは「契約当初の家賃が30年間変わらない」という意味ではありません。
サブリース契約書には、ほぼ間違いなく「2年ごと」など定期的に賃料を見直す条項が含まれています。そして、周辺の家賃相場の下落、建物の老朽化、空室率の上昇などを理由に、サブリース会社はオーナーに対して賃料の減額を請求する権利を持っています。
これは、「借地借家法第32条」で定められた権利(借賃増減請求権)です。この規定は、当事者の特約によっても排除できない強行規定であるため、たとえ契約書に「賃料は減額しない」という特約があっても、その特約は無効となり、法的にサブリース会社からの減額請求は認められます。魅力的な保証賃料も、数年後には大幅に下がってしまうリスクがあることは、必ず覚えておかなければなりません。
デメリット2【収益性が一般的な管理委託より低くなる】
サブリース会社は、空室リスクを負う代わりに、オーナーに支払う保証賃料と入居者から得る本来の家賃との差額を利益とします。この差額(手数料)は、一般的に本来の家賃の10%~20%に設定されており、管理委託の手数料(3%~5%)よりも高額です。
つまり、常に満室に近い状態で経営できる人気の物件であれば、サブリースを利用する方が手取り収入は少なくなる可能性があります。安定と引き換えに、得られる収益の上限が低くなることは覚悟しておく必要があります。
デメリット3【オーナーからの途中解約は非常に難しい】
サブリース契約は法律上「賃貸借契約」であり、サブリース会社はオーナーにとって「借主(店子)」の立場になります。借地借家法では、借主の権利が強く保護されており、貸主(オーナー)からの一方的な契約解除や更新の拒絶は、「正当事由」がなければ認められません。
この「正当事由」が認められるハードルは非常に高く、「もっと収益性の高い他の会社に変えたい」「自分で管理したくなった」といった理由では、まず認められません。一度契約を結ぶと、たとえ不満があっても、長期間にわたって関係を続けざるを得ない可能性があるのです。
デメリット4【修繕費用の負担をめぐるトラブルと対策】
入居者が入れ替わる際の原状回復費用や、小規模な修繕はサブリース会社が負担してくれることが多いですが、建物の外壁塗装、屋上防水、給排水管の更新といった大規模な修繕費用は、原則としてオーナーの負担です。
契約内容によっては、エアコンや給湯器といった設備の交換費用もオーナー負担とされる場合があります。サブリースに任せているからといって、将来の修繕費用のための積み立てを怠ると、突然の高額な出費に対応できなくなる恐れがあります。契約時に、どちらがどの範囲の修繕を負担するのか、特にエアコンや給湯器といった「付帯設備」の修繕・交換に関する特約を明確に確認することが不可欠です。
デメリット5【サブリース会社の倒産リスクを忘れてはいけない】
万が一、契約しているサブリース会社が倒産してしまった場合、家賃保証はもちろんなくなります。それだけでなく、事態はさらに複雑化します。
- 入居者との関係:入居者はサブリース会社と契約しているため、オーナーは直接の契約関係にありません。改めて全入居者と個別に賃貸借契約を結び直す事態となる可能性があります。
- 敷金の返還:サブリース会社が預かっていた敷金が返ってこない場合、退去時にオーナーが返還義務を負う可能性があります。
大切な資産を預けるわけですから、会社の経営状態や財務の健全性も、契約前にしっかりと見極める必要があります。
サブリース契約で後悔しないための全知識と注意点とは?
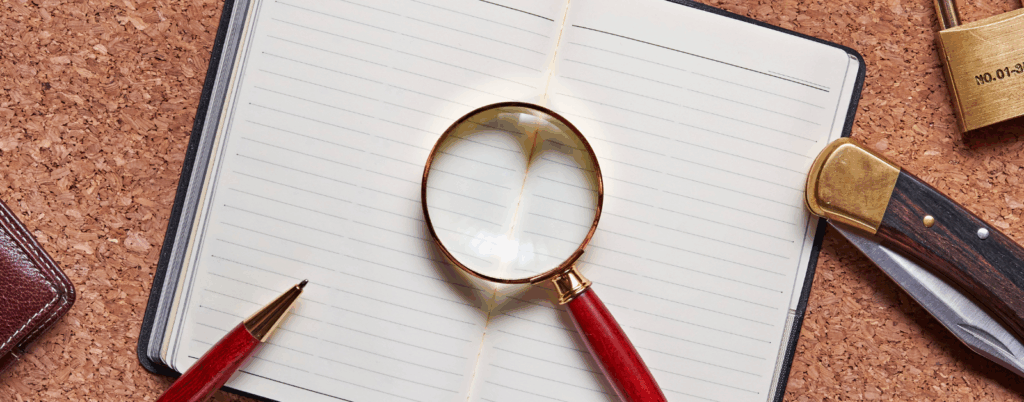
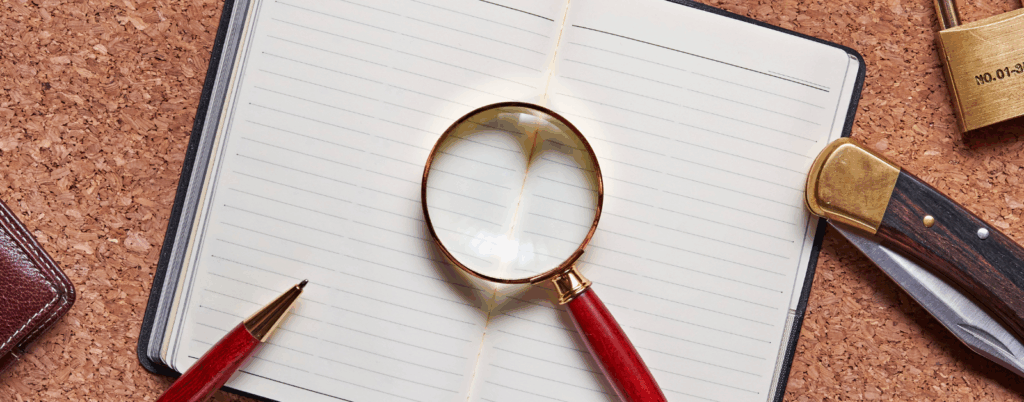
サブリースのリスクを理解した上で、もし契約を検討するならば、どのような点に注意すればよいのでしょうか。後悔しないための具体的な行動指針を解説します。
契約前に必ず確認!重要項目チェックリスト
サブリース契約を結ぶ際は、必ず契約書を隅々まで読み込み、以下の項目を重点的に確認してください。不明な点は、担当者に納得できるまで説明を求めましょう。
- □ 保証賃料の金額と改定の条件
- 何年ごとに見直されるのか?
- どのような条件で減額される可能性があるのか?
- □ 免責期間の有無と期間
- 契約開始後や入居者退去後、家賃が支払われない期間はないか?
- □ 修繕費用の負担区分
- 原状回復、設備交換、大規模修繕の費用は誰が負担するのか?
- □ 契約期間と更新の条件
- 契約期間は何年か?自動更新か?
- □ オーナーからの解約条件
- 中途解約は可能か?その場合の違約金は?
- □ 礼金・更新料の帰属
- 入居者が支払う礼金や更新料は誰の収入になるのか?
信頼できるサブリース会社の選び方3つのポイント
良いパートナーとなるサブリース会社を選ぶことは、成功の絶対条件です。以下の3つのポイントを参考に、慎重に会社を選びましょう。
- 国土交通省の登録業者であるか
2020年に施行された「賃貸住宅管理業法」により、一定規模以上のサブリース業者は国土交通省への登録が義務付けられました。登録業者は、誇大広告の禁止や不当な勧誘の防止、契約前の重要事項説明などが義務付けられています。まずは、この登録業者であるかを国土交通省の「賃貸住宅管理業登録業者検索システム」などを利用して必ず確認しましょう。 - 長年の実績と管理戸数
長年にわたり安定した経営を続けている会社は、それだけ多くのオーナーから信頼されている証です。管理戸数の多さも、賃貸経営のノウハウが蓄積されている指標となります。 - 財務状況と経営の健全性
会社の財務状況を確認することは、倒産リスクを見極める上で重要です。可能であれば、企業のウェブサイトで決算公告などを確認しましょう。また、複数の会社から相見積もりを取り、提案内容や担当者の対応を比較検討することも有効です。


消費者庁も警告!よくあるトラブル事例とその回避策
サブリース契約をめぐるトラブルは後を絶たず、消費者庁も注意喚起を行っています。よくあるトラブル事例を知り、同じ轍を踏まないようにしましょう。
事例1 – 「30年間、家賃は変わりません」というセールストーク
回避策
前述の通り、家賃は社会経済情勢の変化などにより変動するリスクがあることを理解し、セールストークを鵜呑みにしない。家賃が変動する可能性について、契約前の重要事項説明で必ず説明を受ける必要があります。
事例2 – 高額な修繕費用を一方的に請求された
回避策
契約時に修繕費用の負担区分を明確にし、契約書に明記されていることを確認する。将来の大規模修繕に備え、自身で修繕積立金を用意しておくことも重要です。
事例3 – 解約を申し出たら、高額な違約金を請求された
回避策
契約書の中途解約条項を事前に必ず確認する。オーナーからの解約が非常に難しいことを前提に、長期的な視点で契約を検討することが大切です。
結論【結局サブリースの利用が向いている人・いない人とは?】
これまでの情報を踏まえ、サブリースという選択肢がどのような人に適しているのかをまとめました。ご自身の状況や考え方と照らし合わせてみてください。
サブリースがおすすめな人の特徴
- とにかく手間をかけずに不動産経営をしたい人
- 収入のブレをなくし、安定性を最優先したい人
- 所有物件が遠方にあり、自主管理が難しい人
- 不動産経営の知識や経験が全くない初心者
これらの人々にとって、サブリースはリスクを管理会社に移転し、手間なく安定したインカムゲインを得られる有効な手段となり得ます。
管理委託など他の方法を検討すべき人の特徴
- 少しでも収益性を高め、手取り収入を最大化したい人
- 空室リスクなどをある程度は許容できる人
- 物件経営に積極的に関わり、ノウハウを蓄積したい人
- 入居者の選定やリフォームなどを自分で行いたい人
これらの人々にとっては、サブリースの手数料や制約が足かせになる可能性があります。リスクは自身で負いながらも、より高いリターンを目指せる管理委託などの方法が適しているでしょう。
まとめ
今回は、サブリースとは何か、その仕組みからメリット、そして最も重要なデメリットや注意点までを網羅的に解説しました。
サブリースは、「不労所得」「手間いらず」といった魅力的な側面がある一方で、家賃減額や解約の困難さといった重大なリスクを内包した契約形態です。
決して「怪しい契約」というわけではありませんが、その仕組みとリスクを正しく理解しないまま安易に契約してしまうと、将来的に大きな後悔に繋がりかねません。不動産会社からの提案を鵜呑みにせず、本記事で解説したチェックポイントを参考に、ご自身の資産と将来を守るための冷静な判断を心がけてください。




