
アパート経営の空室リスクや管理の手間から解放されたい…そんなお悩みから「サブリース」に興味を持っていませんか?
本記事では、サブリースの基本的な仕組みから、「家賃保証」といったメリット、そして家賃減額や解約トラブルなど、契約前に必ず知るべきデメリットまでを詳しく解説します。
安易な契約は大きな損失に繋がるため、サブリース新法の内容や安全な会社の選び方まで含めた正しい知識が不可欠になります。この記事を最後まで読めば、サブリースのリスクを正確に理解し、ご自身の状況に本当に合った選択なのかを自信を持って判断できるようになります。
サブリースの仕組みとは?一括借上げと管理委託の違いを解説
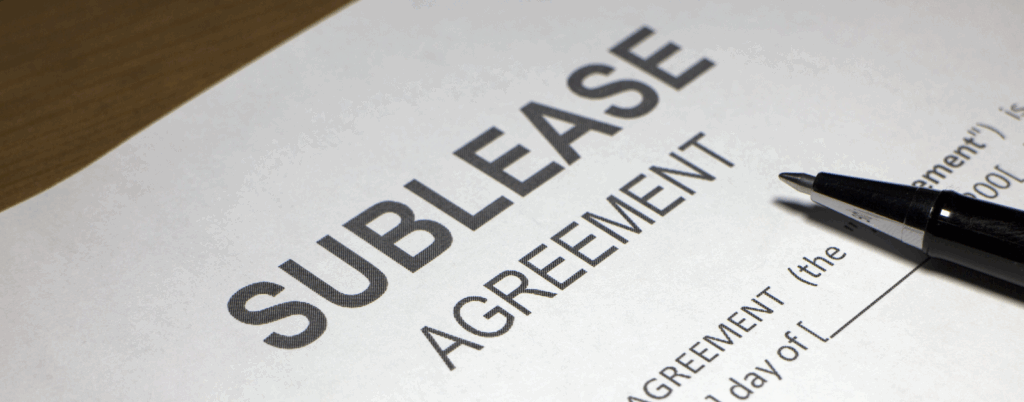
「サブリース」という言葉はよく聞くけれど、具体的にどのような仕組みなのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか。まずは、サブリースの基本的な仕組みと、混同されやすい「管理委託」との違いを明確に理解しましょう。
サブリース契約の基本的な仕組みをわかりやすく
サブリースとは、不動産会社(サブリース会社)がオーナーから物件を丸ごと借り上げ、それを入居者に転貸(又貸し)する仕組みのことです。「一括借り上げ」とも呼ばれます。
この取引には、「オーナー」「サブリース会社」「入居者」の三者が関わります。
オーナーは、サブリース会社と「マスターリース契約」という賃貸契約を結びます。これにより、サブリース会社は物件の借主となります。
オーナーは、サブリース会社と「マスターリース契約」という賃貸契約を結びます。これにより、サブリース会社は物件の借主となります。
オーナーから見た貸主はサブリース会社です。そのため、実際に入居者がいるかどうかに関わらず、オーナーはサブリース会社から毎月一定の「保証賃料」を受け取ることができます。一方、入居者が支払う家賃はサブリース会社が受け取ります。この保証賃料と実際の家賃との差額が、サブリース会社の利益となります。
「サブリース」と「管理委託」の決定的な違いを比較表で整理
サブリースとよく似た仕組みに「管理委託」があります。どちらも管理業務を不動産会社に任せる点では同じですが、契約形態や家賃保証の有無が根本的に異なります。
| 比較項目 | サブリース契約 | 管理委託契約 |
| 契約形態 | 賃貸借契約 | 委任契約 |
| オーナーの立場 | 貸主 | 貸主 |
| 不動産会社の立場 | 借主 | 管理の代理人 |
| 家賃保証 | あり | なし |
| 空室・滞納リスク | サブリース会社が負担 | オーナーが負担 |
| オーナーの収入 | 一定の保証賃料(相場の80〜90%) | 家賃収入から管理手数料を引いた額 |
| 管理手数料 | なし(保証賃料に含まれる) | 家賃収入の5%前後 |
| 入居者との関係 | 間接的(関わらない) | 間接的(管理会社が窓口) |
最大の違いは「家賃保証の有無」です。サブリースは空室があっても収入が保証される一方、管理委託は空室が出ればその分の家賃収入はゼロになります。この点が、サブリースが選ばれる大きな理由です。
マスターリース契約とは?サブリースとの関係性
少し専門的になりますが、「マスターリース」と「サブリース」という言葉の関係を整理しておきましょう。
マスターリース契約
物件のオーナーとサブリース会社との間で結ばれる「親」となる賃貸借契約のこと。
サブリース契約(転貸借契約)
サブリース会社と入居者との間で結ばれる「子」となる賃貸借契約のこと。
一般的に、オーナーが関わる不動産会社との一括借り上げ契約全体を、総称して「サブリース契約」と呼ぶことが多くなっています。この記事でも、オーナーとサブリース会社との契約を指して「サブリース」と表現します。

【家賃保証以外にも】サブリース契約のメリットを徹底解説
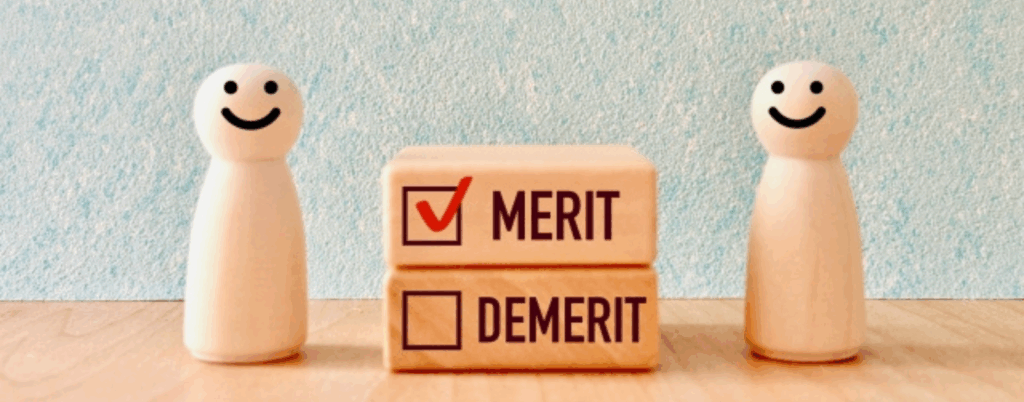
サブリース契約が多くのオーナーに選ばれるのには、明確なメリットがあるからです。ここでは、代表的な3つのメリットを解説します。
空室や家賃滞納のリスクを気にせず安定収入を得られる
サブリースの主なメリットは、空室や家賃滞納のリスクをサブリース会社が負担してくれることです。
通常の賃貸経営では、空室期間が長引いたり、入居者が家賃を滞納したりすると、その月の収入は不安定になりがちです。しかし、サブリース契約では、実際の入居状況に関わらず、サブリース会社から毎月決まった額の保証賃料が支払われます。これにより、オーナーは将来の収支計画を立てやすくなり、精神的な安心感も得られます。
面倒な賃貸管理業務から解放される
アパートやマンションの経営には、想像以上に多くの管理業務が伴います。
- 入居者募集の広告活動
- 入居希望者の内見対応・審査
- 賃貸借契約の手続き
- 毎月の家賃回収・送金
- 入居者からのクレームや問い合わせ対応
- 共用部分の清掃やメンテナンス
- 退去時の立ち会いと原状回復工事の手配
- 次の入居者のためのリフォーム
サブリース契約を結ぶと、これらの煩雑な業務をすべてサブリース会社に一任することが可能です。特に、本業で忙しい方や、物件から遠い場所に住んでいる方にとっては、大きなメリットと言えるでしょう。
確定申告の手続きが簡素化される
不動産所得がある場合、年に一度の確定申告が必要です。
通常の管理委託では、部屋ごとに入居や退去、家賃の変動があるため、収入の計算が複雑になりがちです。一方、サブリースの場合、収入の相手方はサブリース会社のみ。毎月一定額の収入が一本化されるため、帳簿付けが非常にシンプルになり、確定申告の手間を軽減できるという副次的なメリットもあります。
【契約前に必ず確認】サブリースに潜む7つのデメリット・リスク

安定した収入と手間の削減という魅力的なメリットがある一方、サブリースには契約前に必ず理解しておくべき重大なデメリットやリスクが存在します。これらを知らずに契約すると、「こんなはずではなかった」と後悔する原因になります。
①家賃保証ではない?保証賃料の減額リスク
最も注意すべきリスクが、「保証されているはずの家賃が減額される」可能性です。「家賃保証」という言葉から、契約期間中ずっと同じ額が保証されると誤解しがちですが、そうではありません。
多くのサブリース契約書には、「経済状況の変動」や「近隣相場の変動」などを理由に、定期的に賃料を見直す条項が含まれています。そして、法律(借地借家法第32条)によって、契約内容にかかわらず、借主(サブリース会社)は貸主(オーナー)に対して賃料の減額を請求する権利が認められています。
つまり、サブリース会社は法的に賃料減額を請求する権利を持っており、オーナーはこれを一方的に拒否することは非常に困難です。「家賃保証」は永続的なものではない、ということを必ず覚えておいてください。
②オーナーからの解約は困難【違約金・正当事由】
一度サブリース契約を結ぶと、オーナーの都合で解約するのは非常に難しいというリスクがあります。
サブリース契約は、サブリース会社が借主となる「賃貸借契約」です。借地借家法では、借主の権利が強く保護されており、貸主(オーナー)から契約を解除するには「正当な事由」が必要となります。この「正当な事由」は、「オーナーがその物件に住む必要ができた」など、よほど切迫した理由でなければ裁判所では認められないのが実情です。
もし解約が認められたとしても、サブリース会社が被る損害(転貸している入居者の立ち退き料など)を補填するために、家賃の数年分に相当する高額な違約金を請求されるケースも少なくありません。
③収益性の低下【手数料と保証賃料の相場】
サブリースは、空室リスクをサブリース会社が負う代わりに、オーナーの収益性が低下するビジネスモデルです。
一般的に、サブリース会社がオーナーに支払う保証賃料は、入居者が支払う家賃相場の80%〜90%程度に設定されます。差額の10%〜20%が、サブリース会社の手数料(マージン)となります。
仮に、常に満室経営ができる優良物件であれば、自分で管理したり、管理委託にしたりする方が、手元に残る収益は大きくなります。安定を取るか、収益性を取るかのトレードオフの関係にあるのです。
④新築時や退去後に収入が途絶える「免責期間」
契約書をよく見ると、「免責期間」という条項が定められていることがあります。これは、一定期間、サブリース会社が家賃の支払いを免れる、つまりオーナーに家賃が振り込まれない期間のことです。
例えば、「新築後、最初の入居者が決まるまで最長90日間」や、「入居者の退去後、次の入居者が決まるまで30日間」といった形で設定されます。この期間中は家賃保証が適用されないため、ローン返済などを予定している場合は注意が必要です。
⑤高額な修繕費を請求される可能性
入居者が退去した際の原状回復費用や、給湯器・エアコンなどの設備交換費用はサブリース会社が負担してくれることが多いですが、建物の維持に不可欠な大規模修繕はオーナー負担となるのが一般的です。
- 外壁塗装
- 屋上の防水工事
- 共用部分の鉄部の塗装
これらの大規模修繕には、百万円単位の費用がかかることもあります。サブリース契約だからといって、建物の維持管理コストが完全になくなるわけではないことを理解し、計画的に修繕費を積み立てておく必要があります。
⑥サブリース会社の倒産リスク
万が一、契約しているサブリース会社が倒産してしまった場合、家賃保証は当然ながら打ち切られます。それだけでなく、以下のような複雑な問題が発生します。
- 入居者との転貸借契約をオーナーが引き継ぐ必要がある
- サブリース会社が預かっていた敷金の返還義務をオーナーが負う可能性がある
- 滞納していた入居者がいた場合、その回収もオーナーが行う
会社の経営状況が不安定になれば、保証賃料の支払いが遅れたり、一方的な減額交渉を迫られたりする可能性も高まります。契約する会社の経営体力を見極めることは非常に重要です。
⑦サブリース契約付き物件は売却しにくい?
これは見落とされがちなリスクですが、サブリース契約中の物件は、いざ売却しようと思っても買い手が見つかりにくい傾向があります。
理由は主に2つあります。
売却価格を評価する際の指標となる「利回り」が、保証賃料を基に計算されるため、相場家賃で計算した場合より低く見えてしまいます。
物件を購入した新しいオーナーは、既存のサブリース契約を引き継ぐ義務があります。そのため、自分で運営方針を決めたい投資家からは敬遠されがちです。
将来的に物件の売却も視野に入れている場合は、サブリース契約が足かせになる可能性があることを覚えておくべきです。
サブリースのトラブルを防ぐには?新法と信頼できる会社の選び方

ここまでサブリースのリスクを解説してきましたが、これらを理解し、対策を講じることで、トラブルを未然に防ぐことは可能です。ここでは、オーナーを守る法律と、安全な会社の選び方について解説します。
オーナーを守る「サブリース新法」3つのポイント
相次ぐサブリーストラブルを受け、オーナーを保護するために、2020年12月に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(通称:サブリース新法)」が施行されました。この法律により、サブリース業者には以下の3点が義務付けられました。
「30年間家賃保証!」など、将来の家賃が確定しているかのように誤解させる広告が禁止されました。
契約の判断に影響する重要な事実(家賃減額リスクなど)を、わざと伝えないような勧誘が禁止されました。
契約を結ぶ前に、家賃減額リスクや解約条件など、オーナーにとって不利益となりうる情報を書面で交付し、必ず説明することが義務付けられました。
この法律のおかげで、以前よりも安心して契約の検討ができる環境が整ってきています。
【チェックリスト付】安全なサブリース会社の選び方
法律が整備されても、最終的にパートナーとなる会社を選ぶのはオーナー自身です。以下のチェックリストを参考に、信頼できる会社を慎重に見極めましょう。
- □ 実績と経営状況は安定しているか?
- 長年の実績があるか、管理戸数は多いか。上場企業であれば財務状況も公開されているため、一つの判断材料になります。
- □ 査定賃料の根拠は明確か?
- なぜその保証賃料なのか、近隣の家賃相場や物件の強み・弱みを基に、納得のいく説明をしてくれるか確認しましょう。
- □ 複数の会社から相見積もりを取ったか?
- 必ず2〜3社を比較検討し、最も条件が良く、信頼できる会社を選びましょう。1社だけの話で決めるのは危険です。
- □ 国土交通省の「賃貸住宅管理業の登録」を受けているか?
- 一定規模以上の管理会社には登録が義務付けられています。登録業者は法令遵守の意識が高いと考えられます。
- □ 担当者の対応は誠実か?
- メリットばかりを強調し、デメリットの説明を避けるような担当者には注意が必要です。あなたの質問に真摯に答えてくれるかを見極めましょう。
契約書で必ず確認すべき重要項目
口頭での説明だけでなく、必ず契約書の内容を隅々まで確認することがトラブル防止の鍵です。特に以下の項目は、時間をかけて読み込みましょう。
- 保証賃料の改定に関する条項
何年ごとに、どのような条件で賃料が見直されるのか。 - 免責期間の有無と期間
新築時や入居者交代時の免責期間が何日間に設定されているか。 - 修繕費の負担区分
原状回復、設備交換、大規模修繕の費用を誰がどこまで負担するのか。 - 解約に関する条項
オーナーからの解約条件、必要な予告期間、違約金の額や計算方法。 - 契約期間と更新の条件
契約期間は何年か。自動更新なのか、合意更新なのか。
不明な点があれば、絶対に放置せず、担当者に説明を求めましょう。必要であれば、契約前に弁護士などの専門家に契約書をチェックしてもらうことも有効な手段です。
【最終判断】あなたの状況にサブリースは向いている?
サブリースは、誰にとっても最適な選択肢というわけではありません。メリットとデメリットを理解した上で、ご自身の状況や目的に合っているかを判断することが大切です。
サブリースをおすすめできる人の特徴
以下のような方は、サブリースのメリットを最大限に活用できる可能性が高いでしょう。
- とにかく管理の手間をかけたくない方: 本業が多忙、不動産経営の知識がない、管理業務に時間を割きたくないという方。
- 物件が遠隔地にあり、自主管理が難しい方: 頻繁に物件を訪れることができない場合、地元のサブリース会社に任せるのは有効です。
- 収益性よりも収入の安定性を最優先したい方: 多少収益が下がっても、毎月決まった収入があることによる精神的な安定を重視する方。
- 相続で物件を取得したが、どうしていいかわからない方: まずはサブリースで安定的に運用し、その間に今後の活用法をじっくり考えるという使い方もできます。
サブリースを慎重に検討すべき人の特徴
一方、以下のような方は、サブリース以外の方法(管理委託や自主管理)を検討した方が良いかもしれません。
- 不動産投資による収益を1円でも多く最大化したい方: サブリースの手数料が、機会損失と感じる可能性があります。
- 物件の運営(入居者募集やリフォームなど)に自分で関わりたい方: 経営の自由度が制限されるサブリースは不向きです。
- 築年数が古く、近い将来に大規模修繕が想定される物件をお持ちの方: 修繕費の負担が重くのしかかり、収支が悪化するリスクがあります。
- 不動産経営の知識や経験を積んで、事業として成長させたい方: 管理業務をすべて手放してしまうと、経営ノウハウが身につきません。
まとめ『サブリースはリスクを理解すれば有効な選択肢』
今回は、サブリースの仕組みからメリット、そして契約前に知るべき7つのリスクと対策まで、詳しく解説しました。
サブリースは、保証賃料による安定した収入と、煩雑な管理業務からの解放というメリットを持つ、不動産経営の有効な手法の一つです。しかしその裏には、家賃減額のリスクや解約の困難さといった、重大なデメリットが隠されています。
重要なのは、サブリースを「善」か「悪」かで判断するのではなく、メリットとデメリットを正しく天秤にかけ、ご自身の状況や目的に合っているかを冷静に見極めることです。
この記事で解説したチェックリストや契約書の確認ポイントを活用し、信頼できるパートナーを選べば、サブリースはあなたの不動産経営を成功に導く心強い味方となってくれるでしょう。もし少しでも不安が残る場合は、一人で悩まず、弁護士や不動産コンサルタントといった第三者の専門家に相談することも検討してください。



