
「サブリース」という言葉、不動産投資に興味をお持ちの初心者の方なら、一度は耳にしたことがあるかもしれませんね。「どんな仕組み?」「メリットばかりじゃないの?」そんな疑問を抱えていませんか。この記事では、サブリースの基本的な仕組みから、知っておくべきメリット・デメリットまで、専門用語を極力使わずに分かりやすく解説します。
この記事を読めば、「家賃保証は本当に安心?」「管理の手間が省けるってどういうこと?」といった具体的な疑問が解消され、サブリースがあなたにとって本当に有利な選択肢なのかを見極める基礎知識が身につきます。
読み終わる頃には、サブリースへの漠然とした不安がなくなり、メリットとデメリットを客観的に理解した上で、冷静に検討できる状態になっているはずです。不動産投資の重要な選択肢の一つとして、サブリースを正しく理解し、賢い一歩を踏み出しましょう。

サブリース とは?初心者が知っておきたい基本の仕組みを簡単解説
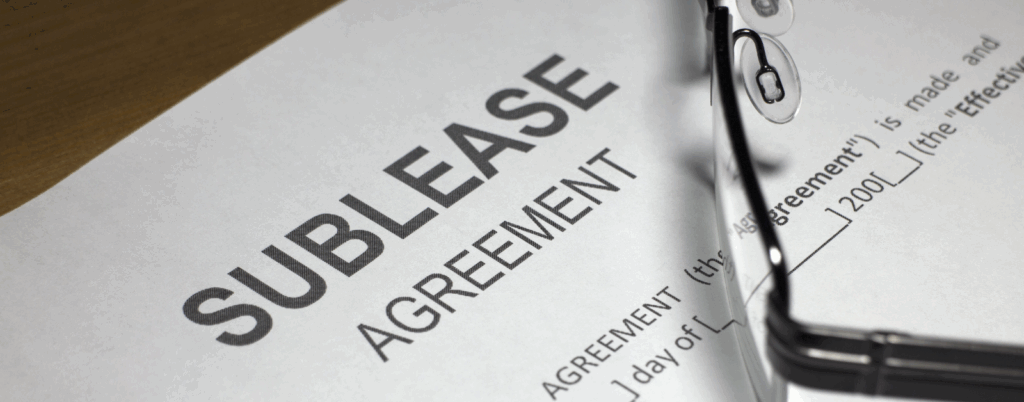
まずは、「サブリース」という言葉の基本的な意味と、その仕組みについて見ていきましょう。難しく考えず、ポイントを押さえて理解することが大切です。
まずはここから!「サブリース」の基本的な意味とは?
サブリースを一言でいうと、「又貸し(またがし)」のことです。 物件のオーナー(大家さん)から不動産会社が物件を一括で借り上げ、その借り上げた物件を不動産会社が別の入居者に貸し出す仕組みを指します。英語では「sublease」と書き、「sub(副の、下の)」と「lease(賃貸借)」を組み合わせた言葉です。
では、なぜこのような「又貸し」の仕組みが生まれたのでしょうか。主な背景としては、物件オーナー側の「賃貸経営の手間を省きたい」「空室リスクを避けたい」というニーズと、不動産会社側の「管理物件を増やして事業を拡大したい」というニーズが合致したことが挙げられます。特に、専門的な知識や多くの時間を必要とする賃貸経営を、プロに任せたいと考えるオーナーにとって、魅力的な選択肢の一つとして広まってきました。
登場人物は3者!オーナー・サブリース会社・入居者の関係性
サブリースの仕組みを理解する上で、登場人物とその役割を把握することが重要です。主な登場人物は以下の3者です。
アパートやマンションなどの賃貸物件の所有者です。サブリース会社に物件を一括で貸し出し、サブリース会社から毎月一定の賃料(保証賃料などと呼ばれることもあります)を受け取ります。賃貸経営に関する専門的な業務の多くをサブリース会社に委ねることができます。
オーナーから物件を一括で借り上げ、その物件を入居者に貸し出す(転貸する)不動産会社です。オーナーに対しては借主として賃料を支払い、入居者に対しては貸主として賃料を受け取ります。入居者の募集や契約手続き、家賃回収、クレーム対応などの管理業務全般を担います。
サブリース会社が貸し出す物件に実際に住む人です。サブリース会社と賃貸借契約を結び、サブリース会社に対して家賃を支払います。物件のオーナーと直接的な契約関係はありません。
このように、サブリースではオーナーと入居者の間にサブリース会社が入ることで、オーナーは直接入居者と関わることなく賃貸経営を行うことができるのが特徴です。
「マスターリース契約」と「サブリース契約」って何が違うの?
サブリースの話になると、「マスターリース契約」という言葉も出てくることがあります。この二つの契約の違いを簡単に整理しておきましょう。
マスターリース契約とは
これは、物件のオーナーとサブリース会社との間で結ばれる「一括借り上げ契約」のことです。この契約に基づき、サブリース会社はオーナーから物件全体を借り上げます。オーナーにとっては、この契約がサブリース会社への物件賃貸の根拠となります。
サブリース契約とは
これは、サブリース会社と実際の入居者(転借人)との間で結ばれる「転貸借契約」のことです。サブリース会社がマスターリース契約に基づいてオーナーから借り上げた物件を、さらに第三者である入居者に貸し出す際の契約です。
つまり、オーナーが関わるのは主に「マスターリース契約」であり、その結果としてサブリース会社が「サブリース契約」を入居者と結ぶ、という流れになります。
サブリースとここが違う!「管理委託」との基本的な違い
サブリースとよく比較されるものに「管理委託」という仕組みがあります。どちらも賃貸経営の手間を不動産会社に任せるという点では似ていますが、契約形態やリスクの所在が大きく異なります。初心者の方が混同しやすいポイントなので、違いをしっかり押さえておきましょう。
| 比較ポイント | サブリース | 管理委託 |
|---|---|---|
| 契約形態 | 賃貸借契約 (オーナーがサブリース会社に貸す) | 委任契約 (オーナーが管理会社に業務を委託する) |
| 家賃収入の受け取り方 | サブリース会社から一定の賃料 (保証賃料など)を受け取る | 入居者から支払われた家賃から管理手数料を差し引いた額を受け取る |
| 空室時のリスク負担 | 原則としてサブリース会社が負担(家賃保証がある場合)。ただし、契約内容や市場状況により変動する可能性があり、免責期間が設けられる場合もあります。 | オーナーが負担 (空室期間は家賃収入なし) |
| 貸主の立場 | サブリース会社が貸主として入居者と契約 | オーナーが貸主として入居者と契約(管理会社は代行) |
| 不動産会社への報酬 | サブリース会社は入居者からの家賃とオーナーへの支払賃料の差額が利益の一部となる | オーナーが管理会社に管理委託料(一般的に家賃の数%)を支払う |
サブリースは、物件を丸ごと不動産会社に「貸す」イメージです。そのため、空室があっても(契約内容や市場状況によりますが)オーナーは一定の収入を得られる可能性があります。 一方、管理委託は、あくまで管理業務を「お願いする」イメージです。物件の貸主はオーナー自身のままで、空室リスクもオーナーが負います。
どちらが良いかは、オーナーの考え方や物件の状況によって異なります。ご自身の目的やリスク許容度に合わせて選ぶことが大切です。
【徹底比較】サブリース とはどんなメリット・デメリットがある?
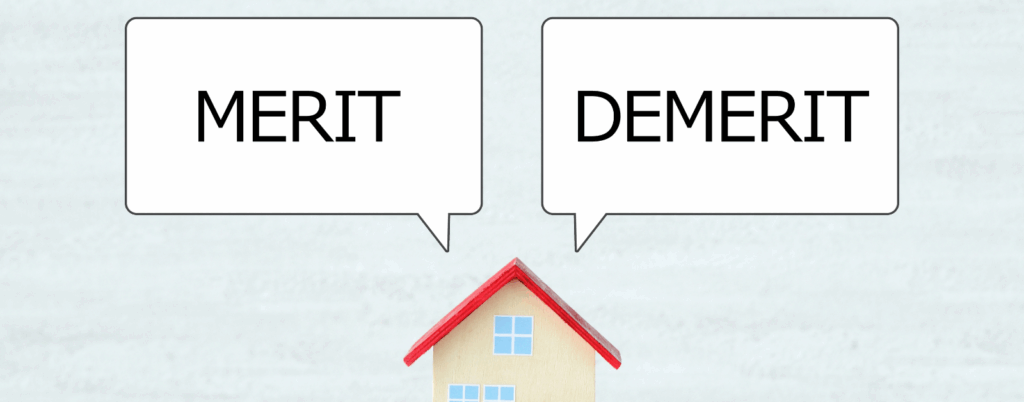
サブリースは、不動産投資における一つの選択肢ですが、その仕組みにはメリットとデメリットの両面が存在します。 ここでは、オーナーの視点から見たサブリースの主なメリットと、契約前に必ず理解しておくべきデメリットや注意点を詳しく見ていきましょう。
オーナーが知っておきたい!サブリースの主なメリット5選
まずは、サブリースを利用することでオーナーが得られる主なメリットを5つご紹介します。
メリット1『空室・家賃滞納リスクの心配を軽減できる仕組みとしての「家賃保証」』
サブリースの大きな特徴の一つに「家賃保証」があります。これは、サブリース会社が物件を一括で借り上げ、たとえ空室が発生したり、入居者が家賃を滞納したりしても、オーナーには毎月事前に合意した賃料が支払われるというものです。ただし、この家賃保証は契約内容や市場状況により変動する可能性があり、免責期間が設けられる場合もあります。 これにより、賃貸経営で頭を悩ませる空室リスクや家賃滞納リスクを軽減できる可能性があります。「必ずしも保証されるわけではない」という点は後述しますが、この仕組みは安心材料の一つとなり得るでしょう。
メリット2『手間いらず!煩雑な賃貸管理業務から解放される』
賃貸経営には、入居者募集、内見対応、契約手続き、家賃集金、クレーム対応、退去時の立ち会いや原状回復の手配など、非常に多くの業務が伴います。これら専門知識が必要だったり、手間がかかったりする業務のほとんどをサブリース会社に任せることができます。特に、本業が忙しい方や、物件から遠方に住んでいる方にとっては大きなメリットです。
メリット3『毎月比較的安定した家賃収入が期待できる』
メリット1の家賃保証とも関連しますが、サブリース契約では、空室状況に左右されずに毎月ほぼ固定の収入が見込めるため、収支計画が立てやすくなることがあります。不動産投資ローンを利用して物件を購入した場合でも、比較的安定した収入は返済計画の安心感につながることがあります。
メリット4『初心者も安心!専門知識がなくても不動産経営を始めやすい』
不動産経営には、法律や税金、建築など、さまざまな専門知識が求められます。サブリースを利用すれば、これらの専門的な業務の多くをプロであるサブリース会社に委託できるため、不動産投資の経験が浅い初心者の方でも比較的スムーズに賃貸経営をスタートできます。
メリット5『場合によっては節税効果も?』
不動産所得は、他の所得と合算して税金が計算される総合課税の対象です。サブリースを利用した場合でも、経費計上の仕方などによっては節税につながるケースがあります。ただし、節税効果は個々の状況や税制によって異なり、必ずしもメリットになるとは限りません。安易に期待せず、税理士などの専門家に相談することが重要です。

契約前に必ず確認!サブリースの主なデメリット・注意点6選
魅力的なメリットがある一方で、サブリースには注意すべきデメリットやリスクも存在します。契約後に「こんなはずではなかった」と後悔しないために、以下の点をしっかりと理解しておきましょう。
デメリット1『手取り収入が減る可能性(一般的な賃料相場より低い設定、手数料)』
サブリース会社は、オーナーから借り上げた物件を入居者に貸し出すことで利益を得ています。そのため、オーナーが受け取る賃料(保証賃料)は、サブリース会社が直接入居者から得る家賃収入の全額ではなく、通常、市場家賃から一定の割合(例:10%~20%程度)がサブリース会社の収益や経費として差し引かれた金額が、オーナーへの保証賃料として設定されるケースがあります。ただし、この割合は契約条件によって大きく異なりますので、必ず契約書で確認が必要です。つまり、自分で直接入居者に貸し出す場合(満室時)と比較して、手取り収入が少なくなる可能性があります。
デメリット2『「家賃保証」は絶対じゃない!?賃料減額リスクと免責期間』
「家賃保証」という言葉は非常に魅力的ですが、これが未来永劫、契約時の金額で保証されるわけではない点に最大限の注意が必要です。多くのサブリース契約では、経済状況の変動や周辺物件との競争激化、建物の経年劣化などを理由に、定期的に保証賃料の見直し(減額交渉)が行われる条項が含まれています。保証賃料の減額請求に応じない場合、サブリース会社から契約を解除されたり、話し合いがまとまらなければ訴訟に発展したりする可能性もゼロではありません。 また、契約開始から一定期間や、入居者退去後の一定期間は家賃が保証されない「免責期間」が設けられていることもあります。「保証」という言葉だけに安心せず、契約内容を細かく確認する必要があります。
デメリット3『契約期間の縛り!長期契約と中途解約の難しさ』
サブリース契約は、10年、20年といった長期契約になることが一般的です。そして、オーナー側の都合で契約期間の途中で解約することは非常に難しいか、あるいは高額な違約金が発生するケースが多いです。物件を売却したくなったり、自身で直接運営したくなったりしても、サブリース契約が足かせになる可能性があることを理解しておく必要があります。
デメリット4『サブリース会社の倒産リスク!契約先選びは慎重に』
万が一、契約しているサブリース会社が倒産してしまった場合、家賃保証が受けられなくなるだけでなく、入居者から預かった敷金がサブリース会社にプールされている場合、その敷金が返還されないといった問題や、 入居者との関係が複雑になるなどの問題が発生する可能性があります。サブリース会社を選ぶ際には、経営状況や実績、評判などを十分に調査し、信頼できる会社を選ぶことが極めて重要です。
デメリット5『想定外の費用も?修繕費の負担区分と範囲の確認は必須』
物件の維持管理に必要な修繕費(外壁塗装、給湯器交換、エアコン修理など)の負担区分は、サブリース契約によって異なります。「全てサブリース会社が負担してくれる」と思い込んでいると、後で高額な費用を請求されることもあります。契約時に、どのような修繕がどちらの負担になるのか、負担割合はどうなるのかを明確に確認しておく必要があります。
デメリット6『自由度が低い?入居者を選べない、リフォームが自由にできない可能性』
サブリースの場合、入居者の募集や選定はサブリース会社が行うため、基本的にオーナーは入居者を選ぶことができません。また、物件のリフォームや大規模な改修を行いたいと思っても、サブリース会社の同意が必要になるなど、物件運営の自由度が低くなることがあります。ご自身の物件に対する思い入れが強い方にとっては、この点がデメリットと感じられるかもしれません。
後悔しないために!サブリース とは契約前に確認すべき重要チェックポイント
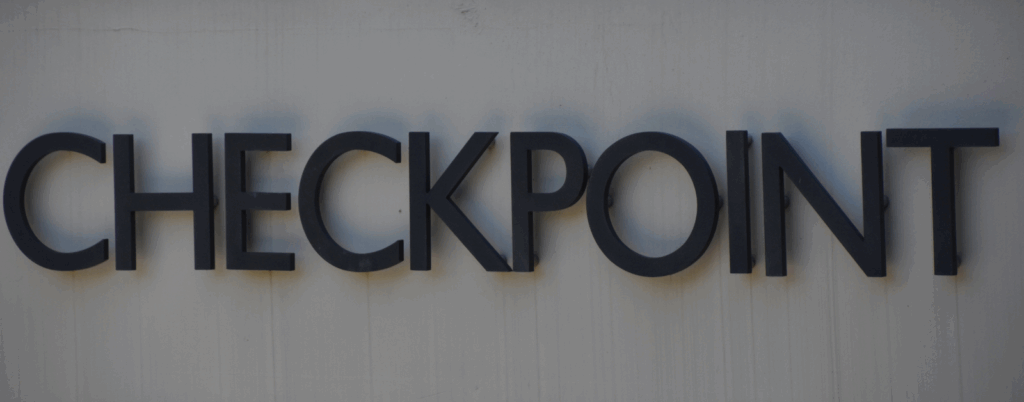
サブリース契約は長期にわたることが多く、一度契約すると簡単には変更できません。だからこそ、契約前の確認が非常に重要になります。近年、サブリース契約を巡るトラブル防止のため、国も法整備を進めています。特に、家賃保証を伴う「特定賃貸借契約」については、2020年12月15日に施行された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(賃貸住宅管理業法)により、サブリース業者に契約前の重要事項説明などが義務付けられました。契約時には、書面で詳細な説明を受け、理解できるまで確認しましょう。
ここでは、特に初心者の方がサブリース契約を結ぶ際に、必ずチェックしてほしい重要ポイントを具体的に解説します。
契約書で絶対確認!「家賃保証」の詳細な条件
「家賃保証」はサブリースの大きな魅力ですが、その内容は契約によって様々です。以下の点を必ず確認しましょう。
保証される家賃の金額と保証率
実際に保証される家賃の金額はいくらか、それは相場家賃の何%程度なのか(保証率)を確認します。「相場家賃の90%を保証」などと記載されている場合、その「相場家賃」がどのように算出されるのかも重要です。
家賃改定(増減)の条件と通知時期、協議の可否
「何年ごとに家賃が見直されるのか」「どのような状況になったら見直されるのか(例:近隣相場の変動、空室率の上昇など)」「見直しの何ヶ月前に通知があるのか」「賃料減額の提案があった場合に、オーナー側から協議を申し入れることは可能なのか」などを細かく確認します。「一方的に減額できる」といった条項になっていないか注意が必要です。
免責期間の有無とその期間
契約開始後の一定期間や、入居者が退去してから次の入居者が決まるまでの一定期間など、家賃が保証されない「免責期間」が設定されていないか確認します。もし設定されている場合、その期間はどのくらいなのかを把握しておきましょう。
- 「家賃が下がることは絶対にない」と営業担当者に言われたのですが…?
-
口頭での説明だけでなく、必ず契約書の内容を確認してください。契約書に賃料改定の条項があれば、それが優先されます。重要な約束事は、必ず書面に残してもらうようにしましょう
いつまで続く?「契約期間」と「更新条件」の確認
サブリース契約は長期に及ぶことが多いので、契約期間と更新に関する条件は非常に重要です。
契約期間の長さ(一般的傾向)
契約期間が何年になっているかを確認します。一般的には5年、10年、20年、場合によっては30年を超える契約もあります。
契約更新の条件、更新料の有無
契約期間が満了した際に、自動的に更新されるのか、それとも双方の合意が必要なのか。更新される場合の条件(例:賃料の見直しがあるかなど)や、更新料が発生するのかどうかを確認します。
中途解約の可否と、可能な場合の条件・違約金
オーナー側の都合で契約期間の途中で解約ができるのか、もしできるとしたらどのような条件(例:解約通知の時期、正当事由の必要性など)があるのか、そして違約金が発生するのかどうか、発生する場合はその金額の算定方法などを必ず確認します。一般的にオーナーからの中途解約は非常に厳しい条件が設定されていることが多いです。
どちらが負担?「修繕費」の負担範囲と割合
物件の維持管理には修繕が不可欠です。その費用負担については、後々トラブルになりやすいポイントですので、契約時に明確にしておく必要があります。
大規模修繕、小規模修繕、原状回復費用の負担区分
外壁塗装や屋上防水といった「大規模修繕」、給湯器やエアコンの交換、水漏れ修理といった「小規模修繕」、入居者退去時のクロスの張り替えやハウスクリーニングといった「原状回復費用」について、それぞれオーナーとサブリース会社のどちらが負担するのか、あるいはどのような割合で負担するのかを具体的に確認します。また、共用部分の電球交換や日常的な清掃費用など、細かな維持管理費用についてもどちらの負担となるのか、事前に確認しておきましょう。
経年劣化と入居者の過失による破損の扱い
建物の自然な劣化(経年劣化)による修繕と、入居者の故意・過失による破損の修繕では、費用負担の考え方が異なる場合があります。この点も明確にしておきましょう。
万が一の事態に備える!サブリース会社の「倒産リスク」と見極め方
サブリース会社が倒産してしまうと、家賃保証が途絶えるなどの大きな影響が出ます。契約先の会社が信頼できるかどうかを見極めることが重要です。
会社の経営状況や実績の確認方法
会社の設立年数、資本金、過去の実績(管理戸数や契約年数など)、財務状況(可能であれば決算情報などを確認)などを調査します。上場企業であればIR情報などが参考になります。また、インターネットでの評判や口コミも参考にしつつ、鵜呑みにしすぎないように注意しましょう。
保証会社の利用や契約内容の確認
サブリース会社によっては、家賃保証に関してさらに別の保証会社を利用している場合があります。その場合、保証の範囲や条件がどうなっているのかも確認しておくとよいでしょう。また、万が一倒産した場合の敷金の取り扱いも契約書で確認が必要です。特に、入居者から預かった敷金がサブリース会社の資産として管理されている場合、倒産時にはその敷金がオーナーや入居者に返還されないリスクがあるため、敷金の管理方法や保全措置についても確認することが望ましいです。
その他、契約書で確認しておきたい細かな条項
上記以外にも、契約書には様々な条項が含まれています。細かく感じるかもしれませんが、後々のトラブルを避けるために目を通しておきましょう。
敷金・礼金・更新料などの取り扱い
入居者から受け取る敷金、礼金、更新料などが、最終的にオーナーとサブリース会社の間でどのように分配されるのか(あるいは全額サブリース会社の収益となるのか)を確認します。
契約解除の正当事由
どのような場合に契約が解除される可能性があるのか(オーナー側、サブリース会社側双方から)、「正当事由」とは具体的にどのようなケースを指すのかを確認します。
報告義務(サブリース会社からオーナーへの報告内容や頻度)
サブリース会社からオーナーに対して、物件の状況や入居状況、収支状況などについて、どのくらいの頻度で、どのような内容の報告があるのかを確認します。適切な情報開示があるかどうかも信頼性を見極めるポイントになります。
これらのチェックポイントを参考に、契約書の内容を隅々まで確認し、少しでも疑問に思う点や不明な点があれば、必ず契約前にサブリース会社の担当者に質問し、納得できるまで説明を求めましょう。説明を受けた内容は、記録として残しておくことをお勧めします。
サブリース とはどんな人に向いてる?賢い活用法と相談先
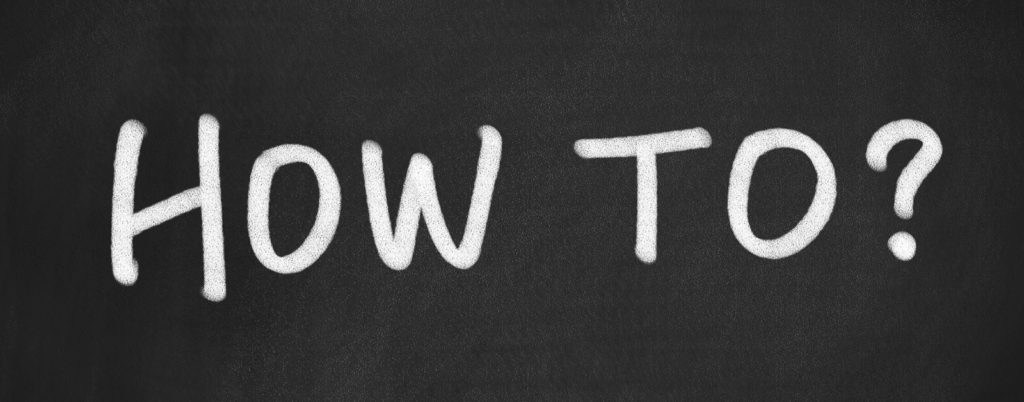
ここまでサブリースの仕組みやメリット・デメリット、契約時のチェックポイントを見てきました。では、実際にサブリースはどのような人に向いているのでしょうか。また、契約で失敗しないためにはどうすればよいのでしょうか。
こんなあなたにおすすめ!サブリースが向いている人の特徴
以下のような考え方や状況の方には、サブリースが有効な選択肢となる可能性があります。
- とにかく手間をかけずに不動産経営をしたい人
- 安定した収入を重視する人(多少利回りが低くても)
- 遠方に住んでいるなど、自主管理が難しい人
- 不動産経営の知識や経験があまりない初心者
ちょっと待って!サブリースが向いていない可能性のある人の特徴
一方で、以下のような方には、サブリースはあまり向いていないかもしれません。
- 収益性を最大限に追求したい人
- 物件の運営に積極的に関わりたい人
- 自分で入居者を選びたい、リフォームを自由に行いたい人
サブリース契約で失敗しないための心構えと情報収集のコツ
サブリース契約で後悔しないためには、以下の点を心がけましょう。
- 1社だけでなく複数の会社から話を聞き比較検討する
- 契約書の内容を隅々まで確認し、不明点は必ず質問する
- 周辺の家賃相場や市場動向を自分でも調べてみる
不安や疑問は専門家に相談!頼れる相談先の例
サブリース契約は複雑で、専門的な知識も必要となるため、自分だけで判断するのが不安な場合は、中立的な立場の専門家に相談することも有効な手段です。
- 不動産鑑定士や不動産コンサルタント
- 弁護士などの法律専門家
まとめ『サブリース とは何かを理解し、賢い不動産投資の第一歩を』
今回は、不動産投資の初心者向けに「サブリース とは何か」という基本的な仕組みから、そのメリット・デメリット、契約時の注意点まで詳しく解説してきました。
サブリースは、空室リスクの軽減や管理業務の委託といったメリットが期待できる一方で、家賃収入の減少や賃料減額リスク、契約期間の縛りといったデメリットも存在します。重要なのは、これらの両側面を正しく理解し、ご自身の状況や目的に照らし合わせて、本当にサブリースが最適な選択肢なのかを慎重に判断することです。
初心者でもサブリースを上手に活用するためのポイントは、以下の3点に集約されるでしょう。
- 情報収集を徹底する(複数の会社を比較、契約書を熟読、法改正の動きも注視)
- メリットだけでなく、デメリットやリスクを正確に理解する
- 不明な点や不安な点は、納得できるまで確認・相談する
安易な契約は禁物です。「家賃保証だから安心」「全部お任せできるから楽だ」といった言葉だけに安易に流されず、ご自身でしっかりと情報を集め、冷静に判断することが、後悔しないための最も大切な心構えです。
この記事が、あなたが「サブリース とは何か」を深く理解し、賢い不動産投資の第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。あなたの不動産投資が成功することを心より願っています。



