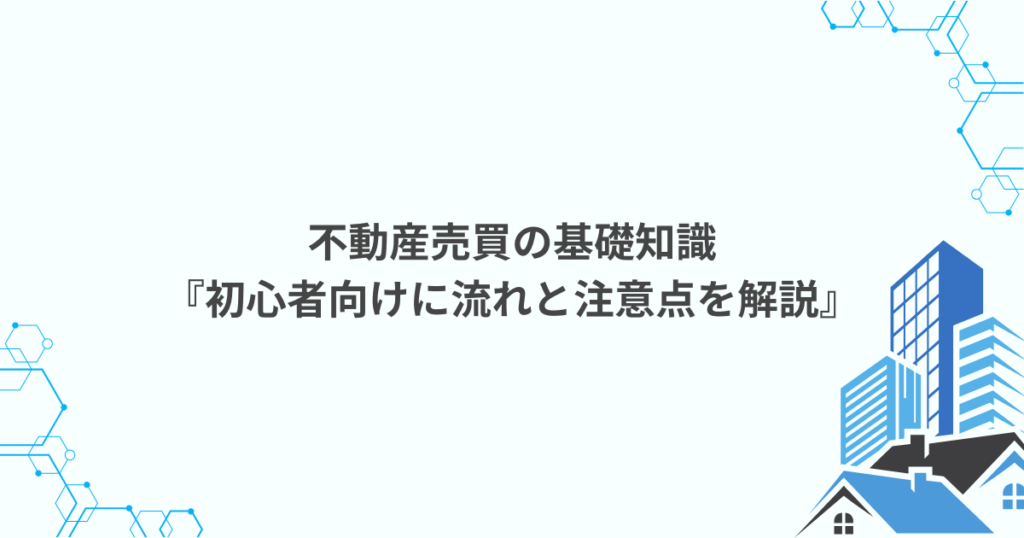
不動産の売却や購入は、人生の中でも大きな決断の一つです。しかし、「何から始めればいいのか分からない」「手続きが複雑そうで不安だ」「失敗したらどうしよう」と感じている初心者の方は少なくありません。
この記事では、そんな不動産売買の初心者の方に向けて、売却と購入それぞれの基本的な「流れ」と、後悔しないために知っておきたい「注意点」を、専門用語を避けながら基礎から分かりやすく解説します。 複雑なプロセス、必要な費用、契約時のポイントなどを事前に把握すれば、知識不足による不安が軽くなり、安心して準備を進められます。
この記事を読むことで、不動産売買の全体像を理解し、自信を持って次の一歩を踏み出すための不動産売買の基礎知識を身につけることを目指します。さあ、一緒に学んでいきましょう!
そもそも不動産売買とは?最初に知っておきたい基礎知識

不動産売買と聞くと、難しそうだと感じる方もいるかもしれません。しかし、基本的なことを知っておけば、より身近なものとして捉えることができます。まずは、不動産売買の「そもそも」から見ていきましょう。
不動産売買の主な目的と種類(居住用・投資用など)
「不動産売買」とは、文字通り、土地や建物といった「不動産」を売ったり買ったりする取引のことです。この取引には、いくつかの目的や種類があります。
居住用
自分で住むための家(マイホーム)を買ったり、住み替えのために今の家を売ったりする場合です。最も一般的な目的の一つと言えるでしょう。
投資用
家賃収入を得る目的(アパート経営など)や、将来の値上がりを期待して不動産を購入する場合です。
事業用
事務所や店舗など、ビジネスのために不動産を売買する場合です。
その他: 相続で受け継いだ不動産を売却したり、資産整理のために売却したりするケースもあります。
土地
建物が建っていない更地などの売買です。
戸建て
一軒家の売買です。新築と中古があります。
マンション
集合住宅の一室の売買です。こちらも新築と中古があります。
このように、不動産売買と一口に言っても、目的や物件の種類は様々です。ご自身の状況に合わせて、どのケースに当てはまるのかを考えてみましょう。なお、この記事では主に居住用不動産の売買について解説します。投資用不動産は税金やローンなどの条件が異なるため、別途専門的な情報をご確認ください。
なぜ初心者こそ「不動産売買の基礎知識」が重要なのか?
不動産売買は、扱う金額が非常に大きいのが特徴です。数千万円、場合によっては億単位のお金が動くこともあります。そのため、不動産売買の基礎知識がないまま進めてしまうと、思わぬ失敗や損につながる可能性があります。
適切な価格で取引できない
相場を知らない場合、相場より安く売ってしまったり、高く買いすぎてしまったりする可能性があります。
不利な契約を結んでしまう
契約内容をよく理解しないままサインしてしまうと、後でトラブルになる可能性があります。
手続きがスムーズに進まない
何をいつまでにやるべきか分からないと、時間がかかったり、余計な手間が増えたりします。
悪徳業者に騙されるリスク
残念ながら、知識のない初心者を狙う悪質な業者が存在する可能性もゼロではありません。
基本的な知識を身につけておくことで、これらのリスクを避け、自分自身を守ることにつながります。また、不動産会社の担当者と対等に話を進めたり、自分で判断したりするためにも、基礎知識は不可欠なのです。
売却が先?購入が先?考えるべきポイント
今の家に住みながら新しい家を探す「住み替え」の場合、「今の家を売るのが先か、新しい家を買うのが先か」という悩みが出てきます。これは「売り先行」「買い先行」と呼ばれ、それぞれにメリット・デメリットがあります。
売却代金が確定するので、新しい家の資金計画を立てやすい。売却に時間をかけられる。
売却後にすぐ新居が見つからない場合、仮住まいが必要になる可能性がある。良い購入物件を見つけても、売却が決まるまで待ってもらえないことがある。
気に入った物件を先に確保できる。仮住まいの心配がない。
売却がスムーズに進まないと、住宅ローンを二重に抱える(ダブルローン)リスクがある。売却を焦ってしまい、安く売ってしまう可能性がある。
どちらが良いかは、ご自身の資金状況、住み替え先の状況、不動産市場の動向などによって異なります。不動産会社の担当者ともよく相談し、自分に合った進め方を選ぶことが重要です。
【売却編】不動産売買の流れと押さえるべき基礎知識

「家を売りたい」と思ったら、具体的にどのようなステップで進んでいくのでしょうか?ここでは、不動産売却の基本的な流れと、各段階で押さえておきたい不動産売買の基礎知識を解説します。
ステップ1『売却相場を調べ、不動産会社に査定を依頼する』
まず最初に行うべきは、「自分の不動産がいくらくらいで売れそうか」という相場を知ることです。
相場調査
インターネットの不動産ポータルサイトで、近隣の似たような物件がいくらで売りに出されているか、過去の取引価格(成約価格)などを調べてみましょう。国土交通省の「不動産取引価格情報検索」なども参考になります。
査定依頼
相場を把握したら、不動産会社に「査定」を依頼します。査定とは、不動産のプロが物件の状態や周辺環境、市場動向などを考慮して、売却できそうな価格(査定価格)を算出することです。
- 簡易査定(机上査定)
物件情報(住所、築年数、広さなど)をもとに、現地を見ずに概算価格を出す方法。手軽に依頼できます。 - 訪問査定
実際に不動産会社の担当者が現地を訪問し、物件の状態を詳しく確認して査定価格を出す方法。より正確な価格が分かります。
査定は無料で行われることが一般的です。1社だけでなく、複数の不動産会社に依頼し、査定価格や担当者の対応を比較検討することが推奨されます。
ステップ2『不動産会社を選び、媒介契約を結ぶ』
査定結果や担当者の提案内容などを比較し、売却を任せる不動産会社を決めたら、「媒介契約(ばいかいけいやく)」を結びます。これは、「私の不動産の売却活動をお願いします」という正式な依頼契約です。媒介契約には主に3つの種類があります。
複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる。
- 自分で買主を見つけて直接契約することも可能(自己発見取引)。
- 不動産会社に売却状況の報告義務がない。
- レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録義務がない。
売却を依頼できるのは1社のみ。
- 自分で買主を見つけて直接契約することは可能。
- 不動産会社は2週間に1回以上、売却状況を報告する義務がある。
- 契約から7日以内にレインズへ登録する義務がある。
売却を依頼できるのは1社のみ。
- 自分で買主を見つけても、必ずその不動産会社を通して契約する必要がある(自己発見取引が認められない)。
- 不動産会社は1週間に1回以上、売却状況を報告する義務がある。
- 契約から5日以内にレインズへ登録する義務がある。
どの契約を選ぶかは、売主の希望や戦略によって異なります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、不動産会社と相談して決めることが重要です。契約期間は通常3ヶ月です。
ステップ3『売却活動の開始と購入希望者の内覧対応』
媒介契約を結んだら、いよいよ売却活動がスタートします。不動産会社は、以下のような方法で買主を探します。
- 自社の顧客への紹介
- 不動産ポータルサイトへの掲載
- 自社ホームページへの掲載
- レインズへの登録(専任・専属専任の場合)
- 新聞折り込みチラシやポスティング
購入に興味を持った人が現れたら、「内覧」の希望が入ります。内覧は、購入希望者が実際に物件を見て、購入するかどうかを判断する重要な機会です。
内覧前の準備
室内をきれいに掃除・整理整頓しておくことが大切です。明るい印象を与えるために、照明をつけたり、カーテンを開けたりすると良いでしょう。水回りなども清潔にしておくことが好印象につながります。
内覧当日の対応
不動産会社の担当者が主体となって案内しますが、売主として質問に答えたり、住み心地などを伝えたりすることもあります。丁寧な対応を心がけることが望ましいです。
ステップ4『購入希望者との条件交渉と売買契約の締結』
内覧の結果、購入希望者から「購入したい」という意思表示(購入申込書、買付証明書など)があったら、具体的な条件交渉に入ります。
- 売買価格
- 引き渡し時期
- 手付金の額
- その他(エアコンなどの付帯設備をどうするか、など)
不動産会社の担当者が間に入って交渉を進めてくれます。条件がまとまったら、いよいよ「売買契約」を結びます。
契約に先立ち、宅地建物取引士(不動産会社の資格者)が、物件に関する重要な情報(登記情報、法令上の制限、契約条件など)を記載した「重要事項説明書」を読み上げ、説明します。内容をしっかり確認し、不明な点は必ず質問することが重要です。
重要事項説明に納得したら、売買契約書の内容を確認し、売主・買主双方が署名・捺印します。
買主から売主へ、手付金(売買代金の一部)が支払われます。
売買契約は法的な拘束力を持つ重要な契約です。安易に考えず、内容を十分に理解してから進める必要があります。
ステップ5『買主からの代金受領(決済)と物件の引き渡し』
売買契約を結んだら、契約時に定めた引き渡し日に向けて準備を進めます。
- 引っ越しの手配、荷物の搬出
- 公共料金(電気・ガス・水道)の精算
- 住宅ローンの残債がある場合は、完済手続き(抵当権抹消の準備)
- 引き渡しに必要な書類の準備(登記済権利証または登記識別情報、実印、印鑑証明書など)
そして、引き渡し当日(決済日)を迎えます。決済は、銀行などで行われることが多いです。
決済・引き渡しの流れ
司法書士が立ち会い、所有権移転登記などに必要な書類を確認します。
買主から売主へ、売買代金の残額が支払われます(通常は銀行振込)。
引き渡し日を基準に、固定資産税・都市計画税などを日割りで清算します。
買主へ物件の鍵を引き渡します。
不動産会社への仲介手数料などを支払います。
司法書士が法務局へ所有権移転登記などを申請します。
これで不動産の売却手続きは完了です。
【購入編】不動産売買の流れと押さえるべき基礎知識
夢のマイホーム購入!でも、何から始めればいいのでしょうか?ここでは、不動産を購入する際の基本的な流れと、各ステップで知っておきたい不動産売買の基礎知識を解説します。
ステップ1『予算を決め、資金計画を立てる(ローンの事前審査含む)』
まず最も重要なのが「お金」の話、つまり資金計画です。
予算の把握
- 自己資金
貯蓄など、購入のために用意できるお金はいくらか。 - 借入可能額
住宅ローンでいくら借りられそうか。年収や勤務先、勤続年数などによって変わります。金融機関のウェブサイトでシミュレーションできますが、後述の「事前審査」でより具体的に把握することが推奨されます。 - 諸費用
物件価格以外にも、仲介手数料や登記費用、税金などの「諸費用」がかかります。物件価格の6~10%程度が目安と言われますが、余裕をもって考えておくことが大切です。(詳しくは後の章で解説します)
資金計画
自己資金、借入可能額、諸費用を考慮して、購入できる物件価格の上限(予算)を決めます。無理のない返済計画を立てることが重要です。
住宅ローン事前審査(仮審査)
物件を探し始める前、または探し始めた段階で、金融機関に住宅ローンの事前審査を申し込むことが非常に有効です。これにより、実際にいくら借りられそうかの目安が分かり、予算が明確になります。また、事前審査に通っていると、購入申し込みの際に有利になることがあります
しっかりとした資金計画が、理想の住まい探しの第一歩です。
ステップ2『希望条件を整理し、物件情報を収集・内覧する』
予算が決まったら、次はどんな家に住みたいか、具体的な希望条件を整理しましょう
エリア
通勤・通学時間、周辺環境(スーパー、病院、公園など)、治安
物件種別
新築/中古、マンション/戸建て
広さ・間取り
家族構成やライフスタイルに合わせて
設備
駐車場、システムキッチン、オートロックなど
その他
日当たり、階数、ペット可否など
すべての希望を叶える物件を見つけるのは難しいので、優先順位をつけておくことが大切です。
希望条件がまとまったら、物件情報を集めます。
インターネット
不動産ポータルサイト、不動産会社のホームページ
不動産会社に相談
希望条件を伝え、物件を紹介してもらう
チラシ・広告
新聞折り込み、ポスティングなど
気になる物件が見つかったら、「内覧(物件見学)」を行います。図面や写真だけでは分からない、実際の雰囲気や周辺環境を確認できます。複数の物件を比較検討することが推奨されます。
ステップ3『購入したい物件が決まったら購入申し込み』
「この物件を買いたい!」と決めたら、売主に対して購入の意思を伝えるために「購入申込書(買付証明書など)」を提出します。
- 購入希望価格
- 手付金の額
- 契約希望日、引き渡し希望日
- 住宅ローンの利用予定(金融機関名、借入額など)
- その他の希望条件
購入申込書は、あくまで「購入したい」という意思表示であり、この時点では法的な契約ではありません。しかし、これをもとに売主との条件交渉が始まります。人気物件の場合は、複数の申し込みが入ることもあります。住宅ローンの事前審査に通っていると、売主へのアピールポイントになります。
ステップ4『重要事項説明を受け、売買契約を結ぶ(手付金など)』
売主との間で条件が合意できたら、「売買契約」に進みます。契約は通常、不動産会社の事務所などで行われます。
売買契約の流れ
契約に先立ち、宅地建物取引士が物件に関する重要な情報を説明します(売却編ステップ4と同様)。買主として、権利関係、法令上の制限、建物の状況、契約解除に関する事項などをしっかり確認することが求められます。疑問点は遠慮なく質問することが重要です。
説明内容に納得したら、売買契約書の内容(売買代金、支払い方法、引き渡し時期、特約事項など)を最終確認し、署名・捺印します。
売主へ手付金を支払います。手付金は売買代金の一部に充当されますが、契約の証拠金や、万が一契約解除になった際の違約金としての意味合いも持ちます。金額は売買代金の5~10%程度が一般的ですが、売主と買主の合意で決められます。
売買契約を結ぶと、原則として一方的な都合で解除することは難しくなります(解除する場合は手付金を放棄したり、違約金が発生したりします)。内容を十分に理解し、納得した上で契約することが不可欠です。
ステップ5『住宅ローンの本審査と契約、決済、物件の引き渡し』
売買契約を結んだら、住宅ローンを利用する場合は、金融機関に「本審査」を申し込みます。事前審査に通っていても、本審査で否決される可能性もゼロではありません。
住宅ローン本審査
事前審査よりも詳細な書類(売買契約書の写し、所得証明書、物件資料など)を提出し、金融機関が最終的な融資可否を判断します。審査には通常1~2週間程度かかります。
ローン契約(金銭消費貸借契約)
本審査に承認されたら、金融機関と正式な住宅ローンの契約を結びます。
そして、いよいよ最終段階、決済(残代金の支払い)と物件の引き渡しです。
決済・引き渡しの流れ
司法書士が立ち会い、所有権移転登記などに必要な書類を確認します。
約束の決済日に、売買代金の残額を売主の口座に振り込みます(住宅ローンを利用する場合は、このタイミングで融資が実行されます)。
引き渡し日を基準に、固定資産税・都市計画税などを日割りで清算し、売主に支払います。
不動産会社や司法書士へ費用を支払います。
売主から物件の鍵を受け取ります。
司法書士が法務局へ所有権移転登記などを申請します。後日、登記識別情報(権利証に代わるもの)が発行されます。
これで晴れて物件が自分のものになります!引っ越しをして、新生活のスタートです。
見落とし厳禁!不動産売買にかかる費用・税金の基礎知識
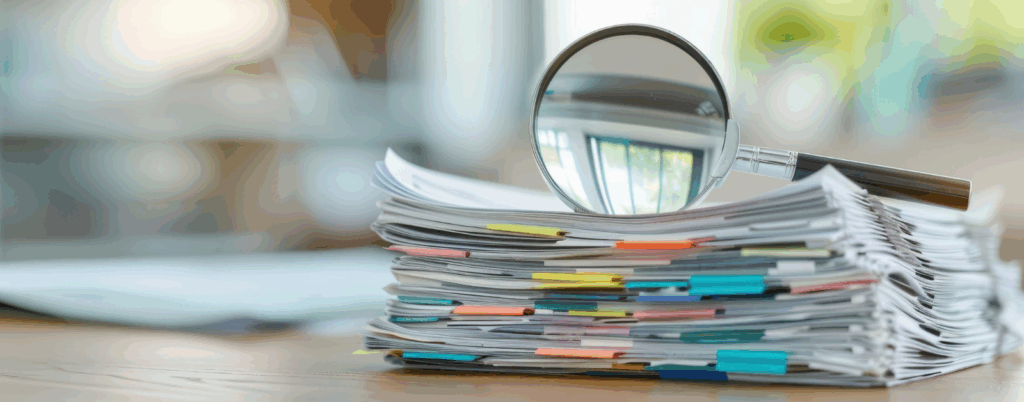
不動産売買では、物件の価格以外にも様々な「諸費用」や「税金」がかかります。これらを把握しておくことは、正確な資金計画を立てる上で非常に重要です。ここでは、主な費用と税金について、不動産売買の基礎知識として押さえておきましょう。
【売却時】仲介手数料、印紙税、登記費用、譲渡所得税など
不動産を売却する際には、主に以下のような費用や税金がかかります。
仲介手数料
不動産会社に売却を仲介してもらった成功報酬として支払う費用です。法律で上限額が定められています(詳しくは後述)。通常、売買契約時と引き渡し時に半金ずつ支払うことが多いです。
印紙税
売買契約書に貼る収入印紙の代金です。契約金額によって税額が変わります。
登記費用(抵当権抹消など)
売却する不動産に住宅ローンが残っている場合、ローンを完済し、抵当権を抹消するための登記費用(登録免許税と司法書士への報酬)がかかります。
譲渡所得税・住民税
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合に課税されます。利益が出なければ課税されません。所有期間によって税率が異なり、マイホームの売却には様々な特例(控除)があります。
その他
引っ越し費用、ハウスクリーニング費用、測量費用(土地の境界が不明確な場合)などがかかることもあります。
【購入時】仲介手数料、印紙税、登記費用、不動産取得税、ローン費用など
不動産を購入する際には、主に以下のような費用や税金がかかります。
仲介手数料
売却時と同様、不動産会社に購入を仲介してもらった場合に支払います(上限額は売却時と同じ)。
印紙税
売買契約書や住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約書)に貼る収入印紙の代金です。
登記費用(所有権移転・抵当権設定など)
不動産の所有権を自分名義に変更する「所有権移転登記」や、住宅ローンを借りる際に金融機関が設定する「抵当権設定登記」にかかる費用(登録免許税と司法書士への報酬)です。登録免許税は、土地・建物の評価額や税率によって決まります。
不動産取得税
不動産を取得した際に、一度だけ都道府県から課税される税金です。取得後しばらくしてから納税通知書が届きます。土地や建物の評価額に基づいて計算されますが、軽減措置があります。
住宅ローン関連費用
住宅ローンを利用する場合にかかる費用です。主なものに、金融機関に支払う「融資事務手数料」や、保証会社に支払う「ローン保証料」などがあります。保証料が不要な金融機関もあります。
固定資産税・都市計画税の清算金
物件の引き渡し日を境に、その年の固定資産税・都市計画税を日割り計算し、売主が既に納付した分などを買主が負担します。
その他
火災保険料・地震保険料、引っ越し費用、リフォーム費用(中古物件の場合など)がかかることもあります。
意外とかかる?諸費用の目安とシミュレーション
これらの諸費用は、物件価格とは別に用意する必要があります。一般的に、中古物件の購入では物件価格の6~10%程度、新築物件では3~7%程度が目安と言われています。
(※新築分譲物件の場合、売主から直接購入すると仲介手数料がかからないため、中古物件より諸費用の割合が低くなる傾向があります。)
仲介手数料
約105万円((3000万円 × 3% + 6万円) + 消費税)
印紙税
1万円(売買契約書、軽減措置適用後 ※契約金額による)
登記費用
30~50万円程度(登録免許税+司法書士報酬 ※評価額や税率による)
不動産取得税
0円~数十万円(軽減措置が適用される場合が多い ※評価額による)
ローン関連費用
数万円~数十万円(金融機関や保証料の有無による)
固定資産税等清算金
数万円~十数万円(物件や引き渡し時期による)
火災保険料
数万円~数十万円(契約内容や期間による)
合計:約150万円~250万円以上(物件価格の約5%~8%以上)
※上記はあくまで一例です。物件の種類(新築/中古、マンション/戸建て)、地域、取引条件、利用する金融機関、税金の軽減措置の適用有無などによって、実際の金額は大きく異なります。正確な金額は不動産会社や金融機関に見積もりを依頼して確認する必要があります。
このように、諸費用だけでもかなりの金額になります。資金計画を立てる際には、必ず諸費用分を考慮に入れるようにしてください。
節税に繋がる可能性のある特例や控除(概要)
不動産売買に関連する税金には、条件を満たせば適用できる特例や控除(税金の負担を軽くする制度)がいくつかあります。すべてをここで詳しく説明することはできませんが、代表的なものをいくつかご紹介します。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
マイホームを売却して利益が出ても、最高3,000万円まで控除できる制度。
特定の居住用財産の買換え・交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
マイホームを買い換える場合に、譲渡益への課税を将来に繰り延べられる制度。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、年末のローン残高に応じて一定期間、所得税(一部住民税)が還付される制度。
不動産取得税の軽減措置
一定の要件を満たす住宅や土地について、税額が軽減される制度。
登録免許税の軽減措置
一定の要件を満たす住宅用家屋について、所有権移転登記や抵当権設定登記の税率が軽減される制度。
これらの制度には細かい適用要件があります。利用できるかどうか、具体的な手続きについては、税務署や税理士、不動産会社などの専門家に確認することが推奨されます。
【初心者必見】不動産売買の注意点とよくある疑問・不安解消Q&A

ここまで不動産売買の流れや費用について見てきましたが、初心者にとってはまだまだ不安や疑問が多いかもしれません。ここでは、特に注意すべき点や、よくある質問にQ&A形式でお答えします。
- 信頼できる不動産会社はどうやって見つける?
-
不動産会社選びは売買成功の鍵を握ると言っても過 言ではありません。以下の点を参考に、信頼できるパートナーを見つけることが重要です。
免許番号を確認する
不動産会社の事務所には、免許番号(例:「東京都知事(3)第○○○○○号」)が掲示されています。カッコ内の数字は免許の更新回数を示し、数字が大きいほど業歴が長いと言えますが、絶対的な指標ではありません。国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」でも確認できます。
得意分野を確認する
不動産会社には、賃貸仲介が得意、売買が得意、特定のエリアに強い、マンション専門など、それぞれの得意分野があります。自分の目的(売却か購入か、物件種別など)に合った会社を選ぶことが大切です。
査定の根拠をしっかり説明してくれるか(売却の場合)
なぜその査定価格になったのか、具体的な根拠や市場データを示して説明してくれる会社は信頼できます。単に高い査定額を提示するだけでなく、現実的な売却戦略を提案してくれるかも重要です。
担当者との相性も重要
不動産売買は担当者と二人三脚で進める期間が長くなります。こちらの話をしっかり聞いてくれるか、質問に丁寧に答えてくれるか、連絡はスムーズかなど、コミュニケーションの取りやすさも確認するポイントです。
複数の会社を比較検討する
最初から1社に絞らず、複数の会社に相談(査定依頼や物件紹介依頼)し、提案内容や担当者の対応を比較して決めることが推奨されます。
- 契約時に特に気をつけるべきことは?(重要事項説明・契約不適合責任など)
-
売買契約は非常に重要です。以下の点には特に注意が必要です。
重要事項説明は必ずしっかり聞く
専門用語が多くて難しいと感じるかもしれませんが、物件の状態や権利関係、法令上の制限など、後々のトラブルを防ぐための重要な情報が含まれています。分からないことはその場で必ず質問し、納得してから契約に進むことが肝要です。説明は宅地建物取引士の資格を持つ人が行う義務があります。
契約書の内容を隅々まで確認する
売買代金、手付金の額、引き渡し時期はもちろん、「特約事項」なども見落とさないように注意が必要です。不明な点があれば、署名・捺印する前に必ず確認してください。
手付金の意味を理解する
手付金は、契約が成立した証拠であると同時に、解約手付としての性質も持ちます。買主は手付金を放棄すれば、売主は受け取った手付金の倍額を買主に支払えば、相手方が契約の履行に着手するまでは契約を解除できます。
「契約不適合責任」を理解する(主に売主向け)
以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものです。引き渡した物件が、種類、品質、数量に関して契約内容に適合しないものであった場合、売主は買主に対して、修理(追完)、代金減額、損害賠償、契約解除などの責任を負う可能性があります。例えば、雨漏り、建物の主要な構造部分の欠陥(基礎のひび割れなど)、シロアリ被害などが該当する可能性があります。 特に中古物件の場合、どこまでが契約不適合にあたるのか、事前に不動産会社とよく相談し、物件の状況を買主に正確に伝えることが重要です。買主は、不適合を知った時から1年以内に売主に通知する必要があります。中古物件の購入を検討する際は、専門家による建物状況調査(ホームインスペクション)を利用することも、リスクを減らすために有効な手段です。
事故物件(心理的瑕疵)について
過去にその物件で自殺、殺人、火災による死亡事故などがあった場合(いわゆる事故物件)、これは心理的瑕疵と呼ばれ、買主の判断に重要な影響を与える可能性があります。売主や不動産会社は、知っている事実について買主に告知する義務があります。内覧時や契約前の段階で、気になる場合は不動産会社に確認するようにしてください。
- 内覧ではどこをチェックすればいい?【購入者向け】
-
内覧は、物件の状態を自分の目で確認できる貴重な機会です。以下のポイントをチェックすることが有効です。
建物全体
- 日当たり・風通し: 時間帯を変えて確認できるとベストです。
- 眺望: 周辺の建物との距離感なども確認します。
- 騒音・臭い: 周辺環境(道路、工場、店舗など)からの影響も確認します。窓を開け閉めして確認すると良いでしょう。
- 共用部分(マンションの場合): エントランス、廊下、ゴミ置き場などがきれいに管理されているか。管理状況が良いかの指標になります。
室内
- 間取り・広さ: 家具の配置をイメージしながら、実際の生活動線を確認します。収納スペースも忘れずにチェックします。
- 水回り(キッチン、浴室、トイレ、洗面所): 使い勝手、清潔さ、水漏れの跡がないかなどを確認。
- 壁・床・天井: ひび割れ、シミ、カビ、傾きがないか。
- 建具(ドア、窓、ふすまなど): 開閉がスムーズか、隙間がないか。
- 設備: 給湯器、エアコン、換気扇などの動作状況や製造年月日を確認。
周辺環境
- 最寄り駅からの距離・道のり: 実際に歩いて確認します。夜間の雰囲気もチェックできると安心につながります。
- 生活利便施設: スーパー、コンビニ、病院、学校、公園などが近くにあるか。
- 治安: 周辺の雰囲気を確認します。
内覧時にはメジャーやメモ帳、カメラ(スマホ)などを持っていくと便利です。気になる点は遠慮なく不動産会社の担当者に質問してください。
- 査定価格=売却価格ではない?【売主向け】
-
その通りです。査定価格はあくまで「このくらいの価格で売れる可能性が高い」という不動産会社の予想価格であり、実際に売れる価格(成約価格)とは異なる場合があります。
査定価格
不動産会社が物件の状態や市場動向などから算出する「売却予想価格」。
売出価格
査定価格を参考に、売主の希望なども考慮して、実際に売りに出す価格。通常、査定価格と同額か、少し高めに設定することが多いです。
成約価格
最終的に買主と合意して売買契約を結んだ価格。売出価格から値引き交渉が入ることもあります。
査定価格は不動産会社を選ぶ上での重要な判断材料ですが、高すぎる査定額に惑わされず、その根拠をしっかり確認することが大切です。最終的な売出価格は、不動産会社とよく相談し、周辺の相場や売却戦略を踏まえて決めることが重要です。
- 住宅ローン審査で落ちることはある?【購入者向け】
-
残念ながら、住宅ローンの審査に落ちてしまう(否決される)可能性はあります。特に、事前審査に通っていても、本審査で状況が変わることもあり得ます。
- 年収と返済負担率
年収に対して、年間のローン返済額の割合がどれくらいか(通常30~35%以内が目安)。 - 勤務先・勤続年数
安定した収入があるか。勤続年数が短いと不利になることも。 - 他の借入状況
カードローンや自動車ローンなど、他の借入が多いと審査に影響します。 - 個人信用情報
過去にクレジットカードやローンの延滞などがないか(信用情報機関に記録されています)。 - 健康状態
団体信用生命保険(団信)に加入できるか。 - 物件の担保価値
購入する物件が、融資額に見合う担保価値があるか。
もし審査に不安がある場合は、不動産会社や金融機関に早めに相談することが推奨されます。また、売買契約書には、万が一ローン審査に通らなかった場合に契約を白紙解除できる「住宅ローン特約」を付けてもらうのが一般的です。
(※情報の正確性について)この記事の情報は2025年4月現在のものです。不動産に関する税制や法制度は変更される可能性があるため、最新の情報や個別のケースについては、必ず税務署、自治体、不動産会社、税理士、司法書士などの専門家にご確認ください。
まとめ『不動産売買の基礎知識を活かして、成功への第一歩を』
今回は、不動産売買の初心者の方に向けて、売却と購入それぞれの基本的な流れ、かかる費用や税金、そして注意点やよくある疑問について、不動産売買の基礎知識として解説してきました。
不動産売買は、確かに複雑で、大きな金額が動く取引です。しかし、基本的な流れやポイントを理解しておけば、過度に不安になる必要はないでしょう。むしろ、知識はあなた自身を守り、より良い条件で取引を進めるための武器になります。
この記事で得た基礎知識をもとに、
まずは気軽に複数の不動産会社に査定を依頼してみることから始めると良いでしょう。
資金計画を立て、住宅ローンの事前審査を受けてみることから始めるのが第一歩です。
そして、信頼できる不動産会社の担当者を見つけ、パートナーとして一緒に進めていくことが、不動産売買を成功させるための重要なステップです。
不動産売買は、あなたのライフプランにおける大きな一歩となるはずです。この記事が、その第一歩を自信を持って踏み出すための一助となれば幸いです。


