
「そろそろマイホームを…」「この不動産、どうやって売却すればいいんだろう?」人生で大きな転機となる不動産取引。しかし、専門用語の多さや手続きの複雑さから、何から手をつければ良いのか分からず、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな不動産取引の“かなめ”となる「不動産仲介」について、その基本的な仕組みから、気になる仲介手数料の詳細、売買を進める際の具体的な流れ、そして少しややこしく感じる媒介契約の種類まで、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。
この記事を読むことで、不動産仲介に関する漠然とした不安が解消され、取引の全体像がクリアに見えてくるはずです。さらに、ご自身にとって最適な選択をするための知識が身につくため、不利な条件での契約を避け、安心して不動産会社とコミュニケーションを取れるようになります。読後は、自信を持って不動産取引の第一歩を踏み出し、後悔のない大切な資産の売買を実現するための土台が整っている状態を目指します。
まずはここから!不動産仲介の基礎知識と全体像を掴もう

不動産取引を考え始めたとき、多くの方が耳にする「不動産仲介」。しかし、具体的に何をしてくれるのか、どんな役割があるのか、はっきりとは分からないという方もいらっしゃるでしょう。このセクションでは、不動産仲介の最も基本的な部分と、その全体像を分かりやすく解説します。 不動産仲介の基礎知識を身につける最初のステップとして、まずはここから理解を深めていきましょう。
不動産仲介とは?売主と買主を繋ぐ役割と基本的な仕組み
不動産仲介とは、簡単に言うと、不動産を「売りたい人(売主)」と「買いたい人(買主)」の間に立って、双方の取引がスムーズに成立するようサポートする業務のことです。不動産会社(宅地建物取引業者)が、この仲介役を担います。
不動産仲介業者は、売主と買主の間に立ち、以下のような多岐にわたる業務を行います。
- 物件情報の収集と提供
売主からは物件情報を預かり、買主へは希望に合った物件情報を提供します。 - 価格査定
売却希望の物件について、市場相場や物件の状態を考慮して適正な価格を査定します。 - 販売活動・購入サポート
物件の広告活動、購入希望者の案内(内覧)、条件交渉のサポートなどを行います。 - 契約条件の調整
売主と買主双方の希望条件を調整し、合意形成をサポートします。 - 契約書類の作成
売買契約書や重要事項説明書など、専門知識が必要な書類を作成します。 - 重要事項の説明
買主に対して、物件に関する重要な情報を法律に基づき説明します。 - 契約締結・決済のサポート
売買契約の締結から、ローンの手続き、物件の引き渡し、登記手続きまでをサポートします。 - トラブル防止のためのアドバイス
取引に関する様々な疑問や不安に対応し、トラブルを未然に防ぐための助言を行います。
仲介業者に依頼するメリット・デメリット
不動産仲介業者に依頼することには、以下のようなメリットとデメリットがあります。
専門知識と経験の活用
法律や税務、建築など専門知識が必要な不動産取引を、専門家である不動産会社に任せられるため安心です。
広範囲な情報網
不動産会社は独自のネットワークや不動産流通システム(レインズなど)を活用し、広範囲から売却先や購入物件を探すことができます。
適正価格での取引
市場相場に基づいた適正な価格での取引が期待できます。
手続きの代行と時間的負担の軽減
煩雑な手続きや交渉を代行してくれるため、時間や手間を大幅に削減できます。
トラブル回避
契約内容のチェックや法的な手続きを専門家が行うことで、後々のトラブルを回避しやすくなります。
仲介手数料の発生
仲介業者に依頼すると、成功報酬として仲介手数料が発生します。
業者による力量差
担当者や会社の力量によって、販売活動の質や期間、取引の満足度が左右されることがあります。
なぜ不動産仲介が必要?個人間取引との違いと注意点
不動産取引は、理論上は売主と買主が直接交渉する「個人間取引」も可能です。しかし、多くの場合、不動産仲介が利用されるのには明確な理由があります。
専門知識の必要性とリスク回避
不動産取引には、民法、宅地建物取引業法、建築基準法、都市計画法など、多くの法律が複雑に絡み合っています。物件の権利関係、法令上の制限、隠れた瑕疵(欠陥)の取り扱いなど、専門知識がなければ見落としてしまうリスクが多数存在します。
個人間取引では、これらのリスクを全て自分で負うことになります。例えば、物件に重大な欠陥が見つかった場合、契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)を問われ、損害賠償や契約解除に至るケースも考えられます。不動産仲介を利用すれば、専門家がこれらのリスクを事前にチェックし、適切な対応をアドバイスしてくれるため、安心して取引を進められます。
取引の透明性と安全性
不動産仲介業者は、法律に基づき、買主に対して物件に関する重要な情報を開示する「重要事項説明」を行う義務があります。これにより、買主は不利な情報を知らされずに契約してしまうリスクを減らすことができます。
また、代金の支払いや物件の引き渡し、所有権移転登記といった手続きも、司法書士などの専門家と連携しながら安全かつ確実に行われるようサポートしてくれます。個人間取引では、こうした手続きの安全性確保も自己責任となり、トラブルが生じやすいポイントです。
不動産会社にも種類がある?大手と地域密着型の特徴
不動産会社と一口に言っても、全国展開している大手企業から、特定のエリアに強みを持つ地域密着型の企業まで様々です。それぞれに特徴があり、どちらが良いとは一概には言えません。ご自身の状況や希望に合わせて選ぶことが大切です。
- 大手不動産会社
- メリット
全国的な知名度とブランド力があり、広範囲な情報網を持っています。テレビCMなどで馴染みがある会社も多いでしょう。集客力が高く、多くの買主候補・売却物件情報にアクセスできる可能性があります。研修制度が充実しており、一定水準以上のサービスが期待できる場合が多いです。 - デメリット
組織が大きいため、担当者の異動があったり、画一的な対応になったりする可能性も指摘されます。仲介手数料の値引き交渉が難しい傾向にあるとも言われます。
- メリット
- 地域密着型不動産会社
- メリット
特定のエリアに特化しているため、その地域の相場や物件情報、生活環境に関する詳細な情報を持っていることが多いです。地元ならではのネットワークを活かした、きめ細かい対応や柔軟な交渉が期待できる場合もあります。大手にはない未公開物件の情報を持っていることも。 - デメリット
情報網や広告宣伝力は、大手に比べて限定的になる可能性があります。会社の規模が小さい場合、担当者個人の力量に左右される部分が大きいこともあります。
- メリット
不動産会社によっては、マンション専門、戸建て専門、投資用物件専門など、得意とする物件種別がある場合があります。また、特定の市区町村や沿線に特化している会社もあります。ご自身の売買したい物件の種類やエリアに合わせて、その分野に強みを持つ不動産会社を選ぶことも重要なポイントです。
【徹底解説】不動産仲介でかかる手数料の基礎知識と相場

不動産仲介を利用する際に、最も気になることの一つが「仲介手数料」ではないでしょうか。高額なイメージがあるかもしれませんが、その金額や支払いタイミングには法律で定められたルールがあります。ここでは、不動産仲介の基礎知識の中でも特に重要な仲介手数料について、その上限、計算方法、支払い時期、そして仲介手数料以外に必要な諸費用まで詳しく解説します。
仲介手数料はいくらかかる?法律で定められた上限と計算方法
不動産会社が受け取ることのできる仲介手数料の上限は、宅地建物取引業法で定められています。これを超える金額を請求することはできません。
宅地建物取引業法に基づく計算式(速算式も紹介)
仲介手数料の上限額は、売買価格に応じて以下の計算式で算出されます(消費税別途)。
売買価格200万円以下の部分: 売買価格 × 5% + 消費税
売買価格200万円を超え400万円以下の部分: 売買価格 × 4% + 消費税
売買価格400万円を超える部分: 売買価格 × 3% + 消費税
この計算は少し複雑なため、実務では以下の「速算式」がよく用いられます。
売買価格が200万円以下の場合: 売買価格 × 5% + 消費税
売買価格が200万円を超え400万円以下の場合: (売買価格 × 4% + 2万円) + 消費税
売買価格が400万円を超える場合: (売買価格 × 3% + 6万円) + 消費税
具体的な計算例(売買価格別)
例として、いくつかの売買価格で仲介手数料の上限額(税抜)を計算してみましょう。
売買価格が300万円の場合(200万円超400万円以下):
(300万円 × 4% + 2万円) = 12万円 + 2万円 = 14万円 これに消費税が加わります。
売買価格が3,000万円の場合(400万円超):
(3,000万円 × 3% + 6万円) = 90万円 + 6万円 = 96万円 これに消費税が加わります。
※上記はあくまで上限額です。不動産会社によっては、この上限額の範囲内で手数料を設定しています。
仲介手数料を支払うタイミングはいつ?契約時と決済時の2回が一般的
仲介手数料は、不動産取引が「成功」したときに支払う「成功報酬」です。つまり、売買契約が成立しなければ、原則として支払う必要はありません。
成功報酬であることの理解
不動産会社に物件の売却や購入の相談をしたり、物件をいくつか案内してもらったりした段階では、仲介手数料は発生しません。あくまで、売主と買主の間で売買契約が成立し、その取引が無事に完了(決済・引き渡し)して初めて、不動産会社は仲介手数料を請求できる権利を得ます。
支払い時期の一般的なケースと確認ポイント
仲介手数料の支払い時期は、法律で明確に定められているわけではありませんが、一般的には以下の2回に分けて支払うケースが多く見られます。
- 売買契約締結時: 仲介手数料の半金
- 物件の引き渡し時(決済時): 残りの半金
ただし、これはあくまで一般的な慣習であり、不動産会社との間で別途合意があれば、一括で支払うケースなどもあります。仲介を依頼する際に、媒介契約書などで支払い時期や条件をしっかりと確認しておくことが重要です。
要注意!仲介手数料以外にも発生する諸費用一覧
不動産取引では、仲介手数料以外にも様々な諸費用が発生します。これらの費用も事前に把握し、資金計画に組み込んでおくことが大切です。
売主側・買主側それぞれでかかる費用(印紙税、登記費用、ローン諸費用など)
以下に主な諸費用を挙げますが、取引の内容や物件によって異なる場合があります。
- 印紙税
売買契約書に貼付する印紙代。売買価格によって金額が異なります。 - 抵当権抹消登記費用
ローンが残っている場合に、抵当権を抹消するための登記費用(司法書士への報酬含む)。 - 譲渡所得税・住民税
不動産を売却して利益が出た場合にかかる税金。 - 引越し費用、ハウスクリーニング費用など
- 印紙税
売買契約書に貼付する印紙代。 - 登録免許税
所有権移転登記や抵当権設定登記などにかかる税金。 - 登記費用(司法書士報酬)
登記手続きを司法書士に依頼する場合の報酬。 - 不動産取得税
不動産を取得した際に一度だけかかる税金。 - 住宅ローン関連費用
ローン事務手数料、保証料、団体信用生命保険料、火災保険料など。 - 固定資産税・都市計画税の清算金
引渡し日を基準に日割りで売主と清算します。 - 引越し費用、家具購入費用など
事前に把握しておくべき費用の概算
諸費用の総額は、物件価格やローンの利用状況などによって大きく変動しますが、一般的に売買価格の数%~10%程度が目安と言われることもあります。ただし、これはあくまで目安であり、個別のケースによって異なります。不動産会社に相談する際には、仲介手数料だけでなく、これらの諸費用についても概算を出してもらい、全体の資金計画を立てることが重要です。
「仲介手数料無料」や「割引」の仕組みと賢い見極め方
最近では、「仲介手数料無料」や「半額」をうたう不動産会社も見かけるようになりました。高額な仲介手数料が抑えられるのは魅力的ですが、その仕組みと留意点を理解しておくことが大切です。
なぜ無料や割引が可能なのか(売主からのみ受領、両手仲介など)
仲介手数料が無料または割引になる主なケースとしては、以下のような理由が考えられます。
売主からのみ手数料を受領するケース(買主無料)
不動産会社が売主からのみ仲介手数料を受け取ることで、買主の手数料を無料または割引にしている場合があります。特に新築物件の販売などで見られることがあります。
両手仲介で調整しているケース
不動産会社が売主と買主の双方から仲介業務の依頼を受けている場合(両手仲介)、双方から手数料を得られるため、一方の手数料を割引する余地が生まれることがあります。
業務効率化によるコスト削減
オンラインでのやり取りを主体にしたり、店舗を持たなかったりすることで経費を削減し、その分を手数料に還元しているケース。
集客戦略の一環
手数料を低く設定することで、多くの顧客を集めようとする戦略。
メリットだけでなくデメリットや注意点も理解する
仲介手数料が安いことは大きなメリットですが、以下の点には注意が必要です。
サービスの質
手数料が安い分、提供されるサービス範囲が限定的であったり、担当者のサポートが手薄になったりする可能性がないか確認が必要です。
物件の選択肢
特定の物件(例えば、売主から手数料を得やすい物件)に誘導される可能性がないか、幅広い選択肢を提案してくれるかを見極める必要があります。
契約内容の確認
なぜ無料や割引が可能なのか、その条件や契約内容をしっかりと確認し、不明な点は遠慮なく質問しましょう。
囲い込みのリスク(両手仲介の場合)
売主・買主双方から手数料を得たいがために、他の不動産会社への情報公開を制限する「囲い込み」が行われていないか注意が必要です。
手数料の安さだけで判断せず、提供されるサービス内容や担当者の対応、取引の透明性などを総合的に比較検討することが、賢い不動産会社選びのポイントです。
不動産仲介の基礎知識『売買取引の具体的な流れをステップで理解』

不動産を売る場合も買う場合も、取引には一定の流れがあります。この流れを事前に把握しておくことで、各ステップで何をすべきか、どんな準備が必要かが見えてきます。ここでは、不動産仲介の基礎知識として、売主と買主それぞれの立場から、不動産取引の具体的な流れを7つのステップに分けて解説します。
【売主編】不動産売却の相談から物件引き渡しまでの7ステップ
不動産を売却する場合の一般的な流れは以下の通りです。各ステップで不動産会社と密に連携を取りながら進めていくことになります。
まずは不動産会社に売却の意思を伝え、相談します。物件の状況や売却希望時期、希望価格などを伝えます。 不動産会社は物件を調査し、市場相場や近隣の取引事例などを基に査定価格を算出します。複数の会社に査定を依頼することも一般的です。
査定価格や販売方針、仲介手数料などに納得できれば、不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があり、それぞれの特徴を理解して選択します(詳しくは後述)。
不動産会社は、物件情報を不動産ポータルサイトへ掲載したり、チラシを作成・配布したり、既存顧客へ紹介したりと、様々な方法で販売活動を行います。 売主は、購入希望者からの内覧希望に対応します。物件の清掃や整理整頓を心がけましょう。
購入希望者が見つかると、価格や引き渡し条件などについて交渉が始まります。不動産会社が間に入り、双方の条件を調整します。
交渉がまとまれば、売買契約を締結します。この際、買主から手付金が支払われます。 契約に先立ち、不動産会社から買主へ「重要事項説明」が行われます。売主も契約内容をしっかりと確認しましょう。
物件に住宅ローンなどの抵当権が設定されている場合は、引き渡しまでに抹消する手続きが必要です。不動産会社や司法書士と連携して進めます。 引っ越しの準備もこの期間に行います。
買主から売買代金の残額が支払われ(決済)、同時に物件の鍵や関連書類を買主に引き渡します。 所有権移転登記の手続きもこのタイミングで行われます。これで売却手続きは完了です。
【買主編】不動産購入の相談から物件引き渡しまでの7ステップ
不動産を購入する場合の一般的な流れは以下の通りです。資金計画をしっかりと立てることが重要になります。
不動産会社に希望する物件の種類、エリア、予算などを伝えて相談します。 自己資金や年収、住宅ローンの借入可能額などを考慮し、無理のない資金計画を立てます。住宅ローンの事前審査をこの段階で受けておくと、その後の物件探しや交渉がスムーズに進みます。
不動産会社から希望条件に合った物件情報を紹介してもらったり、自分で不動産ポータルサイトなどで探したりします。 気になる物件が見つかったら、実際に現地へ足を運び、内覧します。物件の状態だけでなく、周辺環境や日当たり、騒音なども確認しましょう。
購入したい物件が決まったら、不動産会社を通じて売主に「購入申込書(買付証明書)」を提出します。 価格や引き渡し時期などの条件について、売主と交渉を行います。
(まだの場合)金融機関に住宅ローンの事前審査を申し込みます。事前審査に通ったら、売買契約後に本申込みを行います。
交渉がまとまり、住宅ローンの事前審査も通れば、売買契約を締結します。この際、売主に手付金を支払います。 契約に先立ち、不動産会社から「重要事項説明」を受けます。物件に関する重要な情報なので、しっかりと内容を理解しましょう。
住宅ローンの本申込み手続きを行い、金融機関と金銭消費貸借契約(ローン契約)を結びます。 物件の引き渡しまでに、火災保険への加入手続きも必要です。
売主に売買代金の残額を支払い(決済)、同時に物件の鍵や関連書類を受け取ります。 所有権移転登記や抵当権設定登記の手続きもこのタイミングで行われます。これで購入手続きは完了です。
各ステップで「買主・売主がすべきこと」と「不動産会社の役割」
不動産取引をスムーズに進めるためには、買主・売主自身が主体的に関わること、そして不動産会社の役割を理解し、良好なコミュニケーションを取ることが不可欠です。
スムーズな取引のための準備と心構え
- 情報収集と学習
不動産取引に関する基本的な知識を身につけておく。 - 希望条件の明確化
売却・購入の目的、希望価格、時期などを明確にしておく。 - 迅速な意思決定と対応
不動産会社からの連絡には速やかに対応し、必要な書類は早めに準備する。 - 資金計画の確認
特に買主は、購入可能な予算やローンの返済計画をしっかりと立てておく。 - 不明点の確認
疑問や不安な点は遠慮なく不動産会社に質問し、解消しておく。
- 専門家としてのアドバイス
法令や市場動向に基づいた的確なアドバイスを提供する。 - 条件交渉のサポート
売主・買主双方の利益を考慮し、円滑な交渉をサポートする。 - 手続きの代行と進行管理
煩雑な手続きを代行し、取引全体のスケジュールを管理する。 - 情報提供と説明責任
物件情報や契約内容について、正確かつ分かりやすく説明する。 - トラブルの予防と解決支援
潜在的なリスクを予見し、トラブル発生時には解決に向けてサポートする。
重要事項説明など特に注意すべきポイント
不動産取引において、特に買主が注意すべきなのが「重要事項説明」です。これは、宅地建物取引士が、売買契約を締結する前に、物件の権利関係、法令上の制限、インフラの整備状況、契約条件など、買主の意思決定に影響を与える重要な事項を書面(重要事項説明書)に基づいて説明するものです。
- 説明は必ず契約前に受ける
- 内容を十分に理解するまで質問する
- 不明な点や納得できない点があれば、安易に署名・捺印しない
近年では、対面だけでなく、テレビ会議などのITを活用した重要事項説明(IT重説)も一定の条件下で可能となっています。遠隔地の物件取引などで利便性が向上していますが、機器の準備や通信環境の確認が必要です。
また、物件の物理的な欠陥だけでなく、過去にその物件で人の死があったなど、心理的に住み心地に影響を与える可能性のある事柄(いわゆる心理的瑕疵)についても、宅地建物取引業者が知り得た場合には告知すべき事項として扱われることがあります。気になる場合は不動産会社に確認し、説明を求めましょう。
この重要事項説明をしっかりと理解することが、後々のトラブルを防ぐために非常に重要です。売主側も、物件に関する情報は正確に不動産会社に伝える義務があります。
3つの媒介契約の違いとは?不動産仲介の基礎知識と最適な選び方
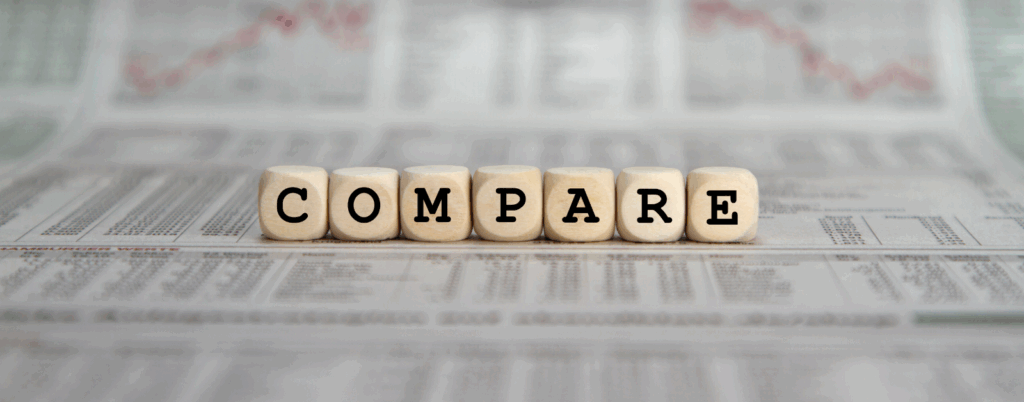
不動産会社に売却の仲介を依頼する際には、「媒介契約」を結びます。この媒介契約には主に3つの種類があり、それぞれ特徴やルールが異なります。どの契約を選ぶかによって、売却活動の進め方や売主の自由度が変わってくるため、不動産仲介の基礎知識としてそれぞれの違いをしっかり理解し、ご自身の状況に合ったものを選ぶことが重要です。
一般媒介契約とは?メリット・デメリットと向いているケース
一般媒介契約は、3つの媒介契約の中で最も自由度の高い契約形態です。
- 複数の不動産会社に依頼可能
同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することができます。 - 自己発見取引もOK
売主自身が買主を見つけて直接契約することも可能です(その場合、仲介手数料は発生しません)。 - レインズへの登録義務なし
不動産会社に、指定流通機構(レインズ)への物件登録義務はありません(任意で登録は可能)。 - 業務報告義務なし
不動産会社に、売主への業務処理状況の報告義務はありません(特約で定めることは可能)。
- 複数の会社に依頼することで、より多くの購入希望者に情報が届く可能性があります。
- 不動産会社間の競争原理が働き、積極的な販売活動が期待できる場合があります。
- 自分で買主を見つけられる可能性がある。
- 不動産会社にとっては、他社で契約が決まってしまうと手数料が得られないため、積極的な広告活動や販売努力が専任媒介などに比べて手薄になる可能性があります。
- 複数の会社とやり取りする必要があるため、手間が増えることがあります。
- レインズへの登録や業務報告が義務ではないため、販売状況が把握しにくい場合があります。
- 人気エリアの物件や希少性の高い物件など、比較的売れやすい自信がある場合。
- 自分で買主を見つけるアテがある場合。
- 複数の不動産会社に依頼して、広く情報を拡散したい場合。
専任媒介契約とは?メリット・デメリットと向いているケース
専任媒介契約は、1社の不動産会社に絞って仲介を依頼する契約形態です。
- 1社の不動産会社のみに依頼
他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することはできません。 - 自己発見取引はOK
売主自身が買主を見つけて直接契約することも可能です。ただし、媒介契約の内容によっては、売主が自ら発見した買主と契約する場合でも、不動産会社が媒介業務に要した実費(広告費用など)の償還を請求されることがあります。詳細は媒介契約書で確認が必要です。 - レインズへの登録義務あり
契約締結日から7日以内に、指定流通機構(レインズ)へ物件情報を登録しなければなりません。 - 業務報告義務あり
不動産会社は、売主に対して2週間に1回以上の頻度で、業務処理状況を文書または電子メールで報告しなければなりません。
- 1社に任せることで、不動産会社が責任を持って積極的に販売活動を行ってくれる可能性が高まります。
- レインズへの登録により、他の不動産会社にも情報が共有され、広く購入希望者を探すことができます。
- 定期的な業務報告により、販売状況を把握しやすくなります。
- 窓口が一本化されるため、やり取りがスムーズになります。
- 依頼した不動産会社の販売力や営業努力に売却の成否が大きく左右されます。信頼できる会社選びがより重要になります。
- 不動産会社による「囲い込み」(他の会社に物件を紹介せず、自社で買主を見つけようとする行為)のリスクが一般媒介より高まる可能性があります(ただし、レインズ登録義務があるため一定の抑止効果はあります)。
- 信頼できる不動産会社を見つけ、集中的に販売活動を任せたい場合。
- 自分で買主を探す手間を省きたいが、万が一自分で見つけた場合の選択肢も残しておきたい場合。
- 販売状況を定期的に把握したい場合。
専属専任媒介契約とは?メリット・デメリットと向いているケース
専属専任媒介契約は、専任媒介契約よりもさらに不動産会社への拘束力が強い契約形態です。
- 1社の不動産会社のみに依頼
他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することはできません。 - 自己発見取引も不可
売主自身が買主を見つけても、必ずその不動産会社を通じて契約しなければならず、仲介手数料が発生します。 - レインズへの登録義務あり
契約締結日から5日以内に、指定流通機構(レインズ)へ物件情報を登録しなければなりません(専任媒介より短い)。 - 業務報告義務あり
不動産会社は、売主に対して1週間に1回以上の頻度で、業務処理状況を文書または電子メールで報告しなければなりません(専任媒介より頻繁)。
- 不動産会社にとっては、確実に仲介手数料を得られる可能性が最も高いため、最も手厚く積極的な販売活動が期待できます。
- レインズへの早期登録と頻繁な業務報告により、販売活動がスピーディーに進み、状況把握もしやすいです。
- 売主の自由度が最も低く、全てを依頼した不動産会社に委ねることになります。会社の選定が極めて重要です。
- 「囲い込み」のリスクは依然として存在します。
- 早期売却を目指しており、不動産会社に全面的に販売活動を任せたい場合。
- 販売戦略や報告などを密に行い、手厚いサポートを受けたい場合。
- 自分で買主を探すつもりがない場合。
【比較一覧表】3つの媒介契約を徹底比較!自分に合った契約形態を選ぶポイント
| 特徴 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 |
|---|---|---|---|
| 依頼できる業者数 | 複数可 | 1社のみ | 1社のみ |
| 自己発見取引 | 可能 | 可能 (※実費償還の場合あり、 媒介契約書で要確認) | 不可 (依頼業者を通す必要あり) |
| レインズへの登録義務 | なし(任意) | 契約日から7日以内 | 契約日から5日以内 |
| 業務報告義務 | なし (特約で定めることは可能) | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| 契約の有効期間 | 法律上の定めなし (通常3ヶ月以内が多い) | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
| メリット例 | 広く情報を拡散、 競争原理が働く | 積極的な活動期待、 窓口一本化、状況把握容易 | 最も手厚い活動期待、 スピーディーな展開期待 |
| デメリット例 | 業者の積極性が低下する 可能性、手間が増える | 業者の力量に左右される、 囲い込みリスク | 自由度が低い、業者の力量に大きく左右される |
自分に合った契約形態を選ぶポイント
- 物件の特性
人気物件か、早期売却が必要かなど、物件の状況を考慮しましょう。 - 売却方針
自分で買主を探したいか、全て任せたいか、どの程度の頻度で報告を受けたいかなど、ご自身の希望を明確にしましょう。 - 不動産会社との信頼関係
特に専任・専属専任を選ぶ場合は、信頼できる不動産会社を選ぶことが最も重要です。担当者の提案力や販売戦略をよく吟味しましょう。
迷った場合は、不動産会社の担当者によく相談し、それぞれの契約形態のメリット・デメリットを十分に理解した上で、納得のいく選択をしてください。
知っておきたい「レインズ(REINS)」の役割と媒介契約との関係
媒介契約の説明で度々登場する「レインズ(REINS)」とは、Real Estate Information Network System の略で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータ・ネットワーク・システムのことです。
不動産情報ネットワークシステムとは
簡単に言うと、会員となっている不動産会社間で物件情報を共有するためのシステムです。売却依頼を受けた不動産会社がレインズに物件情報を登録すると、他の会員不動産会社もその情報を閲覧でき、自社の顧客(購入希望者)に紹介することが可能になります。
買主・売主双方にとってのメリット
- 依頼した不動産会社だけでなく、全国の不動産会社を通じて購入希望者を探せるため、早期成約の可能性が高まります。
- 「囲い込み」(不動産会社が自社だけで取引を完結させようと情報を抱え込むこと)を防ぐ効果があります。
- 多くの物件情報が不動産会社間で共有されるため、より多くの選択肢の中から希望に合った物件を見つけやすくなります。
- 取引の透明性が高まります。
専任媒介契約や専属専任媒介契約では、このレインズへの登録が義務付けられているため、売主・買主双方にとってメリットの大きい、公正な取引を促進する仕組みと言えます。
失敗しない!信頼できる不動産会社を見極めるための基礎知識
不動産取引の成功は、信頼できる不動産会社と出会えるかどうかに大きく左右されます。しかし、数多くの不動産会社の中から、どうやって最適なパートナーを選べば良いのでしょうか。ここでは、不動産仲介の基礎知識の仕上げとして、後悔しない不動産会社選びのための重要なチェックポイントを解説します。
まずは基本!宅地建物取引業の免許番号と行政処分歴を確認する方法
不動産仲介業を営むには、宅地建物取引業の免許が必要です。まずは、その会社が正規の業者であるかを確認しましょう。
免許番号からわかること(大臣免許と知事免許の違い、更新回数など)
不動産会社の広告や店舗には、必ず免許番号が記載されています。免許番号は「国土交通大臣(○)第×××××号」または「○○県知事(○)第×××××号」という形式です。
国土交通大臣免許
複数の都道府県に事務所を設置して事業を行う場合に必要です。
知事免許
1つの都道府県内のみに事務所を設置して事業を行う場合に必要です。
(○)の数字: 免許の更新回数を示します。5年ごとに更新されるため、この数字が大きいほど営業年数が長い一つの目安となります。
(例:(3)であれば、更新2回を経て3期目、つまり10年以上の営業実績がある可能性が高い)
ただし、営業年数が長いからといって必ずしも優良とは限りませんし、新しい会社でも素晴らしいサービスを提供するところはあります。あくまで参考情報の一つと捉えましょう。
国土交通省ネガティブ情報等検索システム等の活用
国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」や、各都道府県の宅地建物取引業担当課のウェブサイトなどで、過去に行政処分(業務停止命令など)を受けた業者を検索できる場合があります。気になる会社があれば、事前に確認してみるのも一つの方法です。
担当者の対応力と専門知識はここをチェック!具体的な質問例と見極め方
不動産会社選びは、最終的には「人」選びとも言えます。信頼できる担当者かどうかを見極めることが非常に重要です。
レスポンスの速さ、説明の分かりやすさ
- 問い合わせや質問に対する返答が迅速かつ丁寧か。
- 専門用語を避け、分かりやすい言葉で説明してくれるか。
- こちらの話を親身になって聞いてくれるか。
これらの点は、基本的なコミュニケーション能力や顧客への姿勢を判断する上で重要です。
物件や地域情報への精通度、提案力
担当者には、物件そのものだけでなく、周辺環境や地域の相場、将来性などについても深い知識が求められます。以下のような質問を投げかけて、その反応を見てみましょう。
- 「この物件のメリット・デメリットを具体的に教えてください。」
- 「このエリアの最近の取引事例や価格動向はどうですか?」
- 「私の希望(売却理由や購入目的)を踏まえて、どのような販売戦略(または物件探し)が考えられますか?」
- 「もし売れ残った(希望物件が見つからない)場合、次の手としてどんな提案がありますか?」
的確な回答や具体的な提案があるか、こちらの疑問や不安を解消しようと努めてくれるかどうかがポイントです。
提示された査定価格は妥当?根拠をしっかり確認する重要性
不動産を売却する場合、不動産会社に査定を依頼しますが、提示された査定価格の高さだけで会社を選んではいけません。
複数の会社に査定を依頼する(相見積もり)
まずは、複数の不動産会社(一般的には3社程度)に査定を依頼し、査定価格を比較してみましょう。これにより、おおよその相場観を掴むことができます。
査定価格の根拠資料の確認ポイント
重要なのは、なぜその査定価格になったのか、その「根拠」です。不動産会社には、査定価格の根拠を明確に説明してもらうようにしましょう。確認すべきポイントは以下の通りです。
- 比較対象物件
どのような物件(成約事例、販売中事例)と比較して価格を算出したのか。比較対象は、立地、築年数、広さ、間取りなどが類似しているか。 - 市場動向
現在の不動産市場の状況(上昇傾向か下降傾向かなど)がどのように反映されているか。 - 物件の個別要素
日当たり、眺望、管理状況、リフォーム履歴など、物件の良い点・悪い点がどのように評価されているか。 - 評価方法
取引事例比較法、原価法、収益還元法など、どのような評価方法を用いているか(主に取引事例比較法が用いられます)。
高すぎる査定価格は、媒介契約を結ぶためだけのものである可能性も(いわゆる「あて馬査定」)。逆に、安すぎる査定価格は、早く売却したい不動産会社の都合かもしれません。根拠が明確で、納得できる説明をしてくれる会社を選びましょう。
口コミや評判だけに頼らない!自分に合った不動産会社選びのコツ
インターネット上には不動産会社の口コミや評判が多数存在しますが、それらを鵜呑みにするのは危険です。個人の感想であり、全てが客観的な事実とは限りません。
得意な物件種別やエリアの確認
前述の通り、不動産会社には得意とする物件種別(マンション、戸建て、土地など)やエリアがあります。ご自身の売買したい物件と、その会社の得意分野が合致しているかを確認しましょう。実績や取引事例などを聞いてみるのも良いでしょう。
契約を急かさないか、親身になってくれるか
- 契約を急かすような言動はないか
こちらのペースを尊重し、じっくりと検討する時間を与えてくれるか。 - メリットだけでなくデメリットも説明してくれるか
物件や取引に関するリスクや不利な情報も正直に伝えてくれるか。 - こちらの不安や疑問に寄り添ってくれるか
専門家としてだけでなく、パートナーとして親身に相談に乗ってくれるか。
最終的には、ご自身が「この担当者になら安心して任せられる」と感じられるかどうかが重要です。複数の会社と実際に会って話を聞き、比較検討することをおすすめします。
まとめ
本記事では、「不動産仲介の基礎知識」として、その仕組みから仲介手数料、売買取引の流れ、媒介契約の種類、そして信頼できる不動産会社の選び方まで、幅広く解説してきました。
不動産取引は、人生における大きなイベントであり、高額な資金が動くため、誰もが不安を感じるものです。しかし、事前に正しい不動産仲介の基礎知識を身につけておくことで、その不安は大きく軽減され、取引の透明性も高まります。仲介手数料がどのように決まるのか、売買はどのようなステップで進むのか、そして自分にはどの媒介契約が合っているのかを理解することで、不動産会社とも対等な立場で話を進めることができるようになるでしょう。
この記事で得た知識を活かし、まずはご自身の状況や希望を整理し、信頼できる不動産会社という良きパートナーを見つけることから始めてみてください。そして、納得のいく不動産取引を実現し、より豊かな未来への第一歩を踏み出されることを心より願っています。


