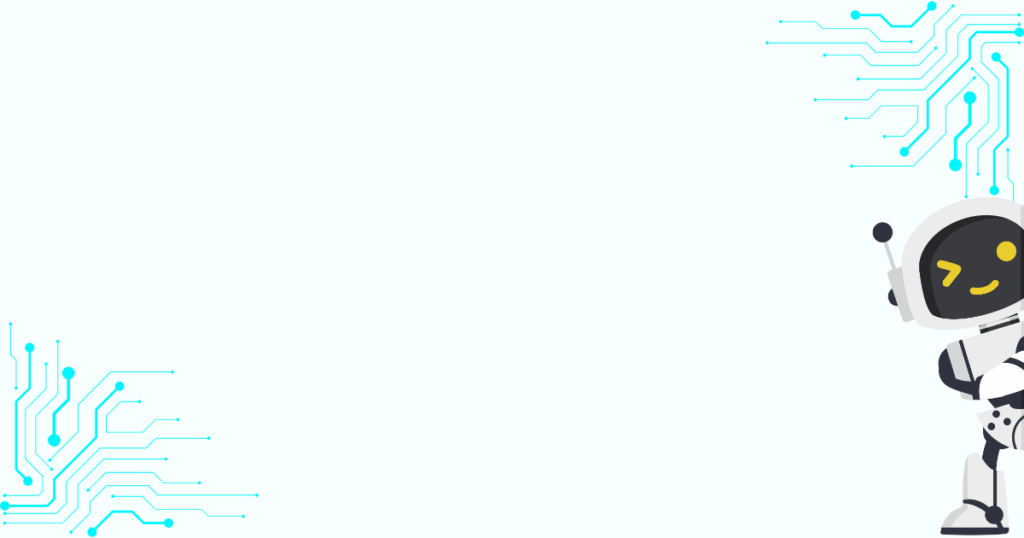「不動産賃貸管理業務」と聞いても、「具体的に何をする仕事?」「不動産仲介とは違うの?」と、その実態がよく分からない初心者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな疑問を持つ方のために、複雑で多岐にわたる「不動産賃貸管理業務」の具体的な仕事内容を、専門用語を噛み砕いてゼロから徹底解説します。入居者募集から家賃管理、クレーム対応、退去精算まで、賃貸経営を支える業務の全体像を網羅的に学べます。
最後まで読めば、管理業務の全体像がスッキリと整理され、「オーナーとして何をすべきか」「仕事としてどんな役割か」が明確になり、「難しそう」という不安が解消されます。
不動産賃貸管理業務とは? 基本の定義と「仲介業務」との違い
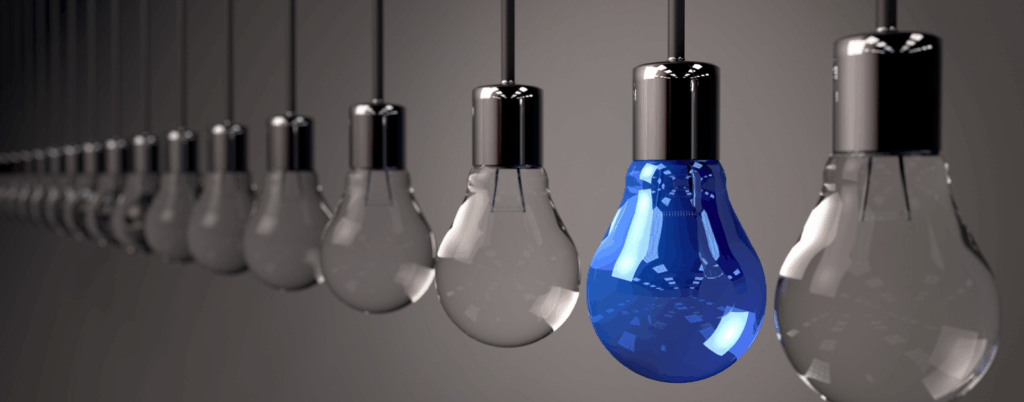
結論|「不動産賃貸管理業務」とはオーナーの賃貸経営を代行する仕事
不動産賃貸管理業務(ふどうさんちんたいかんりぎょうむ)とは、一言でいうと「アパートやマンションのオーナー(大家さん)に代わって、賃貸経営に関わるさまざまな実務を引き受け、その物件と入居者を総合的にサポートする仕事」です。
オーナー業は、物件さえ持っていれば自動的に家賃が入ってくるわけではありません。入居者を見つけ、日々のトラブルに対応し、建物をメンテナンスするなど、やるべきことは山積みです。
これらの「面倒だが非常に重要な業務」を、専門的な知識とノウハウを持つプロ(不動産管理会社)が代行するのが、不動産賃貸管理業務の基本的な役割です。オーナーの負担を減らし、物件の資産価値を維持・向上させながら、安定した賃貸経営を実現することを目指します。
最も重要な違い|「不動産仲介(客付け)」と「不動産管理」の違いを比較
不動産業界の仕事として、初心者の方が最も混同しやすいのが「仲介(ちゅうかい)」と「管理(かんり)」です。この2つは役割が全く異なります。
不動産仲介(客付け)
- 役割
「入居したい人」と「空室を貸したいオーナー」をマッチングさせる仕事。 - 業務
物件の広告宣伝、お客様(入居希望者)への物件紹介(内見)、契約条件の交渉。 - ゴール
賃貸借契約を「成立させる」こと。(契約が終われば、そのお客様との関係は一旦終了)
不動産賃貸管理業務
- 役割
契約が「成立した後」から、入居者が「退去するまで」(そして退去した後も)の全てをサポートする仕事。 - 業務
家賃集金、クレーム対応、建物の清掃・点検、退去時の精算。 - ゴール
入居者に長く快適に住んでもらい、物件の価値を「維持・向上させる」こと。(長期的な関係が続く)
簡単に言えば、「仲介」は「入居者を見つけるまで」の仕事、「管理」は「入居者が決まった後」の仕事、と覚えると分かりやすいでしょう。ただし、多くの不動産会社は仲介部門と管理部門の両方を持っています。
プロパティマネジメント(PM)やリーシングマネジメント(LM)との関係は?
少し専門的な話になりますが、不動産賃貸管理業務は、より広義の「プロパティマネジメント(PM)」の一部とされています。
プロパティマネジメント(PM)
- 「Property Management」の略で、日本語では「資産管理」と訳されます。
- 物件の物理的な維持管理(清掃、修繕など)だけでなく、家賃設定の見直し、大規模修繕の計画、収支レポートの作成など、オーナーの収益を最大化するための「経営的」な視点を持った管理業務を指します。
リーシングマネジメント(LM)
- 「Leasing Management」の略です。
- これは主に「空室を埋める」ことに特化した業務です。市場を分析し、適切な家賃を設定し、効果的な広告戦略(リーシング)を立てて、仲介会社と連携して入居者募集を強力に進める役割を指します。
初心者のうちは、「不動産賃貸管理業務は、PMやLMといった専門的な役割も含む、賃貸経営のトータルサポートなんだな」と理解しておけば問題ありません。
不動産賃貸管理の具体的な業務内容【時系列で徹底解説】
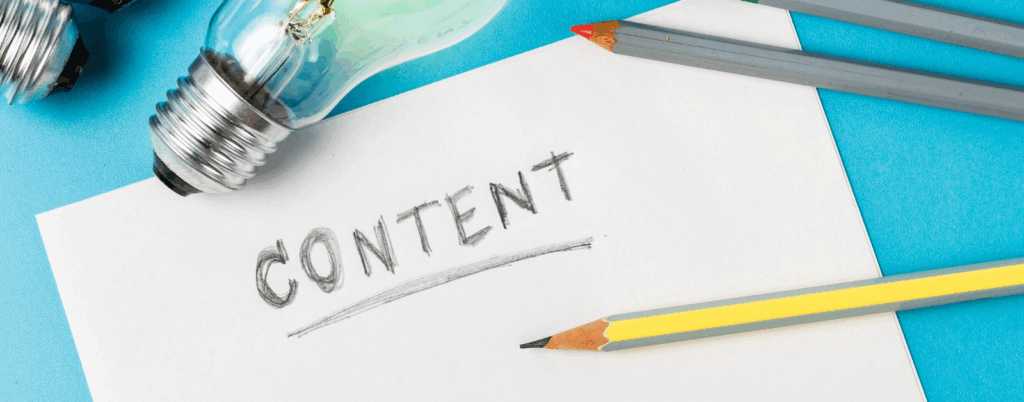
では、不動産賃貸管理業務の具体的な仕事内容を、入居者が決まってから退去するまでの「時系列」に沿って4つのステップで詳しく見ていきましょう。
【ステップ1 – 入居者募集〜契約】空室を埋めるための業務
オーナーにとって最大の課題である「空室」を埋めるための業務です。
募集条件の決定と広告宣伝(リーシング)
周辺の家賃相場や競合物件の状況を調査し、オーナーに「この家賃なら決まりやすい」「敷金・礼金はこうしましょう」といった募集条件を提案します。条件が決まったら、物件情報サイト(SUUMOやHOME’Sなど)に魅力的な写真や紹介文を掲載し、他の不動産仲介会社にも情報を流して、広く入居者を募集します。
内見対応と入居審査
入居希望者から問い合わせがあれば、実際に部屋を案内(内見)します。気に入ってもらえたら、入居申込書を受け取り、「家賃をきちんと払えるか(収入)」「トラブルを起こさない人か」などを確認する「入居審査」を行います。必要に応じて保証会社とも連携します。
賃貸借契約の締結と鍵の引き渡し
審査が通ったら、入居者に対して物件の重要なルールや契約内容を説明する「重要事項説明(※宅建士の独占業務)」を行い、賃貸借契約書を取り交わします。初期費用(敷金、礼金、前家賃など)の入金を確認した後、鍵を引き渡して、ステップ1は完了です。
【ステップ2 – 入居中】安定した経営を支える業務
入居者が住み始めてからが、不動産賃貸管理業務の本番です。
家賃の集金と送金・滞納者への督促
毎月決まった日に入居者から家賃を集金し、管理手数料などを差し引いた金額をオーナーの口座へ送金します。もし家賃の支払いが遅れている入居者がいれば、電話や書面で「督促(とくそく)」を行います。これは精神的にも負担が大きいため、管理会社が代行する大きなメリットの一つです。
入居者からのクレームやトラブル対応(騒音・漏水など)
「お湯が出ない」「上の階がうるさい」「水漏れが起きた」といった、入居者からのクレームや緊急トラブルの一次窓口となります。状況を確認し、必要であれば専門業者を手配し、他の入居者との間に入って調整を行うなど、迅速な対応が求められます。
契約更新・解約の手続き
2年に1度などの契約更新時期が近づいたら、入居者に更新の意思確認を行い、必要な書類の取り交わしや更新料の徴収を行います。逆に入居者から「引っ越したい」と解約の連絡があれば、退去日の調整や手続きを進めます。
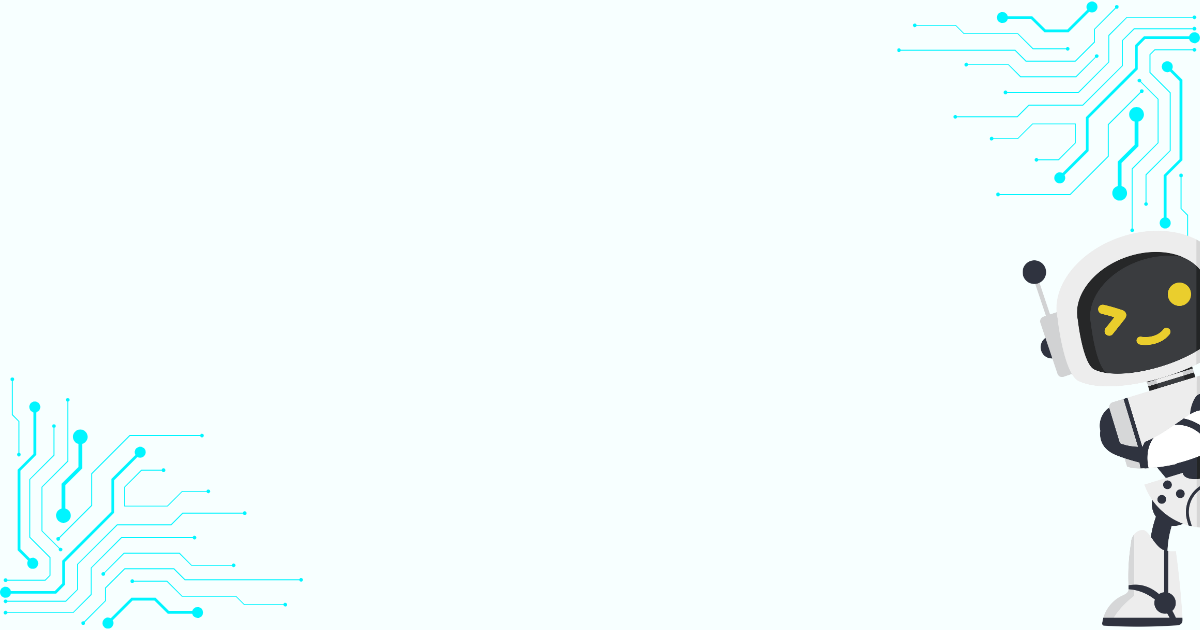

【ステップ3 – 建物・設備の維持管理】物件価値を守る業務
入居者が快適に暮らせるよう、また物件の資産価値が下がらないよう、建物を「維持」する業務も欠かせません。
日常清掃や定期点検(法定点検含む)
エントランスや廊下、ゴミ置き場などの共用部分をきれいに保つための「日常清掃」や「定期清掃」を手配します。また、法律で定められた消防設備点検やエレベーター点検、貯水槽清掃などを計画的に実施し、役所への報告なども行います。
故障時の修繕手配と業者調整
「エアコンが壊れた」「共用部の電気が切れた」といった設備の故障が発生した際に、修理業者を手配します。複数の業者から見積もりを取り、オーナーに費用や内容を報告・相談した上で、工事に立ち会います。
長期修繕計画の立案とリフォーム・リノベーション提案
建物は時間とともに老朽化します。10年後、15年後に必要となる「外壁塗装」や「屋上防水」といった大規模な修繕に備えて、長期的な修繕計画と資金積立をオーナーに提案します。また、空室が長く続いている部屋に対しては、時代に合わせて間取りを変更する「リノベーション」などを提案することもあります。
【ステップ4 – 退去時】次の入居につなげる業務
入居者が退去する際の「出口」をしっかり管理する業務です。
退去の立ち会いと原状回復の査定
入居者が引っ越す日に、部屋の状態を一緒に確認(退去立ち会い)します。タバコのヤニ汚れ、壁の穴、床の大きな傷など、入居者の故意・過失による損傷がないかをチェックし、「原状回復(げんじょうかいふく)」の範囲を査定します。
敷金の精算と原状回復工事の手配
査定に基づき、原状回復にかかる費用を見積もります。入居者から預かっていた敷金からその費用を差し引き、残金があれば返金する「敷金精算」を行います。同時に、次の入居者を迎えるために、部屋をきれいにするクリーニングやクロスの張り替え工事を手配し、ステップ1の「入居者募集」に戻ります。
不動産賃貸管理の主な形態「自主管理」と「委託管理」の違い
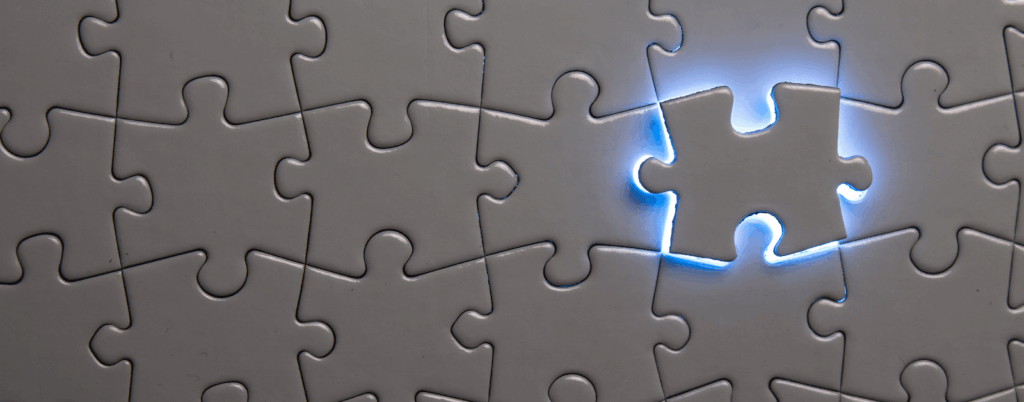
これらの不動産賃貸管理業務を誰が行うかによって、大きく2つの形態に分かれます。それが「自主管理」と「委託管理」です。
オーナー自ら行う「自主管理」のメリット・デメリット
「自主管理」とは、前述した全ての業務(募集、集金、クレーム対応、清掃、退去精算など)を、オーナー自身が行う形態です。
メリット
- 管理委託費用がかからない:管理会社に支払う手数料(一般的に家賃の3%〜7%程度)が不要なため、手残りの収益が最大化されます。
- 経営のノウハウが身につく:入居者対応や業者手配を自ら行うことで、賃貸経営に関する実践的な知識や経験が直接蓄積されます。
デメリット
- 手間と時間が非常にかかる:特にクレームやトラブルは曜日や時間を問わず発生するため、常に対応に追われる可能性があります。
- 専門知識が必要:家賃滞納時の法的手続きや、原状回復のガイドラインなど、専門知識がないと入居者とトラブルになりやすいです。
- 精神的負担が大きい:入居者からの直接的なクレームや家賃督促は、精神的に大きなストレスとなります。
管理会社に任せる「委託管理」のメリット・デメリット
「委託管理」とは、不動産賃貸管理業務のほとんどを、専門の不動産管理会社に手数料(管理委託料)を支払って任せる形態です。現在、多くのオーナーがこの形態を選んでいます。
メリット
- 手間と時間から解放される:面倒な実務のほぼ全てを代行してもらえるため、オーナーは本業に集中できます(いわゆる「大家業」の不労所得化)。
- 専門的な対応による安心感:滞納督促や法律が絡むトラブルも、プロが適切に対応してくれるため安心です。
- 客付け(募集)に強い場合も:管理会社が仲介部門も持っている場合、空室が出た際に優先的に入居者を見つけてくれる可能性があります。
デメリット
- 管理委託費用がかかる:毎月、家賃収入の3%〜7%程度の費用が発生します。
- 管理会社の質に左右される:管理会社の対応が悪いと、逆に入居者の不満が溜まり、退去が増えてしまうリスクがあります。
(補足)「サブリース(一括借り上げ)」との明確な違い
「委託管理」とよく似た言葉に「サブリース(一括借り上げ)」があります。これは不動産賃貸管理業務とは根本的に仕組みが異なります。
委託管理
- 契約の相手方:オーナー ⇔ 入居者
- 管理会社は「代行」するだけ。
- 収益:家賃収入から「管理手数料」が引かれる。(空室時は家賃収入ゼロ)
サブリース
- 契約の相手方:オーナー ⇔ サブリース会社 ⇔ 入居者(転貸)
- サブリース会社がオーナーから部屋を「借り上げ」て、それを入居者に「又貸し」します。
- 収益:空室に関わらず、オーナーはサブリース会社から「一定の保証賃料」(相場の80〜90%)を受け取る。(空室リスクを会社が負う)
サブリースは空室リスクがない反面、手数料が割高で、数年ごとに賃料見直しのリスクがあるなど、委託管理とは全く別の契約形態だと理解しておきましょう。


不動産賃貸管理業務の「やりがい」と「きつい点」
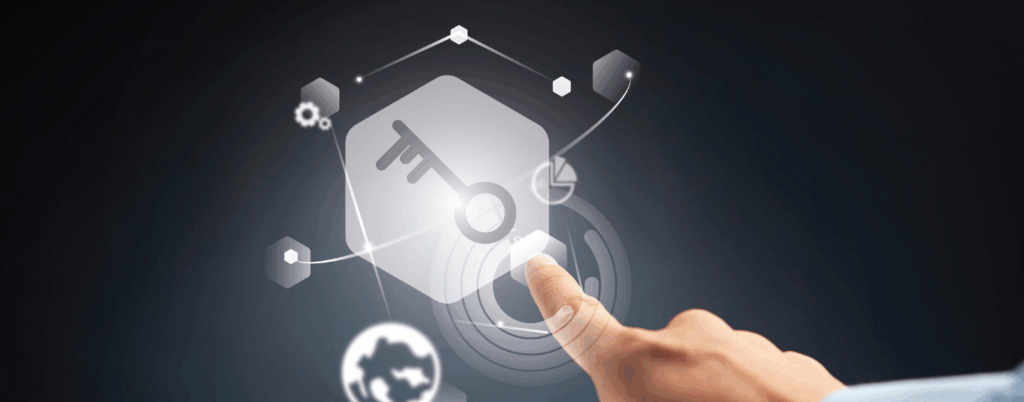
ここでは、主に不動産業界への就職・転職を考えている初心者向けに、不動産賃貸管理業務という「仕事」の側面から、その魅力を解説します。
不動産賃貸管理業務の主な「やりがい」
地味なイメージを持たれがちな不動産賃貸管理業務ですが、非常に大きなやりがいがあります。
オーナーと入居者双方から感謝される
トラブルを迅速に解決すれば入居者から「ありがとう、助かった」、空室を早期に決めたり、修繕提案で物件価値が上がったりすればオーナーから「あなたに任せて良かった」と、直接感謝の言葉をもらえる機会が多い仕事です。双方の間に立ち、調整役として頼りにされる存在になれます。
幅広い知識と対応力が身につく
家賃管理(金融)、滞納督促(法律)、建物修繕(建築・設備)、入居者対応(コミュニケーション)など、関わる業務が非常に多岐にわたるため、不動産に関する幅広く深い知識が身につきます。キャリアアップにも非常に有利です。
不動産賃貸管理業務の「きつい点」や大変さ
もちろん、大変な側面もあります。
クレームや突発的なトラブル対応
「水漏れ」「騒音」「鍵をなくした」など、予期せぬトラブルやクレームの電話は、時として休日や夜間にも入ることがあります(会社によります)。冷静に状況を判断し、迅速に対応するストレス耐性が求められます。
家賃滞納者への督促業務
家賃を支払ってくれない入居者への督促は、精神的に最もきつい業務の一つです。事務的に進めるだけでなく、相手の事情を聞きながら、時には毅然とした態度で交渉する必要があり、メンタル的な強さが求められます。
どんな人が向いている?不動産賃貸管理業務に必要なスキル
不動産賃貸管理業務は、派手な営業(仲介)とは異なり、コツコツとした事務処理能力と、突発的な事態に対応する柔軟性が求められる仕事です。
- コミュニケーション能力
オーナー、入居者、修理業者など、多くの人と円滑に話を進める調整力。 - マルチタスク能力
複数の物件の、複数の業務(集金、修繕手配、募集など)を同時に進める管理能力。 - 誠実さと責任感
オーナーの大切な資産を預かり、入居者の生活を支えるという責任感。
「自分が前に出るより、人をサポートするのが好き」「物事を順序立てて処理するのが得意」という人には、非常に向いている仕事と言えるでしょう。
不動産賃貸管理業務に関わる法律と「賃貸不動産経営管理士」の役割
近年、この不動産賃貸管理業務の重要性が国にも認められ、新しい法律や国家資格が整備されました。
なぜ今注目?「賃貸住宅管理業法」とは
背景には、サブリース業者による家賃不払いや、管理会社によるずさんな対応といったトラブルが社会問題化したことがあります。
そこで2021年6月に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(通称:賃貸住宅管理業法)」が施行されました。これは、一定戸数(200戸)以上の物件を管理する業者を「登録制」にし、国のルールのもとで適正に業務を行うよう義務付けた法律です。この法律により、不動産賃貸管理業務の社会的な重要性が格段に高まりました。
「賃貸不動産経営管理士」とは?設置義務化の背景
この新しい法律(賃貸住宅管理業法)において、「管理業者の事務所ごとに、専門知識を持つ者を必ず1人以上配置しなさい」と定められました。その「専門知識を持つ者」として認められたのが、「賃貸不動産経営管理士(ちんたいふどうさんけいえいかんりし)」という国家資格です。
これにより、以前は民間資格だった賃貸不動産経営管理士の需要と注目が一気に高まりました。
賃貸不動産経営管理士の「独占業務」をわかりやすく解説
賃貸不動産経営管理士には、宅建士の「重要事項説明」のような、その資格を持つ人しかできない「独占業務」が2つあります。
1.管理受託契約に関する重要事項説明
管理会社がオーナー(大家さん)から「管理業務を任せてください」という契約(管理受託契約)を結ぶ前に、オーナーに対して「業務の具体的な内容はこうです」「費用はこうです」と書面で詳しく説明する業務。
2.上記、重要事項説明書面への記名・押印
その説明書面に、賃貸不動産経営管理士として「私が責任を持って説明しました」という証拠として、名前を書いてハンコを押すこと。
つまり、オーナーが管理会社と契約する際の「入口」で、専門家が必ず介在し、オーナーが不利な契約を結ばないように守る役割が与えられたのです。
「管理業務主任者」や「宅建士」との業務範囲の違い
不動産には似た資格が多くて混乱しますよね。簡単に役割を整理します。
宅建士(宅地建物取引士)
- フィールド
不動産「取引」(売買・交換・賃貸の仲介)の専門家。 - 独占業務
重要事項説明(入居者・購入者に対して)。
管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)
- フィールド
「分譲マンション」の管理の専門家。 - 独占業務
分譲マンションの管理組合(区分所有者の集まり)に対する重要事項説明など。
賃貸不動産経営管理士
- フィールド
「賃貸住宅」(アパート・マンション)の管理の専門家。 - 独占業務
管理受託契約の重要事項説明(オーナーに対して)。
簡単に言えば、「宅建士」は取引、「管理業務主任者」は分譲マンションの管理、「賃貸不動産経営管理士」は賃貸住宅の管理、と棲み分けがされています。
まとめ|不動産賃貸管理業務は賃貸経営の安定を支える重要な仕事
今回は、「不動産賃貸管理業務とは何か」という基本から、具体的な仕事内容、管理形態の違い、そして関連する国家資格「賃貸不動産経営管理士」まで、初心者向けに網羅的に解説しました。
- 不動産賃貸管理業務は、「仲介」とは異なり、入居者が決まった後の経営実務(集金・クレーム・維持管理・退去)をサポートする仕事。
- 業務は多岐にわたるため、オーナーは「自主管理」の手間と「委託管理」の費用を天秤にかける必要がある。
- 転職者にとっては、きつい面もあるが、幅広い知識が身につき、オーナーと入居者双方から感謝される「やりがい」のある仕事である。
- 「賃貸住宅管理業法」の施行により、賃貸不動産経営管理士の役割が明確化され、業界全体の重要性が高まっている。
この記事を通じて、「不動産賃貸管理業務」の全体像がスッキリと整理できていれば幸いです。
もしあなたが物件の管理に悩むオーナーであれば、まずは複数の管理会社に「どんな業務をどこまでやってくれるのか」を相談し、見積もりを取ることから始めてみましょう。
もしあなたが不動産業界へのキャリアを考えているなら、この不動産賃貸管理業務という安定したニーズのある分野、そして将来性のある「賃貸不動産経営管理士」の資格取得を、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。