
「AI作曲」という言葉を耳にする機会が増え、「音楽の知識がない自分にも曲が作れるのかな?」と興味をお持ちではないでしょうか。この記事では、そんなAI作曲の初心者向けに、基本的な仕組みから無料で使えるツールの始め方、そして多くの方が不安に思う著作権や商用利用のルールまで、専門用語を一切使わずに解説します。読み終える頃には、AI作曲の全体像がわかり、自分にもできそうだというイメージが掴めるでしょう。著作権の不安なく、あなただけのオリジナル曲を作るための、安全で楽しい第一歩を踏み出せるようになるでしょう。
AI作曲とは?基本の仕組みからメリット・デメリットまで解説
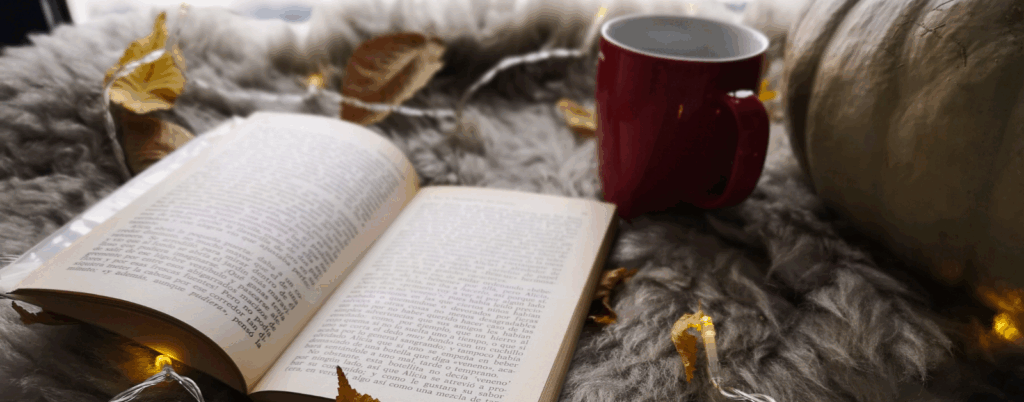
まずは「AI作曲って、そもそも何?」という疑問から解消していきましょう。このセクションでは、AI作曲の全体像を掴み、「作曲」という言葉に対する心のハードルをぐっと下げていきます。
AI作曲とは?身近な例でわかりやすく解説
AI作曲とは、ひとことで言えば「文章で指示するだけで、AIが全自動でオリジナル曲のアイデアを生成してくれる革新的な技術」のことです。
楽器が弾けなくても、音楽理論を知らなくても、まったく問題ありません。「明るい雰囲気のJ-POP」「切ない感じのピアノ曲」といったイメージを言葉で伝えるだけで、AIがものの数分でボーカル入りの本格的な楽曲や、動画にぴったりのBGMを作り出してくれます。
もっと身近な例で言うと、優秀なシェフ(AI)に「濃厚なカルボナーラが食べたい」と注文(指示)するだけで、あなたがレシピ(音楽理論)や調理法(楽器演奏)を知らなくても、言葉の指示だけで曲のアイデアをすぐに試せるツールのようなものです。あなたはただ、どんな料理が食べたいかを伝えるだけでいいのです。
AI はどうやって作曲するの?その仕組みを3ステップで紹介
では、なぜAIにそんなことができるのでしょうか?その秘密は、AIが事前に大量の音楽を”聴き込んで”勉強しているから。その仕組みを、簡単に3つのステップでご紹介します。
AIは、開発段階でクラシックから最新のポップスまで、膨大な数の楽曲データを学習します。「このコード進行の次はこのメロディが来やすい」「このジャンルではこのリズムが使われる」といった、音楽のあらゆるパターンを統計的にインプットしています。
あなたが「壮大なオーケストラ風の曲」と入力すると、AIは「壮大」「オーケストラ」という言葉が、学習したどの音楽パターンと結びついているかを分析します。そして、指示に最も近い音楽スタイルを導き出します。
最後に、学習した無数のパターンを基に、あなたの指示に沿った新しいメロディ、ハーモニー、リズムをゼロから組み立てていきます。これにより、世界に一つだけのオリジナル曲が生成されるのです。
音楽知識が不要!AI作曲の3つのメリット
AI作曲には、これまでの音楽制作の常識を覆すような、大きなメリットがあります。
プロに作曲を依頼すれば数週間かかることも珍しくありませんが、AI作曲ならわずか数分で完成します。思いついたイメージをすぐに形にできるスピード感は、最大の魅力です。
この記事で何度もお伝えしている通り、音楽理論や楽器の経験は一切必要ありません。必要なのは「こんな曲が欲しい」というイメージだけ。誰もが作曲家になれる時代が来たのです。
YouTube動画のBGMなどを外注すれば数万円かかることもありますが、AI作曲なら無料、もしくは月額数千円程度のサブスクリプションで高品質な楽曲が作り放題になります。
知っておきたいAI作曲のデメリットや注意点
もちろん、AI作曲は万能ではありません。知っておきたいデメリットや注意点も正直にお伝えします。
「サビの最後の音を半音だけ上げたい」といった、ピンポイントでの細かな修正はまだ苦手な場合が多いです。基本的にはAIが生み出したものを受け入れる形になります。
AIが作った曲の権利関係は、従来の音楽とは少し考え方が異なります。これは非常に重要なポイントなので、次の章で徹底的に解説します。
AIは指示を基に作曲しますが、偶発的に生まれる部分も大きいため、100%イメージ通りの曲が一発で出てくるとは限りません。何度か指示を変えて試す「ガチャ」のような側面もあります。
【最重要】AI作曲の著作権と商用利用で失敗しないための知識

AI作曲を使う上で、誰もが最も不安に思い、つまずきやすいのが「著作権」の問題です。ここで正しい知識を身につけて、法的なリスクなく、安心して創作活動を楽しみましょう。
基本原則 AIが作った曲の著作権は誰のもの?
まず大原則として、現在の日本の法律では「AI“だけ”が自動で生成したもの」に著作権は発生しない、というのが一般的な見解です。
なぜなら、著作権法は人間の「思想又は感情」が創作的に表現されたものを保護する法律だからです。AIは思想や感情を持たないため、AIによる生成物は著作権の保護対象外とされています。
しかし、ここからが重要です。 法律で著作権が発生しないからといって、自由に使えるわけではありません。AI作曲サービスを提供している運営会社が、「利用規約」で独自のルールを定めており、私たちはそのルールに従う必要があります。結論として、AIが生成した楽曲を利用する際は、法律の考え方を基本としつつも、まずは各サービスが定めている『利用規約』に従う必要がある、と覚えておきましょう。
商用利用はできる?YouTube収益化やBGM活用のポイント
「作った曲を収益化しているYouTubeチャンネルで使いたい」「お店のBGMとして流したい」といった商用利用は可能なのでしょうか?
結論から言うと、「有料プランに加入すれば、ほとんどのサービスで商用利用OK」となっています。
多くのAI作曲サービスは、無料プランでは「個人利用のみ(非商用)」に限定し、月額料金を支払う有料プランユーザーにのみ商用利用を許可するビジネスモデルを採用しています。無料プランで作った曲を商用利用すると規約違反になるケースがほとんどなので、十分に注意してください。
また、YouTubeで利用する際は「Content ID」の問題も考慮が必要です。サービスによっては、AIが作った曲をContent IDに登録することを禁止している場合もあります。
安全に使うために!利用規約で確認すべき必須チェックリスト
利用規約は英語で書かれていることも多く、読むのが大変ですよね。しかし、ここを確認しないと後でトラブルになりかねません。最低限、以下の4点は必ずチェックするようにしましょう。
- ✅ 商用利用(Commercial Use)は許可されているか?
あなたの利用目的(YouTube収益化、BGM活用など)が許可されているかを確認します。 - ✅ 著作権の帰属(Copyright Ownership)はどうなっているか?
生成した楽曲の権利が「ユーザーに譲渡される」のか、それとも「運営会社が保持したまま、ユーザーに使用を許可する」のかを確認します。 - ✅ クレジット表記(Attribution)は必要か?
楽曲を利用する際に、「作曲 by 〇〇(サービス名)」といった表記が必要かどうかを確認します。 - ✅ 禁止事項(Prohibited Uses)に該当しないか?
生成した楽曲をそのまま販売することや、他者を誹謗中傷するコンテンツへの利用を禁止している場合があります。
意図せず著作権侵害しないために知っておくべきこと
AI作曲で最も避けるべきなのは、既存の楽曲に酷似したものを意図せず生成し、著作権侵害を指摘されてしまうことです。これを避けるために、以下の点を必ず守ってください。また、生成された曲が既存の楽曲に偶然酷似していないか、公開・利用する前に一度確認する習慣をつけることも、意図しないトラブルを避けるために有効です。
「既存のアーティスト名、バンド名、曲名をプロンプトに直接入力しない」
例えば、「米津玄師風の曲」といった指示を出すと、AIが学習データの中からそのアーティストの作風に強く寄せた結果、偶然似すぎてしまうリスクが高まります。作風を真似たい場合は、「切ない歌詞のアップテンポなエレクトロポップ」のように、具体的な音楽的特徴で指示するようにしましょう。
【実践】知識ゼロから始めるAI作曲の簡単な始め方(Suno AI編)
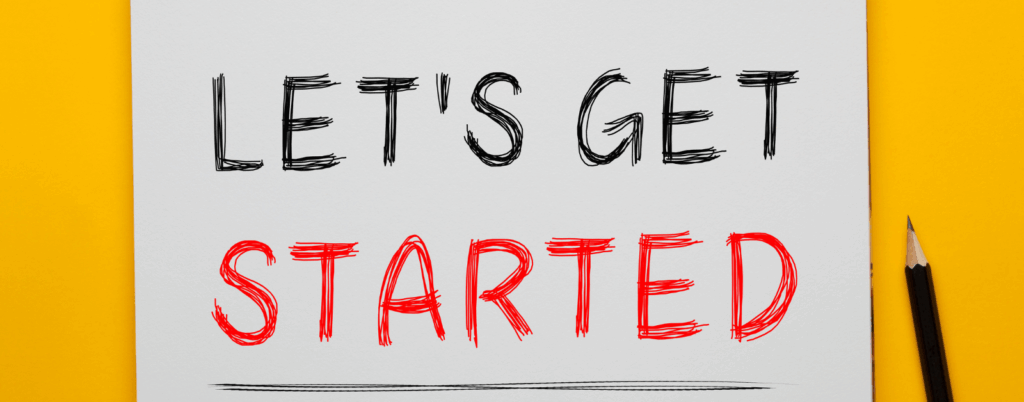
お待たせしました!ここからは、いよいよ実際にAI作曲を体験してみましょう。今回は、日本語の歌のクオリティが非常に高いと評判で、初心者にも使いやすい「Suno AI」を例に、アカウント登録から曲の完成までを徹底的にガイドします。
ステップ1 Suno AIにアクセスしてアカウント登録する
まずはSuno AIの公式サイトにアクセスします。
「Make a song」と書かれたボタンをクリックすると、アカウント登録画面に進みます。Google、Discord、Microsoftのアカウントが使えますが、特に理由がなければGoogleアカウントで登録するのが一番スムーズです。
お持ちのアカウントを選択すれば、登録はすぐに完了。難しい入力は一切ありません。
ステップ2 曲のイメージ(プロンプト)を入力するコツ
ログインすると、曲を作成する画面が表示されます。
中央にある「Song Description」というボックスに、作りたい曲のイメージを日本語で入力します。例えば、「雨上がりの澄んだ空を見上げるような、爽やかで希望に満ちたJ-POP」のように入力してみましょう。入力したら、右側にある「Create」ボタンをクリックします。
よりイメージに近い曲を作るには、以下のような要素を組み合わせるのがコツです。
- ジャンル:J-POP, ロック, Lo-fi Hip Hop, ジャズ, etc.
- 雰囲気:明るい, 寂しい, 壮大, 落ち着く, etc.
- 使用楽器:アコースティックギター, ピアノ, シンセサイザー, etc.
- テンポ:アップテンポ, スローバラード, ミディアムテンポ, etc.
【応用編】歌詞を自分で入れたい場合 「Custom Mode」というスイッチをオンにすると、自分で書いた歌詞や、AIに作ってもらった歌詞を入力するボックスが表示されます。ここに歌詞を入れれば、その通りの歌を歌ってくれます。
ステップ3 生成された曲の確認と簡単な編集方法
「Create」ボタンを押して30秒〜1分ほど待つと、AIが2パターンの曲を提案してくれます。
左側の再生ボタンを押して、聴き比べてみましょう。イメージに近い方の曲が見つかったら、さらに編集を加えることも可能です。曲名の右側にある「…」ボタンを押すと、「Continue From This Song(この曲の続きを生成)」というメニューがあり、曲を長くしたり、サビを追加したりできます。
ステップ4 完成した曲をダウンロードして活用する
気に入った曲が完成したら、ダウンロードして保存しましょう。
曲の右側にある「…」ボタンから「Download」を選択すると、音声ファイル(MP3)または動画ファイル(MP4)形式でダウンロードできます。これで、あなただけのオリジナル曲が手に入りました!YouTube動画のBGMにしたり、SNSでシェアしたりして楽しんでみましょう。
【無料】初心者におすすめのAI作曲ツール・サイト3選

Suno AIでAI作曲の楽しさを体験したところで、他にも特徴的なサービスをいくつかご紹介します。目的によって使い分けることで、あなたの創作の幅がさらに広がります。
歌モノなら一番人気!「Suno AI」
- 得意なこと: ボーカル入りの楽曲(特に日本語の歌詞)
- 日本語対応: 完璧に対応
- 無料プランの商用利用: 不可
- こんな人におすすめ: オリジナルの歌を作りたい人、とにかく手軽に始めたい人
先ほど実践で使った通り、簡単な指示だけで驚くほど自然な日本語の歌モノが作れるのが最大の特徴です。AI作曲の入門として、まず最初に試すべきサービスと言えるでしょう。
おしゃれなBGM制作に特化!「Soundraw」
- 得意なこと: BGM、インストゥルメンタル楽曲
- 日本語対応: 一部対応
- 無料プランの商用利用: 不可
- こんな人におすすめ: YouTube動画や配信に使う高品質なBGMが欲しい人
ジャンルやムード、長さを選ぶだけで、プロが作ったようなクオリティのBGMを無限に生成してくれます。歌は作れませんが、BGM制作においては非常に強力なツールです。
鼻歌からでも作れる!「Boomy」
- 得意なこと: 実験的、ユニークな楽曲
- 日本語対応: 非対応
- 無料プランの商用利用: 不可
- こんな人におすすめ: 自分のメロディをAIにアレンジしてほしい人、予想外の曲を楽しみたい人
自分で考えたメロディを鼻歌で録音し、それを基にAIが伴奏をつけたり、アレンジを加えたりしてくれるユニークな機能を持っています(ベータ機能)。
【比較表】目的別におすすめのAI作曲ツールはこれ!
| ツール名 | 得意なこと | 日本語対応 | 無料プラン商用利用 | こんな人におすすめ |
| Suno AI | ボーカル曲 | ◎ | ✕ | オリジナルソングを作りたい人 |
| Soundraw | BGM/インスト | 〇 | ✕ | 高品質なBGMが欲しい人 |
| Boomy | 実験的な曲 | ✕ | ✕ | 自分のメロディを基に作りたい人 |
※AI作曲サービスの料金プランや商用利用の可否といった利用規約は、頻繁に更新される可能性があります。実際に利用する際は、必ず各サービスの公式サイトで最新の規約を確認するようにしてください。
AI作曲に関するよくある質問(Q&A)
最後に、AI作曲を始めるにあたって多くの方が抱く、細かい疑問にお答えします。
Q. スマートフォンのアプリだけでも使えますか?
A. はい、使えます。
今回ご紹介したSuno AIには公式のスマートフォンアプリ(iOS/Android)があります。また、多くのAI作曲ツールはWebブラウザ上で動作するため、PCがなくてもスマホからアクセスして利用することが可能です。
Q. 日本語の歌詞で自然な歌を生成できますか?
A. はい、できます。
特にSuno AIは、非常に流暢で自然な日本語の歌を生成することで高く評価されています。他のツールはまだ日本語対応が不十分な場合もありますが、技術の進歩は非常に速いため、今後さらに多くのツールが対応してくるでしょう。
Q. 作った曲をTuneCoreなどで販売・配信することはできますか?
A. これは各サービスの利用規約を必ず確認する必要があります。
例えば、Suno AIは有料プランに加入していれば、生成した楽曲をSpotifyやApple Musicなどで配信することを許可しています。しかし、サービスによっては禁止している場合もあるため、楽曲の販売や配信を考えている場合は、規約の「商用利用」や「所有権」の項目を事前にしっかりと読み込んでください。
まとめ
この記事では、AI作曲の基本から、最も重要な著作権の話、そして具体的な始め方までを網羅的に解説してきました。
- AI作曲は、音楽知識がなくても言葉の指示だけで誰でもオリジナル曲が作れる画期的な技術
- 著作権は複雑だが、サービスの利用規約、特に「商用利用」の項目を確認することが何よりも重要
- Suno AIを使えば、無料で、しかもアカウント登録から数分で最初の1曲を完成させることができる
「作曲なんて自分には縁のない世界だ」と思っていた方も、この記事を読んで「意外と簡単そうかも」「ちょっと試してみようかな」と感じていただけたのではないでしょうか。
難しく考える必要はありません。まずは遊び感覚で、あなたが見た夢の話や、今日食べたランチの感想をAIに伝えてみてください。きっとAIは、あなたも知らなかった創造性を引き出し、素敵な一曲を生み出すきっかけを与えてくれるでしょう。
さあ、この記事を閉じて、あなただけの最初の曲作りに挑戦してみましょう!


