
ChatGPTなどの生成AIを使っていて、回答に「あれ?」と違和感を覚えたり、明らかに事実と異なる情報が出力されたりした経験はありませんか?
今、ビジネスシーンでも大きな注目と同時に「懸念」を集めている「ハルシネーション」について解説します。
この記事では、AIが事実に基づかない情報を生成する「ハルシネーションとは何か」、その発生の「仕組み」、そして私たちが知っておくべき「具体的なリスク」を、IT初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。
AIの「嘘」に気づかずに利用してしまうリスクは、ビジネスでもプライベートでも深刻な問題になりかねません。本記事を読めば、AIがなぜ間違えるのか、そして私たちがどう対策すべきかが明確に分かります。
読み終える頃には、ハルシネーションへの漠然とした不安が解消され、AIを「安全で優秀なアシスタント」として正しく活用するための一歩を踏み出せるようになります。
ハルシネーションとは?AIが「嘘」をつく現象をわかりやすく解説

ハルシネーションの基本的な意味
ハルシネーションとは、一言でいうと「生成AIが、事実に基づかない情報や文脈と無関係な情報を、あたかも事実であるかのように自信満々に生成する(回答する)現象」のことです。
AIは質問に対して非常に流暢で、もっともらしい文章を作成します。しかし、その内容をよく調べてみると、実際には存在しない人物名、架空の事件、間違った日付や統計データが平然と含まれていることがあるのです。
これがハルシネーションの最も恐ろしい点です。AIは「分かりません」と答える代わりに、それらしい「嘘」を堂々とついてしまうのです。
なぜ「幻覚(ハルシネーション)」と呼ばれるのか
「ハルシネーション(Hallucination)」という言葉は、もともと医療の分野で「幻覚」や「幻聴」を意味する専門用語です。
AIが「まるで幻覚を見ているかのように、現実には存在しないもの(情報)を語り出す」様子が、この言葉の使われ方に似ていることから、AIの分野でもこの用語が使われるようになりました。
人間が疲れている時に幻覚を見ることがあるように、AIもその特性上、事実とは異なる「幻覚」を生成してしまうのです。
【具体例】ChatGPTなどで見られるハルシネーションの発生事例
ハルシネーションは、私たちが日常的に使うAIツールでも頻繁に発生しています。
事例1|架空の情報をでっち上げる
質問
「〇〇(マイナーな地方都市)でおすすめのイタリアンレストランは?」
回答
「『リストランテ・〇〇』が人気です。住所は〇〇で、シェフはイタリアで修行した〇〇氏です。」
→実際
調べてみると、そのレストランも住所もシェフも実在しない。AIが「それらしいレストラン情報」を創作してしまった。
事例2|事実を巧妙に間違える
質問
「作家〇〇の代表作を教えて」
回答
「代表作は『〇〇(実在の作品)』『△△(実在の作品)』『××(架空の作品)』です。」
→実際
実在する作品に交ぜて、巧妙に架空の作品名を紛れ込ませる。
事例3|最新の情報を間違える
質問
「昨日の〇〇の試合結果は?」
回答
「AチームがBチームに3対1で勝利しました。」
→実際
本当はBチームが勝っていたり、スコアが違ったりする。
ハルシネーションは「間違い」や「バグ」と何が違うのか
ここで重要なのは、ハルシネーションは、プログラムの「バグ(不具合)」や「単純な計算間違い」とは根本的に異なるという点です。
- バグ: プログラムの設計ミスや記述ミス。AIが停止したり、エラーメッセージが出たりします。
- ハルシネーション: AIはプログラムとしては正常に動作しています。設計通りに「次に来る確率が最も高い言葉」を選び続けた結果、内容が「事実と異なってしまった」状態です。
つまり、AIは「間違えよう」と思って間違えているわけでも、システムが壊れているわけでもありません。AIが持つ「仕組み」そのものから、ハルシネーションは必然的に発生してしまうのです。
なぜハルシネーションは起こるのか?生成AIの仕組みと発生原因
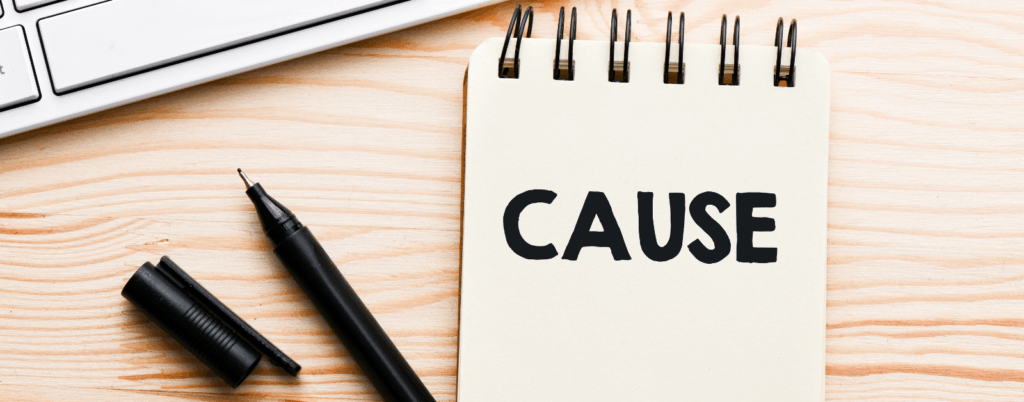
では、なぜ賢いはずのAIが、ハルシネーションを起こしてしまうのでしょうか。その答えは、生成AIが文章を作る「仕組み」にあります。
【重要】AIは「理解」しているのではなく「予測」している
私たち人間は、「日本の首都は東京です」という文章を読んだ時、日本の地図や東京の風景、首都という「概念」を理解します。
しかし、今の生成AIは違います。AIは「日本の首都は」という言葉の次に、「東京」「大阪」「京都」など、どの言葉が来る確率が最も高いかを計算しているに過ぎません。
インターネット上の膨大なテキスト(学習データ)を統計的に処理した結果、「日本の首都は」の後には「東京」という単語が来る確率が圧倒的に高いことを知っているだけなのです。
生成AIが文章を作る基本的な仕組み(比喩を使った簡単な解説)
生成AIの仕組みは、スマートフォンのキーボードにある「予測変換」機能の、途方もなく高性能なものだとイメージしてください。
- 「ありがとう」と入力すると、次に「ございます」が予測されます。
- 「明日の天気は」と入力すると、次に「晴れ」が予測されます。
生成AIは、これを文章全体で行います。 「ハルシネーションとは、」と入力されれば、次に「生成AIが、」と続く確率が高い、その次は「事実に基づかない」と続く確率が高い……というように、単語から単語へと確率的に「次に来る言葉」を予測し続けているのが、AIが回答を生成する正体です。
この仕組みが、ハルシネーションを生む根本的な原因となります。
ハルシネーションが発生する主な3つの原因
AIが「確率」で言葉を選んでいる以上、以下のような場合にハルシネーションが発生しやすくなります。
原因1 学習データの不足や偏り
AIは、学習したデータ(主にインターネット上の大量のテキスト)が知識のすべてです。 もし、学習データ自体が間違っていれば、AIも間違った情報を「正しい」ものとして学習してしまいます。また、ニッチな専門分野や、そもそもネット上に情報が少ないトピックについて質問されると、AIは少ない情報から「それらしい」回答を推測して埋めようとします。これがハルシネーションの元になります。
原因2 学習データが古い
多くの生成AI(特に無料版)は、学習したデータが「〇〇年〇月まで」と決まっています(これを「知識のカットオフ」と呼びます)。 そのため、それ以降に起こった出来事(例:最近のニュース、選挙結果、新製品)について質問すると、AIは古い情報に基づいて回答するか、情報を知らないにもかかわらず「知っているふり」をして架空の回答を生成してしまうのです。
原因3 複雑な指示や曖昧な質問(プロンプト)
ユーザーからの質問(プロンプト)が曖昧だったり、矛盾する内容を含んでいたりすると、AIは「どの確率に従うべきか」を迷ってしまいます。 その結果、文脈を正しく読み取れず、質問の意図とは異なる、ちぐはぐな回答や事実に基づかない回答(ハルシネーション)を生成しやすくなります。
AIは「事実かどうか」を判断するのが苦手
結論として、AIは「文章として流暢であること」を最優先事項としており、「その内容が事実として正しいかどうか」を検証する能力を(基本的には)持っていません。
AIにとって、事実も、巧妙な嘘も、学習データに存在し、統計的な確率が高ければ、どちらも「正解」として出力されてしまう可能性があるのです。
ハルシネーションの具体的なリスクとは?放置する危険性

「AIが嘘をつく」と聞いても、他人事のように感じるかもしれません。しかし、ハルシネーションを「ちょっとした間違い」と軽視して放置すると、日常生活やビジネスにおいて深刻なリスクを引き起こす可能性があります。
【個人編】日常生活や学習で起こりうるリスク
誤った知識や情報を信じてしまう
最も身近なリスクです。例えば、健康に関する情報をAIに尋ね、「〇〇は健康に良い」というAIの回答を鵜呑みにしたとします。もしそれがハルシネーションによるデタラメな情報だったら、健康を害する恐れさえあります。
レポートや課題で間違った内容を提出してしまう
学生が歴史のレポート作成のためにAIを使い、「〇〇の戦いについて教えて」と質問したとします。AIが架空の武将や存在しない合戦を回答に含めてしまい、それに気づかずレポートを提出すれば、評価が下がるどころか、不正を疑われるかもしれません。
【ビジネス編】業務利用で特に注意すべき重大なリスク
ビジネスシーンでのハルシネーションは、個人の失敗では済まされません。
誤った情報に基づく意思決定
例えば、あなたがマネージャーで、「競合他社Aの最新の動向を要約して」とAIに指示したとします。AIがハルシネーションを起こし、「競合A社は〇〇という新サービスを開始した」という架空の情報を生成したとしましょう。 もしあなたがその情報を信じ、自社の戦略を立ててしまったら、時間もコストも無駄にする、致命的な経営判断ミスに繋がります。
企業の信用失墜(例 顧客対応や公開情報での間違い)
- 顧客対応
カスタマーサポートがAIの回答を参考に、「その製品には〇〇という機能があります」と顧客に誤った案内をしてしまう。 - 公開情報
AIに書かせたブログ記事やプレスリリースに、架空の統計データや引用が含まれてしまう。
これらが発覚した場合、「あの会社はデタラメな情報を流している」として、企業の信用は一瞬で失墜します。
法的な問題(例 存在しない判例の引用)
これは実際に海外で起きた有名な事例ですが、ある弁護士がAI(ChatGPT)を使って裁判資料を作成した際、AIが「存在しない過去の判例」を複数引用してしまいました。 弁護士はそれに気づかず資料を裁判所に提出し、虚偽の情報を引用したとして大きな問題となり、制裁を受ける事態にまで発展しました。ハルシネーションは、時として法的な責任問題に直結するのです。
ハルシネーションへの対策とは?今日からできるリスク回避の方法
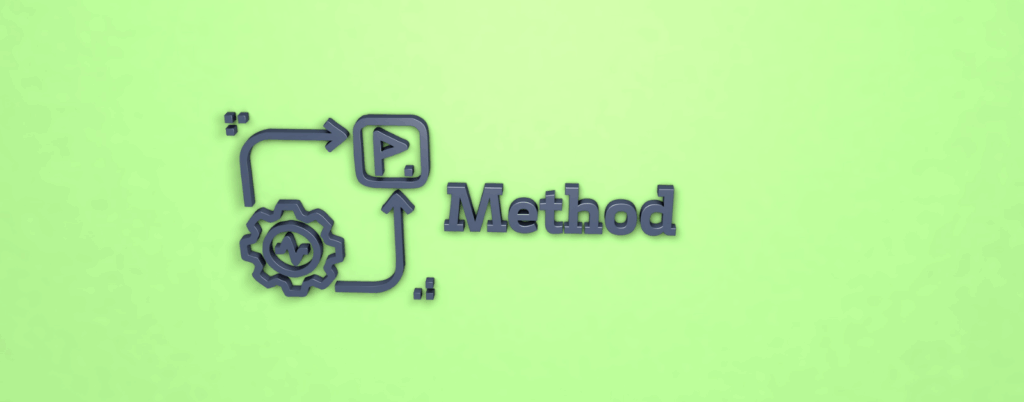
これほどのリスクがあると聞くと、AIを使うのが怖くなってしまうかもしれません。 しかし、心配は不要です。ハルシネーションは、その特性を知り、正しい「心構え」と「技術」で対策すれば、十分に管理できる現象です。
大前提 AIの回答は「下書き」または「壁打ち相手」と心得る
ハルシネーション対策で最も重要な心構えは、これです。
AIの回答を「完成品」や「答え」だと思わないこと。 AIは「優秀だが、時々平気で嘘をつくインターン生」や「アイデア出しを手伝ってくれる壁打ち相手」と捉えましょう。
AIが出してきた回答は、あくまで「下書き(ドラフト)」です。その下書きが事実として正しいかどうかを検証し、修正し、完成品に仕上げる「最後の責任」は、常にAIを使う「人間(あなた)」にあります。
ユーザー(私たち)がすぐに実践できる対策
この心構えを持った上で、今日からすぐに実践できる具体的な対策を4つご紹介します。
ファクトチェック(裏付け)を徹底する
AIの回答に出てきた固有名詞(人名、会社名、製品名)、数値(日付、統計、金額)、出来事(事件、歴史)などは、必ずGoogle検索などで別の信頼できる情報源(公式サイト、公的機関、大手メディア)を使って裏付けを取る習慣をつけましょう。 AIが「〇〇です」と答えたら、あなたは「本当に?」と疑って検索する。これが鉄則です。
情報源(ソース)や引用元をAIに尋ねる
AIの回答に対して、「その情報の情報源(ソース)や引用元、参考にしたURLを教えてください」と追加で質問してみましょう。 もしAIが「情報源は〇〇です」と具体的なURLや文献名を示せば、それを辿ってファクトチェックができます。もしAIが「分かりません」と答えたり、提示されたURLが偽物だったりした場合は、その回答がハルシネーションである可能性が非常に高いと判断できます。
質問の仕方(プロンプト)を工夫する
曖昧な質問はハルシネーションを誘発します。できるだけ具体的に、AIが迷わないように指示を出しましょう。
- 悪い例:「日本の経済について教えて」
- 良い例:「内閣府が発表している2024年第1四半期のGDP速報値を基に、日本の経済状況を要約してください」
このように、情報源や前提条件を具体的に指定することで、AIが「推測」する余地を減らし、事実に基づいた回答を引き出しやすくなります。
自分の知識や専門分野で活用する
AIのハルシネーションを最も簡単に見抜く方法は、あなたが既に詳しい知識を持っている分野でAIを使うことです。 例えば、あなたが不動産のプロなら、AIが不動産に関する「嘘」をついてもすぐに見抜けます。AIを「全く知らない分野の学習」に使うと思わぬ危険がありますが、「自分の専門分野の作業を効率化する(=下書きを作らせる)」ために使えば、ハルシネーションのリスクを最小限に抑えられます。
AI開発側(企業)の取り組み(RAGなど)
私たちユーザー側だけでなく、AIを提供する企業側もハルシネーションを減らす努力を続けています。 最近のAIでは、「RAG(ラグ)」と呼ばれる技術が主流になりつつあります。これは専門用語なので覚える必要はありませんが、「AIが回答を生成する前に、まず信頼できるデータベースや最新のインターネット情報を検索し、その見つけた事実情報『だけ』を基に回答を組み立てる」技術です。
この技術により、AIが「知ったかぶり」で嘘をつくことが劇的に減り、回答の信頼性が向上しています。
まとめ|ハルシネーションとはAIの限界を知り正しく活用する鍵
最後に、この記事の要点を振り返りましょう。
ハルシネーションを恐れず、AIと上手に付き合う
ハルシネーションとは、AIがその仕組み上(=言葉を予測しているだけ)、事実に基づかない情報を自信満々に生成してしまう現象のことです。
これはバグではなく、AIが持つ「特性」の一つです。そして、ハルシネーションを放置すれば、個人の誤解から企業の信用失墜まで、深刻なリスクを引き起こす可能性があります。
しかし、ハルシネーションを過度に恐れる必要はありません。 「AIは嘘をつくものだ」という限界を正しく知り、その上で「ファクトチェック」や「プロンプトの工夫」といった対策を講じれば、AIは私たちの生活や仕事を劇的に効率化してくれる強力なパートナーとなります。
リスクを理解してこそ、AIは最強のアシスタントになる
「ハルシネーションとは何か」を理解することは、AIの「弱点」を知ることです。そして、弱点を理解している人こそ、そのツールの「本当の強み」を最大限に引き出すことができます。
AIの回答を鵜呑みにするのではなく、AIを「優秀な下書きアシスタント」として使いこなす。 この記事を読み終えたあなたが、AIへの漠然とした不安を拭い去り、AIを賢く活用するための一歩を踏み出せることを願っています。


